近年、多くの企業が理念を社会に発信する場として授賞式を開催しています。授賞式は、受賞者に賞を授けることにとどまらず、広報PR活動として主催する企業を広く社会に知らせる機会として有効です。製品やサービスを直接的に知らせることはできなくても、これまで接点がなかったメディア関係者や生活者に対して効果的な広報PR活動をすることができます。
本記事では、なぜ授賞式を開催するのかといった目的を整理したうえで、どのような流れで開催に至るのか、また最適な企画内容などについて詳しくご紹介します。
授賞式とは
授賞式とは、企業や官公庁、自治体などが主催者となり、設定した賞のテーマにふさわしい内容や企業、人物に対して賞を授ける式典です。賞をもらう側ではなく、賞を授ける側が主体となるため、「授賞」という言葉が利用されます。
授賞式はテーマに焦点を当てるという点で受賞者が主体ではないため、「授賞式」が利用されます。

授賞式と表彰式との違い
「授賞式」は受賞者へ賞を授ける式典を意味します。一方「表彰式」は、賞を受け取る・授けることではなく、特定の人を褒めたたえることを目的としています。受賞者をただ褒めるのではなく、大勢の前で褒めたたえるという点を目的としているため、「賞」そのものに着目している「授賞式」と比較し、優先される項目が異なっていることがわかります。
授賞式を開催する3つのメリット
多くの企業が独自の授賞式を開催しています。なぜ授賞式を開催するのか、メリットを紹介します。
メリット1.主催者の理念を社会に広めることができる
授賞式は、賞の主催者の理念を社会に広める場として有効です。
授賞式を開催する際、まずは賞のテーマを設定します。そしてテーマに沿って、適切な人物や企業に賞を授与します。このとき設定されるテーマは、主催者の理念をもととします。企業が持つ理念は、社内に浸透させることはできても社会へ周知していくのは難しいことです。そのため多くの生活者への認知・共感を促すために、授賞式の場を活用するのです。
授賞式を開催するためには、賞のテーマに沿った受賞者や受賞企業を審査する必要が生じます。そのため、主催者と賞のテーマの関連性が必要です。主催者がテーマに関する知識を有していることはもちろん、企業内でテーマに対する取り組みを推進していることが前提となります。
理念をもとにテーマを設定すれば、主催者としての役割を十分に果たすことができるだけでなく、理念を社会に広げていくことにもつながるのです。
メリット2.受賞者の活動の成果を可視化できる
受賞者の活動の成果を可視化できる点は、授賞式を開催するメリットといえます。
企業は日々さまざまな企業活動に取り組んでいます。それらの活動について、プレスリリースやSNSなどを活用して積極的に情報発信をしても、成果は可視化しにくいのが現状です。
その点、賞を授与することは、主催者の視点から応募者の活動を審査するため、受賞することで成果を可視化することにつながります。成果が可視化されると、社外から見た際に信用に足る情報として認識されるため、企業ブランディングにも役立てることができます。
メリット3.受賞者の活動を支援できる
授賞式はただ賞を贈る・受け取るといった内容では終わりません。受賞者や受賞企業は、受賞の実績を生かし、活動にさらに力を入れることができます。
賞品や賞金が贈られる場合、それらはもちろん活動を支援する要因になりますが、「受賞」という実績が受賞者の活動支援につながります。「受賞」という第三者による評価をうまく活用することができれば、企業ブランディングの強化をはじめ、講演や執筆といったさまざまな形で活動の幅を広げていくことができるでしょう。活動の幅が広がると、企業認知度向上などにつなげることができるため、主催者の受賞者支援につながります。
したがって授賞式は、主催者だけではなく、受賞者にも大きなメリットがある場ということがわかります。
授賞式の主な内容や企画・コンテンツ例
授賞式では、ただ賞を贈るだけではなく、工夫を凝らした企画やコンテンツが実施されることも魅力のひとつです。こちらでは、主な企画やコンテンツをご紹介します。
1.受賞企業や受賞者の活動をまとめたVTR放映
授賞式の場で、受賞企業や受賞者の活動を詳しく紹介するためにおすすめなのが、活動の様子をまとめたVTRの放映です。どのような受賞企業や受賞者であるかはもちろん、どのような人々が活動に関わっているのか、どのように活動してきたのかなど、授賞式に参加している人たちにわかりやすく紹介することができます。
VTR制作の際は、受賞企業や受賞者への事前告知をはじめ、必要に応じて撮影などが必要になります。したがって事前に映像や写真などを確保できている場合を除き、受賞企業や受賞者への事前通知が必要となる点に注意が必要です。
また、受賞内容によって映像構成などを練る必要があるため、主催者の力量が問われるコンテンツとなります。なぜ受賞したのか授賞式の参加者へ伝わりやすいVTRに仕上げることが大切です。
2.受賞者や受賞企業の代表者によるスピーチ
受賞の喜びや感動を、授賞式の参加者に直接感じてもらうために有効なのは、受賞者や受賞企業の代表者によるスピーチです。この方法は事前に受賞を通知する場合はもちろん、サプライズでの発表であっても活用できます。
事前通知を行う場合、受賞者は喜びや受賞の経緯が伝わりやすいように内容を整理し、当日に臨むことができます。サプライズの場合、事前通知時のような内容のスピーチにならない可能性はあるものの、そのときに溢れた感情が授賞式の参加者に伝わりやすく、感動や共感を誘いやすくなります。
また、受賞者自身の言葉で受賞に至った経緯などが語られると、参加者への説得力があり、納得しやすいといえます。受賞に至らなかった他企業にとっても、スピーチの内容そのものが今後の参考となる可能性があるため、ぜひ採用したいコンテンツのひとつです。
3.設定した賞のテーマに関連する講演やパネルトーク
設定した賞のテーマをより深めるコンテンツを検討したい場合、おすすめなのが設定した賞のテーマに関連する講演やパネルトークです。
講演の場合、テーマに関連のある著名人などを呼ぶことで、注目度を高めることができます。講演の注目度を高めることができれば、結果的に授賞式そのものの注目度も高めることができます。
パネルトークなどを企画する場合、パネリストはテーマに関連のある著名人と主催者側の代表などにするのがおすすめです。トーク内容次第では、テーマに対する理解を深めることにつなげることができます。
ただの講演やパネルトークで終わらせるのではなく、広報PRの観点からどのようにプロデュースするのが良いのか、吟味したうえで実施することが重要です。
授賞式を開催する流れ【準備から開催まで】
では、授賞式を開催するためにはどのような流れが必要になるのでしょうか。準備から開催まで、詳しく見ていきましょう。

STEP1.授賞式の日時・開催方法を決定する
まず、授賞式の日時や開催方法を決定します。
日時の決定は、大きく2パターンあります。1つ目は授賞式開催決定時に授賞式の日程まで決定するパターン、2つ目は受賞企業決定時に各企業担当者へ情報連絡のうえ、日程を決めるパターンです。
1つ目のパターンが一般的ではあるものの、受賞者が全国にいる場合や、主催企業の代表者の予定が決められない場合などは2つ目のパターンを採用します。どちらのパターンでも問題ない場合は手間が少ない1つ目のパターンがおすすめです。
授賞式の日程が決まったら、開催方法を決定します。リアルなのかオンラインなのかを決定し、リアルの場合は参加者の人数に適した会場を、オンラインの場合には配信ツールと配信場所の決定を行います。
STEP2.授賞式のコンテンツを設計する
続いて、授賞式のコンテンツを設計します。
まずは授賞式の大枠となるタイムテーブルを決定します。目安となる開始時間・終了時間に対して割り出された時間に、コンテンツを組んでいきます。設定した賞のテーマや授賞基準の説明や主催者の挨拶、設定した賞の紹介、受賞者ごとのコンテンツなど、それぞれ時間を割り振ります。
時間を割り振ったのち、演出にもつながる受賞者の企画やコンテンツを設計します。
初めに設定した時間では足りない場合、ホームページや配布資料で補えることがないか検討しましょう。時間が余る場合は、講演やパネルトークなど、軸となるコンテンツを増やすことを検討してみてもよいかもしれません。
STEP3.授賞式の参加者を検討する
授賞式のコンテンツを設計に続き、授賞式の参加者を検討します。
まず、主催者側です。代表者だけではなく、審査担当者も全員呼ぶのか、もしくは書面でのコメントなどにとどめるのかを検討します。
授賞式の参加者の検討を終えたら続いて、受賞者側の検討を行います。受賞者+何名などの人数の上限を設けるのが一般的ですが、開催方法や開催場所とのバランスを鑑みて、判断するのがおすすめです。
そして最後に、メディア関係者の招待を検討します。メディア関係者は積極的に参加してもらうことで、情報を拡散してもらえる可能性が高くなるため必ず招待します。ただし会場や全体の参加人数とのバランスを見ながら、事前予約制か当日参加制かの検討が必要となります。
STEP4.授賞式の日程を周知する
ここまで決定したら、授賞式の概要や日程を周知しましょう。
参加者や受賞者には直接メールなどで周知を行い、当日の参加方法を詳しく伝達します。すでに関係性があるメディア関係者には直接電話やメールで参加可否を確認するのがおすすめです。
そしてさらに広くメディア関係者への周知を進めるために、プレスリリースの配信を行います。授賞式の日程はもちろん、設定した賞のテーマや開催背景など、できる限り詳しく記載しておくことが大切です。
プレスリリースの配信後は、配信先のメディア関係者の力だけに頼るのではなく、主催者側でもSNSを活用した周知や受賞企業への拡散依頼を行うなど、授賞式の開催を広く知ってもらうための工夫が必要です。
STEP5.授賞式を開催する
そしていよいよ、授賞式を開催します。
当日は参加者の許諾がある場合には写真はもちろん、動画撮影などを積極的に行い、のちのコンテンツの配信へとつなげます。
授賞式の開催後も、プレスリリースなどで受賞者や受賞企業の発表や受賞理由の周知などを行います。受賞企業のブランディングにつながるほか、受賞理由を明確にすることで、次年度以降の応募者獲得につなげることができます。
また、受賞者や受賞企業と合わせて主催者の紹介を行うことで、主催者の情報が多くの人の目に留まる可能性が高くなります。
広報PR担当者は授賞式の開催中・開催後も、さまざまなメディア関係者や生活者へ情報が届く工夫を行うことが大切です。
授賞式の開催時に広報PR担当者が行いたい3つのこと
では、授賞式の開催時には広報PR担当者はどのようなことに取り組む必要があるのでしょうか。行うべき3つのポイントをご紹介します。
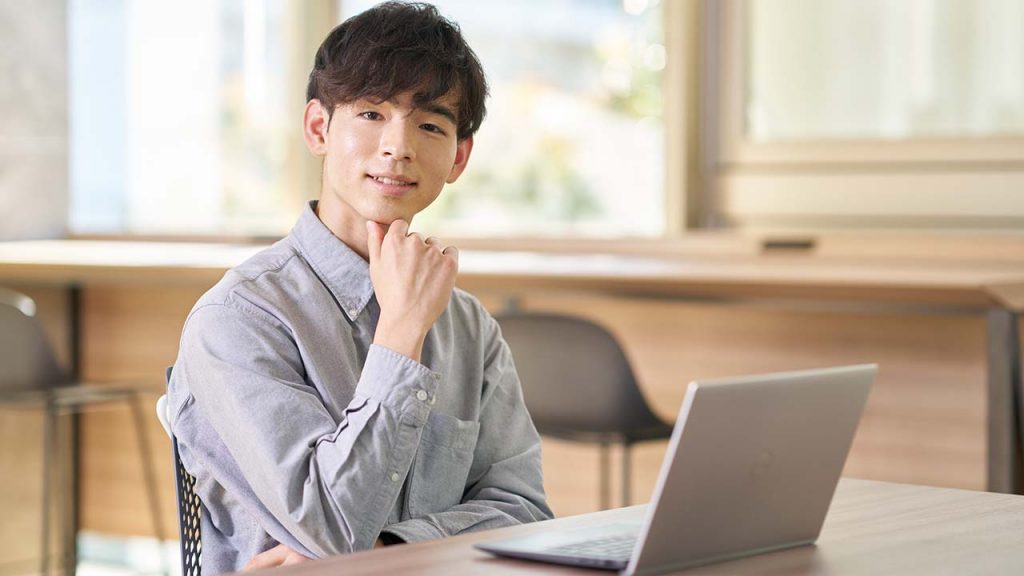
1.プレスリリースを配信する
まず行うべきは、プレスリリースの配信です。可能であれば授賞式開催前、そして開催後という2つのタイミングでプレスリリースの配信を行うと、より効果を高めることができます。
授賞式は、身内同士でたたえ合う式典ではありません。受賞企業や受賞者とともに、社会にテーマに対する理解や共感を持ってもらうことを目的としています。そのためにはまず、授賞式の開催を知ってもらう必要があります。
授賞式の開催を知ってもらうという点で有効なのが、プレスリリースです。メディア関係者の目に留まることはもちろん、検索時に記事化された情報が生活者の目に留まるきっかけにもなります。
必ずプレスリリースの配信を行い、機会損失にならないようにすることが重要です。
2.授賞式の様子をレポートする
授賞式の様子は、積極的にレポートしましょう。写真や映像、テキストなど手段は問いません。当日参加できなかった人に様子を伝えることができるほか、次年度以降の授賞式開催時の参考資料としても役立ちます。
写真や動画、いずれも活用できる場合はSNS投稿がおすすめです。ハッシュタグなどを活用することで、これまで情報が届いていなかった人にアプローチできます。テキストを中心とする場合、オウンドメディアやnoteを活用し、開催レポートなどを作成しましょう。
授賞式の様子が伝わることで、受賞に至らなかった人や企業にやる気を起こさせ、新たな受賞候補者や企業の獲得につなげることができます。
3.授賞式を録画し、配信する
授賞式を録画し、配信することは広報PRの観点で特におすすめです。
録画の場合、必要箇所のみを切り取って配信することができます。テキストや写真と異なり、映像は視聴者にとって情報量が多く、具体的にイメージをふくらませることができるというメリットがあります。
配信形式で映像を展開すると、ほかの視聴者とリアクションを共有することができます。現地参加ではリアクションの共有は式典進行の兼ね合いで難しいため、配信ならではの強みといえます。
受賞者や受賞企業も改めて確認できるため、映像録画・配信は積極的に行うのがおすすめです。
授賞式のプレスリリース事例5選
授賞式のプレスリリースの参考になるように、授賞式開催の告知、授賞式開催後の発表それぞれのシーンに分けてピックアップした5つの事例をご紹介します。
授賞式開催の告知
事例1.プレスリリースアワード
株式会社PR TIMESが実施する「プレスリリースアワード」は、プレスリリースを積極的に活用し、授賞式開催の告知をしています。
授賞式開催前のプレスリリースでは、なぜPR TIMESが「プレスリリースアワード」を開催するのかといった思いや審査員紹介、そしてエントリー方法などが記載されています。
豪華な審査員やForbes JAPANへの広告掲載といったさまざまな情報を通し、「プレスリリースアワード」を盛り上げていることが伝わる事例です。
事例2.コクヨデザインアワード2022
コクヨ株式会社が主催する「コクヨデザインアワード2022」は、授賞式開催以前に2つのプレスリリースを配信しています。ひとつは「コクヨデザインアワード2022」の作品募集、そしてもうひとつは授賞式のライブ配信に関するプレスリリースです。
メディア関係者をはじめとして、多くの人に情報が届くプレスリリースのメリットを生かし、授賞式のライブ配信時に作品への投票を呼びかけています。
合わせて審査員の紹介のほか、各種SNSも紹介されており、メディア関係者だけでなく生活者にとっても有効なプレスリリースとなっています。
授賞式開催後の発表
事例1.プレスリリースアワード
授賞式開催以前のプレスリリースと合わせて、開催後もうまくプレスリリースを活用している例です。改めて「プレスリリースアワード」を開催に至った経緯のほか、受賞企業の受賞理由が詳しく記載されています。
受賞したプレスリリースの原稿が記載されているので、どのようなプレスリリースが有効なものであるかがわかるものになっています。
一次審査を通過したものには講評を添えて返却しているという記載があり、次年度以降にエントリーを検討する企業にとって有効な情報提供を行っている事例といえます。
事例2.読者が選ぶビジネス書グランプリ2022
グロービス経営大学院と株式会社フライヤーが主催する「読者が選ぶビジネス書グランプリ2022」は、受賞者の発表だけではなく、その後の活動についても詳細に記載されている参考になる例です。
受賞作品に合わせて展開される書店でのフェアや、受賞作品の著者・翻訳者・編集者らによる特別セミナーなど、生活者への告知をプレスリリース上で行っています。
授賞式の開催レポートにとどまらず、その後の展開づくりを行いたい場合に有効な事例です。
事例3.Sport in Lifeアワード
スポーツ庁が実施する「Sport in Lifeプロジェクト」の取り組みのひとつ、「Sport in Lifeアワード」に関するプレスリリースは、授賞式の開催レポートの傍ら、スポーツ庁が取り組むさまざまな施策をうまく織り交ぜて説明しています。
5年計画である「第3期スポーツ基本計画」に関する情報や、プロジェクトの最終報告会にあたる「スポーツ参画人口拡大に向けた取り組みモデル創出事業(実証実験/増加方策) 最終報告会」の情報など、多くの人の目に留まる受賞企業報告に、日頃の取り組みをうまく織り交ぜた事例といえます。
授賞式の理念が広く伝わる広報PRを
授賞式は、ただ受賞者や受賞企業に賞を贈るだけの場ではありません。もちろん賞を贈るためのものですが、工夫を重ねることで企業の理念が広く伝わる場となるため、広報PR担当者としては腕の見せどころです。
授賞式は、受賞者や受賞企業を通じて授賞式の存在はもちろん、主催者側・受賞者側双方の日頃の取り組みが周知される機会です。ただし、丁寧に取り組みが伝わる内容に仕上がっていなければ、正しい情報が伝わらない可能性があります。授賞式には、広報PRの観点を生かした設計が必要となるのです。
言い換えれば、広報PR担当者のアレンジによって企業を魅力的に魅せることができる場ともいえます。企業の理念をより広く伝えるために、他社の事例を参考にしながら有意義な授賞式開催を目指しましょう。
授賞式に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事フェムテックとは?市場・企業事例などの基礎知識から広報PRのポイントまで解説

- 次に読みたい記事事業提携とは?基本事項から広報PR・プレスリリースの事例、ポイントまで解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

