事業提携とは、企業同士が協力関係を結んで事業開発や市場開拓を行うことで、提携先企業それぞれの事業成長を実現する手段です。各企業が、互いに提携先のリソースを活用することで、自社単独では達成することが難しい事業の拡大や成長が期待できます。
事業提携は企業にとって大きな事業戦略であるため、対外発信も欠かせません。情報発信においては、複数の企業が関係し、自社単独で完結しないため、注意が必要です。
本記事では、事業提携について理解を深めながら、実際に事業提携を行うためのステップや、広報担当者として心得ておきたい事業提携の広報活動についてご紹介します。
事業提携とは?
事業提携とは、2社以上の企業によって協力関係を構築することをいいます。事業提携を行うそれぞれの企業が共同で技術・人材・サービス・資金などの経営資源を提供し合うことで、自社だけでは生み出せないシナジーをもたらすことを目的とします。
現代社会では生活者のニーズや流行の変化が速く、時代に対する事業の対応力が求められます。事業提携は、提携先のリソースを活用することで研究開発の費用や期間の短縮が期待でき、市場の変化にスピーディーに対応する有効な手段といえます。
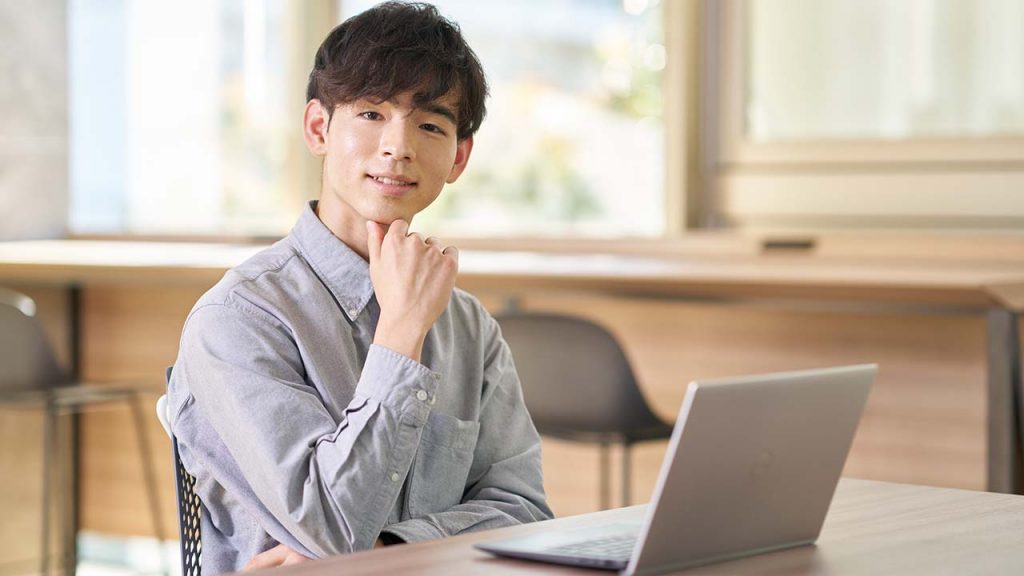
事業提携と業務提携、M&Aとの違い
企業間の協力関係を締結する際には提携の領域や目的、提携先との関係性により、最適な形を選択することが求められます。ここでは企業間の提携関係のうち、よく似た言葉や考え方である業務提携やM&Aとの違いについてご紹介します。
事業提携と業務提携の違い
事業提携は企業同士で関係を結びますが、業務提携は企業の中の特定の事業・サービスで協力関係を結ぶことを言います。事業提携よりも狭い範囲の協力関係を結ぶため、事業提携よりも結びつきは弱いといえます。
事業提携とM&Aの違い
M&Aには株式の取得など資本の移動があります。独立した企業間の提携と違い、2社間は買い手と売り手の関係になります。買い手側は売り手側の経営権を手にすることができ、買収や合併、子会社化することが可能です。
M&Aは、資本と経営権の移動があるため、一度結ぶと解除が困難です。事業提携は協力会社同士の合意が得られればいつでも提携関係の解除が可能です。
同じような関係に「資本提携(資本業務提携)」があります。資本提携には経営権の変化がなく、提携会社同士は独立した企業として提携を結ぶ点がM&Aと異なります。
事業提携を行うメリット
事業提携により、自社が持たない経営資源を手にすることで企業力が上がり、市場競争を優位にする市場競争力の向上が期待できます。
また、ゼロからの事業開発を回避できるので、自社だけで完結するより、専門性や技術、人材教育などの開発にかける資金や時間のコスト削減もメリットのひとつです。開発投資に対する失敗や事故などのリスク回避にもなります。
資本提携やM&Aに比べ、多額の資金の準備が不要で、資本や経営権が動かないため、手続きやリスクも少なく済むことも利点といえます。解消も比較的容易なため、柔軟な判断でスピーディーな経営戦略を実現できます。
事業提携を行うときのリスク
事業が自社だけで完結しないことでリスクが生じる可能性についても留意しなければなりません。複数企業にまたがる管理領域の拡大により、守秘義務違反や情報漏洩などの大きなリスクをはらみます。
自社の経営資源を2社以上で共有することで、技術やノウハウ、情報、時には人材などの経営資源の流出の可能性も高まります。
ひとつの企業だけが利益や売り上げを大幅に伸ばすなど、利益の不均衡は、提携企業同士の関係悪化・対外的なイメージ悪化の懸念もあります。
事業提携の種類
事業提携は提携企業それぞれの性質や関係、活用する経営資源によって提携内容が変わります。目的や事業領域に合わせた最適な提携を選択しましょう。
販売提携
ある企業が販路や販売ノウハウを持つ提携先企業に委託する事業提携の形です。代表的なものに、フランチャイズ契約や販売店契約、代理店契約などがあります。
販売を委託する側のメリットとして、販路や販売チャネルを持っていなくてもスピーディーに自社ブランドや自社製品を市場に出せることが挙げられます。販売能力を開拓する費用や時間を節約した分、商品開発に注力できます。
販売を受託する側のメリットとしては、取り扱う商材が増えることで、新規顧客開拓や顧客単価の向上を見込めることが挙げられます。
技術提携
ある企業が自社の技術を提携先企業に提供し、提携先はその技術で製品やサービス開発を行う事業提携の形です。技術を提供する側のメリットとして、製品やサービス開発のコストが削減でき、技術の研究開発のみに注力することで、自社の技術力向上につなげられることが挙げられます。
技術提供を受け、製品やサービスを開発する側のメリットとしては、新技術の研究開発のコストを削減しながら、自社だけではできない製品やサービスを開発できることが挙げられます。提携企業それぞれに、互いの専門分野の技術やノウハウを共有・蓄積できることもメリットといえます。
共同開発提携
提携企業同士が自社の技術やノウハウ、人材などのリソースを持ち寄り、新たな事業や製品、技術を開発する事業提携の形です。それぞれの企業にとって、自社だけでは実現できない新規開発を可能にし、新たな市場開拓のチャンスを生み出せます。
自社単独の研究開発に比べて費用や時間の削減ができるので、社会の変化に対する技術開発の対応力が上がり、企業の競争力向上につながります。
生産提携
ある企業が自社製品の生産や製造工程の一部を提携先企業に委託する事業提携の形です。生産を委託する側のメリットとして、自社だけでは生産が売り上げに追いつかなくても販売機会を逃さずに安定生産できること、製造設備拡大の費用や時間を節約した分、商品開発に注力できること、製造設備を持っていなくても自社ブランドや自社製品を市場に出せることが挙げられます。
生産を受託する側のメリットとしては、自社設備の稼働率を上げて有効活用できること、生産規模の安定化や大ロット生産により製品単価を下げることができ、製品の競争力を上げられること、自社で製品開発をしなくても生産ノウハウや実績を蓄積することができることが挙げられます。
気をつけるポイントとしては、品質管理や不良品が生じた場合の責任、納品の過不足や遅延に対する補塡など、明確に取り決めておく必要があります。
事業提携を行う流れ
事業提携は基本的に下記のステップで進めます。効果的な事業提携につなげるために、経営陣が各ステップを慎重に進めて社内の合意を得る必要があります。
STEP1.自社分析と事業戦略の整理
事業提携の目的を明確にするため、自社分析を行います。
自社の今後の成長・発展にける課題は何か、その課題を解決するために必要な提携形態は何か、提携におけるメリットや自社への影響は何かを明確にし、事業提携を自社のビジネスプランに組み込めるように計画します。
STEP2.提携先の検討
STEP1を踏まえ、事業提携先の企業をリサーチ・選定します。
提携先のリサーチには専門機関など第三者を介して探す、提携募集プラットフォームやマッチングサービスを使う、インターネットや専門メディア・ビジネスメディア、交流会やセミナーなどへの参加などがあります。
STEP3.提携先企業へ提携の依頼・交渉
STEP2で提携先企業に目星をつけて連絡し、交渉に進みます。
提携先には、提携におけるゴール、提携における両社のメリット、提携におけるリスク、自社が提供できる経営資源について話し合い、条件を調整します。
STEP4.業務提携契約書を作成
STEP3を踏まえ、互いの合意が得れた場合、提携に向けて双方が合意した内容で契約書類を作成します。その場合、基本合意契約と機密保持契約を結んでおく必要があります。契約書では、下記を明確にしておくと後々のリスク回避にもつながります。
- 提携業務の範囲や内容、役割分担・責任分担を明確にする
- 成果物や権利がある場合、その帰属や所在を明確にする
- 利益配分や費用負担を明確にする
- 守秘義務・機密事項の扱いの取り決め、機密保持契約を行う
- 契約期間や提携の更新の条件
書類については食い違いや不備が生まれないように、第三者の専門機関に依頼する場合もあります。
事業提携を進めるときの3つの注意点
事前に注意事項を具体的に取り決めておくことで、事業推進後のリスク回避・円滑な進行が可能になります。
例えば、事業提携のリスクのひとつに、提携により機密情報を開示する必要があります。情報漏洩は経営継続に大きなインパクトを与えるリスクにつながるので、機密情報の取り扱いに関しては、明文化しておくことが大切です。
注意点1.双方の目的・ゴールを確認する
事業提携の最たる目的である、提携のゴールや双方の目的を理解します。
提携内容の齟齬は後々の手続きのコスト増大やリスクにつながります。提携先同士の経営陣・代表レベルで最終的なビジョンが共有されていることが大切です。
注意点2.役割と責任を明確にする
提携開始後、効率的な進行と問題が発生した場合の迅速な対応のため、提携業務における各社の業務範囲やリスクが生じた場合の責任の所在や対応について具体的にします。
注意点3.利益や費用の分配を明確にする
提携による費用負担や利益が発生した場合、各社の分配を取り決めておくことで、事業が開始してから問題が発生しないようにします。
事業提携に関する広報PRを行うときの3つのポイント
事業提携の広報活動は、自社単独の広報活動に比べて確認事項の範囲や回数が増加します。広報担当者は各社の機密事項を抱えることにもなるので、自社単独の広報活動より丁寧な進行が必要です。各連携先の広報担当と緊密に連携を図りましょう。

ポイント1.提携先企業広報と連携する
各企業の広報担当とワンチームで広報活動を行い、提携先企業間で発表内容や解禁日時の食い違いが出ないように調整・進行します。
リリースの体裁や情報発信チャネル、情報解禁のタイミングの共有はもちろん、それぞれの広報担当のリレーションを把握し、各社でメディアアプローチを分担することで効果的な情報発信を行います。
問題が起きた際のリスクコミュニケーションについても、各社の責任範囲や対応について決めておきましょう。
ポイント2.事業提携における広報計画を立てる
事業提携の情報発信が事業提携発表以外にもある場合、おおよその事業計画とともに、いつ何を発表するのかを把握する必要があります。事業計画に合わせて適切なタイミングで適切な広報対応・情報発信ができる計画を立てましょう。
ポイント3.目標や市場への影響を、数字やデータで話せるようにする
事業提携の広報活動はメディアだけでなく、関わるステークホルダーが増えることも意識します。事業提携は提携各社の業績に直結するので、特に株主の注目が大きくIRへの影響も見逃せません。メディア向け・IR向けのそれぞれの資料に対して、提携の効果を具体的な数字で可視化すると対外的な説得力が高まります。
事業提携に関する広報・PR手段
事業提携は経営戦略上の大きな取り組みであるため、広報計画に組み込み、対外発信を行う必要があります。事業成長に直結するため、特に株主や業界からの注目が高い経営戦略といえます。
本項では、事業提携の代表的な対外発信手段である記者発表会とプレスリリースについて、具体的な内容をご紹介します。事業提携における情報発信のポイントを押さえて、効果的な情報発信につなげましょう。
記者発表会
事業提携の広報活動として記者発表会は有効な手段です。案内状を作成し、メディアへの配信や記者クラブに投げ込みを行って参加メディアを募ることで、事業提携内容を効果的に直接メディアに伝えることが可能です。
発表会のプログラムは、各提携企業の代表の挨拶と提携についてコメント、事業担当者から事業成長目標や効果などをスライド資料で伝え、メディアからの質疑に対応する流れが一般的です。新たな製品のイメージ画像やプロトタイプを用意するなど、メディアが取材したくなるような素材を用意することで、より印象に残りやすい発表会にできます。
プレスリリース
発表会をする規模ではない内容でも、提携企業連名のプレスリリースの配信は必須です。
提携内容について、成長目標や市場におけるシェアの変化など、具体的な数字やデータ、グラフを記載して、提携の効果をわかりやすく伝えられるように工夫しましょう。発表会と同じように、各社代表のコメントを掲載することで大きな経営戦略であることもアピールできます。
広報担当は各社から出すプレスリリースによって、内容や情報解禁日時の食い違いがないように注意しましょう。スムーズなプレスリリース作成のために、あらかじめ表記ルールや承認ルート、確認に要する時間などを各社の広報担当で把握しておくことが大切です。配信後も、メディアアプローチの分担や取材対応者、想定質問と回答を決めておくことで、効果的なメディア対応を行いましょう。
事業提携に関する広報PR・プレスリリース事例3選
事業提携について、大手企業からベンチャー企業の取り組みまで3つの事例をご紹介します。
事例1.株式会社ファミリーマートと株式会社TOUCH TO GO
コンビニ大手のファミリーマートと無人決済店舗の開発を行うTOUCH TO GOが無人決済コンビニ店舗の開発に向けた事業提携です。
コンビニという年中無休店舗にとって無人決済が導入されることで、オペレーションや雇用コストの削減につながります。ファミリーマートにとって、コロナ禍における社会情勢のニーズに応え、競合との差別化を図る事業展開といえます。
TOUCH TO GOは全国展開する大手企業の導入により、同社の開発した技術がより広く生活に根付く展開を期待できます。
参考:ファミリーマートとTOUCH TO GOが業務提携 無人決済システムを活用した店舗の実用化に向け協業|TTGのプレスリリース
事例2.株式会社メルカリと日本財団
フリマアプリ「メルカリ」で多くのユーザーを持つメルカリと長年公益事業をサポートし、日本最大の社会貢献財団である日本財団による、寄付の新たなシステム構築と推進を目的とした事業提携です。
メルカリはフリマアプリとして日本最大のユーザー数を持ち、フリマアプリのシステムを活用した新たな寄付システムを開発。日本財団は長年培ってきた寄付活動における知見や社会貢献のノウハウを提供。互いのサービスやノウハウを提供することで効果的な寄付システムを構築しながら、両社共同でCSR活動に取り組みます。
提携には企業イメージも重要です。メルカリが単独でCSR活動を行うより、日本財団の組織イメージにより説得力のあるアクションとして認知されることが期待できます。
参考:メルカリと日本財団、寄付促進に向けた オンライン・オフライン両面での業務提携に合意
事例3.株式会社Birdmanとリアライズ・モバイル・コミュニケーションズ株式会社
デジタルクリエイティブを得意とするBirdmanと、国内有数の360°撮影の施設や技術を持つリアライズ・モバイル・コミュニケーションズによる、新たな体験型デジタルコンテンツの開発を目指した技術提携です。
昨今話題の「メタバース」市場に参入するため、それぞれのデジタル技術を提供し合うことで、エンターテインメントやマーケティング活動におけるバーチャル体験サービスを実現しています。
参考:Birdmanとリアライズ・モバイルが、xRやデジタル・クリエイティブなどを活用したデジタルコンテンツの創出で業務提携
最適な事業提携で、事業成長に効果的な一手を
事業提携は提携企業同士が独立した立場で、互いの経営資源を活用することで、事業成長に直結させる手段です。理解を深め、適切な事業提携を行うことで事業の成長に高い効果が期待できます。一方で、自社以外が事業に関係することによるリスクへの配慮も欠かせません。
広報活動においても、事業提携は自社の注目を高める効果的な情報です。事業担当者や提携先の広報担当と一丸となって、情報発信前後の動きを確認しながら、効果的な広報活動を行いましょう。
事業提携に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする



