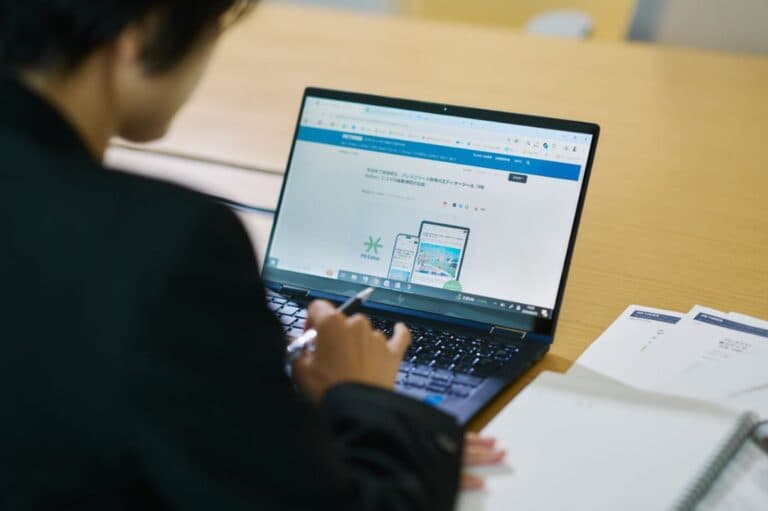インナーブランディングとは、従業員に自社の理念やビジョンを浸透させることで、強い組織へと変革するための広報PR活動です。ビジネス環境が目まぐるしく変化する昨今、持続的に企業を経営するための戦略として、インナーブランディングを取り入れる企業が増えています。
本記事ではインナーブランディングの意味や目的などの基本的な考え方から、その効果、メリットなどについてわかりやすく解説していきます。これから社内ブランディングを始めたい方や、取り組みを見直したい方にとって、実践のヒントとなる内容をお伝えするので、本記事を参考に、ぜひインナーブランディングを実践してみてください。
インナーブランディングとは?
「ブランディング」というと、生活者や取引先、求職者、株主などの社外のステークホルダーへ向けて商品や企業の価値をPRする取り組みをイメージする方が多いかもしれません。実はブランディングには社外向けの「アウターブランディング」と、社内向けの「インナーブランディング」があります。
インナーブランディングとは、従業員に対して、自社の理念やビジョン、大切にしている価値観などを浸透させることを通して、組織を強化する広報PR活動です。
インナーブランディングにはさまざまな施策があり、社内報や社内SNSなどのメディアや、イベント、ワークショップといった対面での場を通じてコミュニケーションを図るのが一般的です。さらに人事制度や評価制度といった具体的な報酬に反映するケースも。主に組織の課題を解決したいときや、記念日などの節目に導入され、社内の広報PR担当や人事担当が運用することが多いようです。

インナーブランディングと混同されやすい言葉との違い
ブランディングにはさまざまな用語があり、いずれも企業の価値やイメージを向上させる取り組みを指します。ビジネス業界で自然と使用されるようになった用語であるため、明確な定義はなく、似ている用語もいくつかあります。ここではブランディングに関する混同されやすい言葉について、それぞれの意味をご紹介します。
インターナルブランディングとの違い
インナーブランディングに似ている言葉として、「インターナルブランディング」という言葉があります。まずインナー(inner)を直訳すると「内側の、内部の、精神的な」という意味。そしてインターナル(internal)も「内部の、内面的な、本質的な」という意味なので、基本的には同じ用途で使われていると考えて問題ありません。
ただ、国内では「インナーブランディング」のほうが使われることが多く、英語圏では「インターナルブランディング」が用いられるのが一般的のようです。
エクスターナルブランディング・アウターブランディングとの違い
インナーブランディングの逆の意味で使われる言葉として、「エクスターナルブランディング」と「アウターブランディング」があります。エクスターナル(external)は直訳すると「外部の、外側の」という意味で、アウター(outer)は「外の、外側の」という意味。両者とも同じ用途で使われていますが、国内ではアウターブランディングのほうが一般的です。
いずれも生活者や取引先、求職者、株主など、社外のステークホルダーへ向けて行う広報PR活動を指します。企業が持ってもらいたいイメージを戦略的に醸成し、売り上げにつなげることが目的。広告やプレスリリースなどを通じて情報発信することがメインになります。
インナーブランディングの目的・効果
インナーブランディングの目的は、主に組織力を高めることにあります。例えばインナーブランディングのさまざまな活動を通して、従業員の自社への愛着や貢献意欲といったエンゲージメントが高まれば、人材が定着し離職率の低下につながります。これにより経験豊富な従業員が育ち、新人教育を充実するため優秀な人材の育成が可能になります。
また、インナーブランディングによって目指す姿が社内で共有されることで、業務における判断軸が明確になるため、従業員一人ひとりがブレずに一貫した判断ができるようになるという効果も。ひいては組織力の強化が期待できるというわけです。

インナーブランディングが注目される理由・背景
あらゆる商品が市場にあふれ、企業の競争が激化する現代。企業にとってはいかに強いブランドを構築して他社と差異化するかが、大きなテーマとなりました。また、終身雇用や年功序列といった従来の慣習が変化し、人材が流動化したことによって、優秀な従業員の確保も困難に。このような背景から、生活者や求職者に選ばれる企業になるためには、ブランドの影響力がますます重要な時代になっています。
また、企業のブランディングに関する研究が進むにつれ、企業が与える生活者へのイメージは、広告的なブランディングだけではないことが明らかになってきました。例えば実店舗やカスタマーセンター、CSR活動など、生活者はさまざまな機会に企業の印象を判断しているのです。このため選ばれる企業になるには、生活者とのあらゆるタッチポイントにおいて統一的なメッセージを伝えることが重要になっています。その結果、すべての従業員が企業の目指す方向性を理解し、それに基づいて行動できるように、インナーブランディングの重視性が注目されるようになったというわけです。
近年ではさらに、SDGsへの積極的な姿勢が企業の価値に影響を与えるようになっています。SDGsに取り組むには従業員とのコミュニケーションは不可欠。今後はますますインナーブランディングの重要性が高まっていくと言えるでしょう。
インナーブランディングを実践する3つのメリット
インナーブランディングを実践することによって、企業にはさまざまなメリットが期待できます。ここでは代表的な3つのメリットをご紹介します。
メリット1.優秀な従業員の確保
インナーブランディングがうまくいくと、従業員の組織へ愛着が強まることが期待できます。従業員が雇用条件や賃金によってだけではなく、心理的な結びつきによってその組織で働くことを選ぶようになると、人材の定着につながり、安定した組織に。経験豊富な従業員が増えることで、社内教育が効果的に機能し、優秀な人材が育成されます。
また、インナーブランディングによって従業員自身が企業のビジョンを体現する存在になると、採用面でのメリットも。従業員の姿に共感して入社する人が増えることで、企業文化にフィットしやすい人材の確保につながります。
メリット2.アウターブランディングの土台ができる
インナーブランディングによって従業員が同じ方向を目指すようになると、社外へ向けたアウターブランディングの土台ができます。例えば広告などで「顧客第一」のメッセージを発信している企業が、実際の店舗では不親切な対応をしていると、ブランドの信頼性が損なわれてしまいます。
商品・サービスなどのタッチポイントと、広告で発信されるメッセージが一致することで、初めてブランドへの信頼感が生まれるのです。このため、アウターブランディングを強化したいなら、同じくらいインナーブランディングにも注力する必要があると言われています。
メリット3.競争優位性・企業価値の向上
インナーブランディングの成功で組織力が強化され、同時にアウターブランディングも効果的に機能するようになると、企業の競争優位性が高まります。なぜなら飽和状態の市場においては価格ではなくブランドによって企業の商品・サービスが差異化され、生活者に選ばれる存在になるためです。
また、インナーブランディングによって優秀な従業員が増えると、組織のリスクマネジメントにも良い影響が。従業員のエンゲージメントが強化されると、コンプライアンス意識も高まることが期待できます。厳しいリスクマネジメントが求められる昨今、コンプライアンスは企業価値の向上につながります。
インナーブランディングを実践する際の7つのポイント
さまざまなメリットや効果が期待できるインナーブランディングですが、実際に着手する際にはいくつか押さえるべきポイントがあります。ここでは、重要な7つのポイントにしぼって解説していきます。

ポイント1.課題・目標を明確化・数値化する
インナーブランディングを実践するうえで、もっとも大切なのが課題を明確にすること。まずは何を解決したいのか掘り下げ、どのような状態になったら課題をクリアしたと言えるのかを言語化する必要があります。そのためには、なぜその課題が生まれたのか、原因を分析することが求められます。
この段階に時間をかけずにいきなり施策内容の検討に入ってしまうと、なんのためのインナーブランディングなのかを見失い、失敗の原因に。しっかりと課題とその原因を特定し、そのうえで目標を立てることが成功の秘訣です。さらに目標は数値化し、施策の効果を計測できるようにしておくと、継続しやすくなるでしょう。
ポイント2.長期的な計画を立てPDCAをまわす
ポイント1を踏まえて目標を立てたら、実行のためのスケジュールを立てましょう。いつまでに、どのような目標を達成し、そのためにはどのような施策を行うのかを細かく立案していきます。このときに重要なのが、長期的な計画にすること。
インナーブランディングはすぐに効果が出るような性質のものではないため、長期目線で取り組みます。ただ、漠然と進めて挫折しないためにも短いスパンでのゴールを設定し、PDCAをまわして成果をチェックすることは必要です。長期的な計画だとメンバーが入れ替わる可能性もあるため、進捗状況がわかるようにPDCAの記録を取っておきましょう。
ポイント3. 経営層に理解してもらう
インナーブランディングの壁になりやすいことのひとつとして、経営層からの理解が得られないことが挙げられます。繰り返しますがインナーブランディングは時間がかかるうえ、はっきりと目に見えるような成果を得にくいのが特徴。課題と目標を明確化し、計画の意図をしっかりすり合わせる必要があります。見通しが不透明だと、最悪の場合経営層からストップがかかることもあります。
また、インナーブランディングの施策には予算確保や人員確保が必要なので、経営層の協力が非常に重要になります。トップから従業員へメッセージを発信してもらうことも多いため、日頃から経営層との関係づくりに努め、意識のすり合わせは丁寧に行いましょう。
ポイント4.従業員に受け入れられる形で行う
インナーブランディングの具体的な施策を検討するうえで、大切なのが従業員への伝え方です。インナーブランディングの大きな効果として、組織への愛着や貢献意欲の高まりがありますが、そのためにはトップから発信される理念やビジョンに共感してもらうことが不可欠です。
インナーブランディングのよくある失敗として、強制的な印象を与えたり、非現実的なメッセージを発信したりして、従業員が拒否感を覚えてしまうということがあります。こうなると共感されないだけでなく、大量離職につながることもあるため、従業員に受け入れてもらえる形で進めることが何より重要です。トップや担当者が一方的に推進するのではなく、現場のキーパーソンをうまく巻き込むとよいでしょう。プロジェクト形式にするなら、人選が成否を分けると言えます。
ポイント5.すぐに効果が出なくてもあきらめない
いざインナーブランディングを開始しても、実際はうまく継続できずに自然消滅してしまうことも少なくないようです。営業活動のように売り上げに直結するような施策ではないため、「本当に意味があるのか?」という声も上がってくるでしょう。そこであきらめずに継続するためには、ポイント2で挙げたように短期スパンでの成果をチェックし、積み重ねていくことが重要です。
それから、賛同してくれるメンバーを増やすことも継続するうえで大切です。社内の関心が途切れないよう、それぞれの施策について定期的に従業員にアンケートを取り結果を共有するなど、進捗状況を発信するのも効果的。いつか小さな変化が起こっていることに気づき、インナーブランディングの効果を実感できるときがくるはずです。
ポイント6.フィードバックの仕組みを作る
インナーブランディングを成功させるには、従業員からのリアルな声を収集し、それを次の施策に反映させる「双方向のコミュニケーション」が欠かせません。一方的な施策の実施ではなく、アンケートや定期的なヒアリング、ワークショップなどを通じてフィードバックを得られる仕組みを整えることが大切です。
得られた意見は集計・分析し、次の打ち手に活かすとともに、「従業員の声が施策に反映されている」と実感してもらえるよう、反映内容や改善点を社内で共有するようにしましょう。こうした積み重ねが、インナーブランディングへの信頼感や主体的な参加を促すことにつながります。
ポイント7.施策を押し付けない
どんなに優れたインナーブランディングの施策でも、それが一方的に押し付けられていると感じられてしまえば、従業員の反発や無関心を招く原因になります。施策の目的や背景を丁寧に説明し、納得感をもって参加してもらう姿勢が重要です。
特に価値観や理念の共有といったテーマは、従業員一人ひとりの感情や考え方に深く関わるため、「自分ごと化」してもらうことが必要です。現場の声を尊重しながら、無理のないペースと方法で進めることが、効果的なインナーブランディングにつながります。
インナーブランディングの施策・手法の例
インナーブランディングの施策や手法はさまざまありますが、代表的なものとして社内報が挙げられます。昔ながらの冊子形式から、イントラネットや社内SNS等のデジタルツールまで、その企業に合った形で取り入れられています。掲載する内容は、トップのメッセージや経営計画の共有といったオフィシャルなものをはじめ、事業所や従業員の紹介、ランチ情報といった小ネタなど、多岐にわたります。
紙面を通して会社全体の動きやトップの思いを理解でき、さらに普段直接やりとりすることが少ないメンバーを知るきっかけになるなど、社内報はインナーブランディングのツールとして非常に有効と言えます。企業によっては社内報を取引先に配布し、自社を紹介するツールとして活用するという事例も。また、どんな会社で働いているのかを家族に知ってもらうために、家に持ち帰ることを推奨するなど、さまざまな活用法があるのが社内報のよさです。
社内報に関する記事はこちらの記事も参考にしてみてください。
インナーブランディングの成功事例
実際に企業ではどのようにインナーブランディングに取り組んでいるのでしょうか。ここではインナーブランディングの成功例として、タカラベルモント株式会社をご紹介します。
タカラベルモント株式会社は、理容室・美容室、エステ・ネイルサロンおよび歯科・医療クリニックの業務用設備機器や化粧品・空間デザイン等を手掛ける企業。BtoBのビジネスでありながら、創業100年の節目に広報PRを強化しました。新たなパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定し、社内外に浸透させるための情報発信を行っています。
特に意識しているのは、「インナーブランディング:アウターブランディング=7:3」の比率で行っている点。従業員のエンゲージメント向上を目指し、社内コミュニケーションに重点を置いています。また、デジタルツールが普及するなか、デジタルが苦手な従業員でも見やすいよう紙媒体にこだわっているそう。プレスリリースを通して新しく制定したパーパスを社外へも発信し、インナーブランディングとアウターブランディングを両方強化している好事例です。
効果的なインナーブランディングを実践しよう
ここまで、インナーブランディングの目的やその効果、事例などを紹介してきました。周年記念などの節目や、合併・統合などのタイミングで始めることが多いインナーブランディングですが、実際に取り組むにはステップが必要です。まずは自社の課題を明確にし、インナーブランディングによって何を成し遂げたいのかを共有することから始めるとよいでしょう。
また、インナーブランディングにはさまざまな施策や手法があるため、自社に合った方法を選ぶことが大切です。従業員のエンゲージメントを高め、より強い組織になるために、ぜひインナーブランディングを実践してみてください。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする