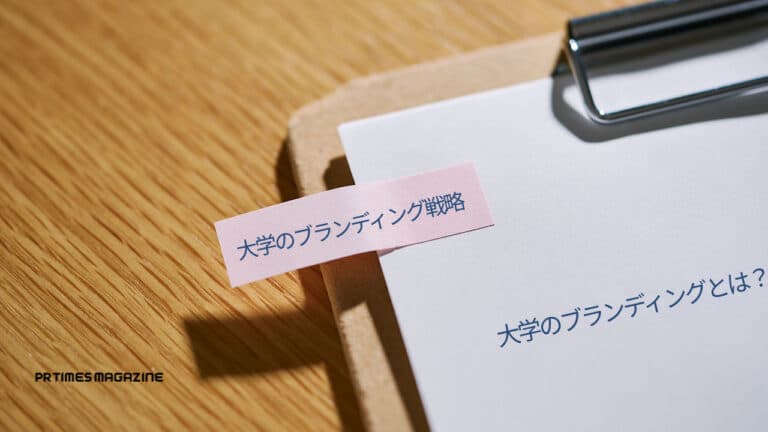医療・福祉・介護業界は、人々の生活や命に直結する分野です。そのため、安心感や信頼性をどう伝えるかが広報PRの大きな課題となります。一方で、良い取り組みをしていても十分に発信できていないケースも少なくありません。
本記事では、業界特有のPRにおける3つのポイントと、利用者・従業員・地域社会に向けた具体的な施策、さらに注目を集めた事例を紹介します。自社の取り組みをどのように情報化し、社会へ発信していくべきか。取り組みの参考となるヒントが見つかるはずです。
医療・福祉・介護業界にPRが必要な理由
医療・福祉・介護は生活や命に直結する分野だからこそ、安心と信頼の構築が最優先課題といえます。そのうえで、取り組みや価値を広く伝えることは利用者や家族の理解を深め、社会全体からの評価を高める大切な活動となります。同時に、発信の仕方ひとつで受け手を不安にさせたり、当事者や家族を傷つけてしまったりする恐れがある点にも注意が必要です。意図せずともそう感じさせてしまう表現は避け、「誰一人として傷つけない」ことを大前提にした情報発信を心がけることが求められます。
この業界は、人の命や生活に直結するサービスを提供しています。だからこそ、信頼や安心を築くことが欠かせません。しかし、いくら良い取り組みを行っていても、利用者や家族、地域社会に伝わらなければ価値が十分に届かないままです。
また、慢性的な人材不足という課題も見逃せません。職場環境や働きがいを発信することは、採用や定着を後押しします。さらに、社会課題に向き合う姿勢を示すことで、組織の社会的評価を高めることにもつながっていくでしょう。安心感や信頼性を伝えるためのPRだからこそ、発信内容がどう受け止められるかを常に考え抜くことが重要です。
医療・福祉・介護業界がPRにつなげる3つのポイント
医療・福祉・介護業界におけるPRは、単にサービスを紹介するだけでは不十分です。「生活者にどう寄り添うか」「自社の強みをどう示すか」「社会課題にどう向き合うか」の3つを整理し、バランスよく発信することが効果を高めるカギとなります。

ポイント1.信頼を築き生活者に寄り添う
生活者にとって最も重視されるのは「安心できるかどうか」です。治療実績やスタッフの資格、衛生管理の徹底といった具体的な情報を示すことで、信頼を得やすくなります。
難しい専門用語を並べるよりも、誰にでも理解できる言葉で説明することが大切です。実績の提示は効果的ですが、最終的に生活者が知りたいのは「自分にとってどんなメリットがあるのか」。そこを明確にすると共感につながるでしょう。
ポイント2.独自の価値と人を発信する
競合との差別化には、自社の強みを事実ベースで示すことが不可欠です。治療件数や資格保有者数などの数字は、客観的な裏付けとなり信頼を支えます。
さらに、独自のリハビリプログラムや先進設備、24時間対応体制といった「ここならではの特徴」をわかりやすく発信すると効果的です。理念やビジョンを伝えることも欠かせません。「誰のために」「何を目指しているのか」を明確にすることで、利用者や家族の共感を呼びやすくなります。
加えて、この業界では「人」がサービスの品質を決めます。スタッフの想いや働き方を紹介すれば、利用者への安心感を高めると同時に、採用広報や社内エンゲージメント強化にもつながるはずです。
ポイント3.地域と社会に貢献する
高齢化や医療アクセス格差といった社会課題は、この業界と密接に関わっています。その課題にどう向き合っているかを示すことで、社会からの信頼を獲得できます。例えば、健康啓発セミナーや地域イベント、防災訓練への参加は「公共性の高い存在」としての印象を強めます。
さらに、費用体系や外部評価の公開は、透明性と説明責任を示す手段になります。介護人材の育成、デジタル化、環境配慮型施設の整備といった取り組みは、未来志向の姿勢として評価されやすいでしょう。
医療・福祉・介護業界のPR3施策
PRを行う対象は大きく「利用者」「従業員」「地域社会」の3つに分けられます。それぞれの立場に合わせたメッセージを届けることで、安心感や働きがい、社会からの信頼を育み、持続的に選ばれる組織づくりにつながります。
患者・利用者に向けたPR施策
患者や利用者に向けたPRでは、安心や安全をきちんと伝えることが欠かせません。医療体制や衛生管理の取り組み、スタッフの専門性をわかりやすく示すことで信頼の構築につながります。さらに、利用者や家族の体験談を紹介すれば、実際の声を通じて共感を呼びやすくなります。
無料体験会や健康相談会を開催することも有効で、直接触れ合う機会が信頼構築につながります。また、生活者調査やアンケート結果を公開し、顧客視点で改善を重ねている姿勢を発信すれば、より一層安心感を与えられるでしょう。
採用に向けた職場環境や働きがいを訴求するPR施策
PRは外部に向けた発信だけではなく、働く従業員やこれから仲間になる採用候補者に向けても大きな役割を果たします。従業員に対しては、働き方改革やキャリア支援の取り組みを伝えることで、安心して働ける環境づくりを示すことができます。スタッフの声を発信することは、社内のエンゲージメント向上にもつながります。
一方、採用候補者に対しては、資格取得支援や研修制度といった成長できる環境を強調することが効果的です。加えて、経営理念やビジョンを示すことで「ここで働く意義」が伝わりやすくなり、人材確保や定着の後押しとなるでしょう。
地域社会に向けたPR施策
地域社会に向けたPRは、施設や事業所が“地域の一員”として信頼を築くために不可欠な要素です。地域包括ケアの推進や学校・自治体との連携を発信することで、地域住民からの理解と協力を得やすくなります。また、健康セミナーや防災訓練、地域イベントへの参加は、利用者以外の人々との接点を広げる効果があります。
さらに、高齢化社会や医療アクセス格差といった社会課題に取り組む姿勢を示すことは、共感を呼びやすいポイントです。加えて、環境配慮型施設の整備やデジタル化の推進など、持続可能性を意識した取り組みを発信すれば、未来志向の組織であることを印象づけられるでしょう。これらを積極的に発信することで、スポンサーやボランティアなどの支援者を巻き込みながら、社会課題解決プロジェクトとして活動の幅を広げていくことが可能になります。
医療・福祉・介護業界が企画化するときの注意点
企画や情報発信を進める際には、専門性や信頼性を損なわない工夫が欠かせません。とくに「専門用語の使い方」「センシティブ情報の扱い」「誇張表現の回避」は注意が必要で、これらを徹底することで発信への安心感を高められます。

1.専門用語を使いすぎず、一般生活者にも伝わる表現にする
医療や介護の現場では専門的な言葉が多く使われますが、そのまま伝えても生活者には理解されにくいことがあります。情報発信ではできるだけかみ砕き、身近な例えや比喩を用いて日常の体験に置き換えることが大切です。専門用語をどうしても使う場合は注釈や補足を添え、理解の助けとなる工夫を行いましょう。「自分の家族や友人に説明するとしたらどう表現するか」という視点を持って見直すことで、伝わりやすさが格段に高まります。
2.センシティブ情報(患者情報など)の扱いに注意する
患者や利用者に関する情報は非常にデリケートであり、慎重に扱う必要があります。発信に際しては本人や家族の同意を必ず得て、書面で記録に残しておくことが望ましいです。名前や顔写真、住所など個人が特定できる情報は原則として公開せず、匿名化や統計化を行うことで安全性を確保します。情報公開の範囲は「必要最小限」にとどめ、利用者や家族の安心を守りながら発信する姿勢が、結果的に社会からの信頼にもつながります。
3.誇張表現や不安をあおる表現は避ける
PRにおいて効果的に見せたい気持ちから、つい強い表現を使いたくなることがあります。しかし「必ず治る」「絶対安心」といった断定的な言葉は誤解を招きやすく、かえって信頼を損なう恐れがあります。他社や他サービスとの過度な比較も同様に避けるべきです。
さらに、利用者や家族の中には情報に敏感に気づける人ばかりではない点にも配慮が必要です。誇張や不安をあおる表現は、気づかれずに誤解や不安を広げるリスクがあります。事実に基づき、根拠やデータを明示した発信を心がけることで、安心感と納得感を届けることができ、結果的に長期的な信頼の構築につながります。
医療・福祉・介護業界のプレスリリースのネタ・事例3選
ここでは「調査データの活用」「地域・社会を巻き込む取り組み」「社会課題の可視化」という異なる切り口の3事例を紹介します。いずれも実績や姿勢を効果的に伝え、注目を集めた好例です。
1.株式会社ミライプロジェクト|調査データの活用
株式会社ミライプロジェクトは、介護現場に美容の力を取り入れる「介護美容」サービスの認知度調査を発表しました。調査データはメディアに取り上げられやすく、サービスの新規性や社会的意義を裏付ける材料になります。利用者の心や生活の質(QOL)向上というテーマも共感を呼びやすく、「調査結果を通じてサービスの可能性を示す」プレスリリースの好例です。
参考:2025年問題の解決策として注目の「介護美容」 認知度はまだ12%でも、働き手は過去最大3.5倍増!
2.株式会社ビジョナリー|地域・社会を巻き込む取り組み
株式会社ビジョナリーは、大規模福祉イベント「VISIONARY DAYS 2025」を開催すると発表しました。イベントやキャンペーンはプレスリリースの題材としてニュース性が高く、参加者の声や地域のつながりを可視化できる点が強みです。特にこの事例は、「地域を巻き込んだ取り組みをそのままニュース化できる」点が参考になります。
参考:大規模福祉イベント“VISIONARY DAYS 2025”138タワーパーク イベント広場にて2025年11月1日(土)に開催決定
3.Ubie株式会社|社会課題の可視化
Ubie株式会社は、全国の20代から70代を対象に医療アクセスに関する意識調査を実施しました。生活者の7割が「適切な医療行動に迷う」と回答した結果は、社会的な課題をわかりやすく示す材料となります。データをもとに問題提起を行い、啓発につなげるプレスリリースは、「社会課題を可視化し、生活者に気づきを与える」発信のあり方といえるでしょう。
参考:「医療アクセス実態調査2025」第1弾・日本人の7割が「適切な医療行動」に迷い。情報に翻弄される実態が明らかに
さらに、病院ブランディングに関する成功事例や病院広報について学びを深めたい方は、以下の記事も参照してください。
まとめ:信頼性・独自性・社会性を意識した発信を
医療・福祉・介護業界のPRは、安心感や信頼性を前提としつつ、自社の独自性や社会的な役割をどう示すかが重要です。
本記事で紹介したポイントは、以下の3つです。
- 生活者に寄り添い信頼を築く
- 自社の強みや人を発信して独自性を示す
- 地域や社会に貢献する姿勢を伝える
さらに、利用者・従業員・地域社会という対象ごとに施策を整理し、専門用語の使い方やセンシティブ情報の扱いにも配慮することが欠かせません。調査発表やイベントを通じた具体事例も参考にしながら、自社ならではの取り組みを発信すれば、生活者や地域社会の共感を得て、組織の信頼と持続的な成長につなげていくことができるでしょう。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする