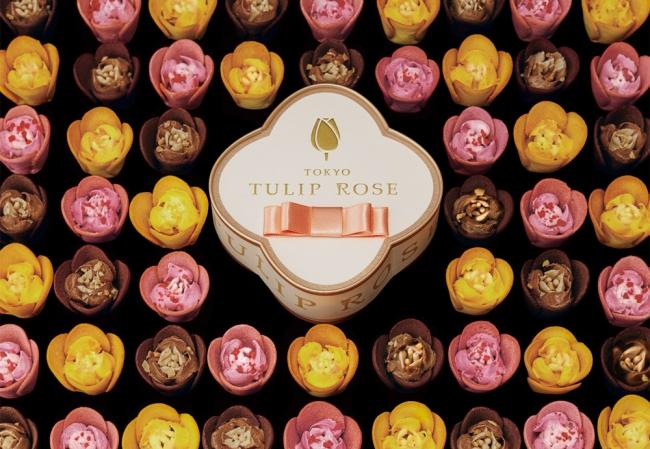2021年に、プレスリリース発信文化の普及と発展を目的として始まった「プレスリリースアワード」。1年間のうちに日本で発表されたプレスリリースの中から、プレスリリースの可能性拡大に貢献していると評価できるものを審査・選考し、表彰します。これまで過去4回の開催で、合計5,000件を超えるエントリーがあり、大企業から地方のスタートアップ、学校や個人まで、多様なプレスリリースが受賞してきました。
今年も当アワードの開催へ向け、審査員を務める株式会社はねの矢嶋 聡さんと、株式会社PR TIMESの三島映拓さんによる審査のポイントを解説するセミナーを実施。審査員のおふたりは、プレスリリースのどのような点を見ているのでしょうか。
2024年度受賞プレスリリースから見る審査のポイントや、最終審査に進んだプレスリリースを讃える「Best101」の選出理由を解説しています。エントリーに必要な「プレスリリースを発信した背景・目的」「社内外に与えた影響や反響」「こだわったポイント」などの項目を入力する際の参考にしてください。
本レポートは、7月7日にオンラインで開催したセミナーの当日の内容をもとに、お届けします。
【登壇者の紹介】

株式会社はね 代表取締役
ネットベンチャー2社でマーケティング→NY留学→PR会社勤務を経て2008年にネイバージャパン株式会社(現:LINEヤフー株式会社)入社。コミュニケーションアプリ「LINE」の広報・マーケティング統括を経て2017年10月より株式会社メルカリにてグループ広報責任者を務める。2023年3月末にメルカリを退社し、同年6月にPRコンサルティング会社「はね」を設立。

株式会社PR TIMES 広報PR管掌取締役
1980年島根県生まれ。2003年東京大学文学部卒業。05年ベクトル入社。07年PR TIMES入社後、CS、PRプランナー、アライアンス、広報などを経験し、17年より取締役。経営管理とPR・HRを担う。プレスリリースアワードとプレスリリースエバンジェリストの立ち上げと審査員を務める。PRで大切にするのは共感と信用。
第5回目となる「プレスリリースアワード」
2021年に、プレスリリース発信文化の普及と発展を目的として始まった「プレスリリースアワード」。プレスリリースを発信するという習慣が、業態・規模・地域・法人個人を問わず広がり、表現方法や用途にも発展性を持たせることを目指しています。エントリーされたプレスリリースは、社会性や公益性、共感性、将来性などの視点から、プレスリリースの可能性拡大に貢献しているものを選出し、「プレスリリースの日」である10月28日前後に表彰式を実施しています。
また、プレスリリースアワードでは大賞や最優秀賞は設けておらず、一つひとつの異なる魅力に着目して審査される点も特徴です。2023年からは、受賞に至らなかったものの最終審査に進出したプレスリリースを「Best101」として発表。発表に携わった方々の活躍を、より広く伝えられるよう取り組んでいます。
受賞プレスリリースから見る審査のポイント
ここからは、昨年2024年度プレスリリースアワードを受賞したプレスリリースの中から4本を取り上げ、審査員のおふたりに審査のポイントを詳しく解説していただきます。
インフルエンス賞:株式会社ヤッホーブルーイング

参考:【飲み過ぎの原因は飲むペース】適正飲酒を実現する“飲みづらい”グラス「ゆっくりビアグラス」開発
意外性と企業の本気度が光る
矢嶋さん(以下、敬称略):最初にご紹介するのは、2年連続で「インフルエンス賞」を受賞した、株式会社ヤッホーブルーイングのプレスリリースです。ビールの会社であるにもかかわらず「飲みづらいグラスを開発」というタイトルに意外性があり、読み手の興味を引くアイキャッチが印象的でした。
厚生労働省が示す適正飲酒のガイドラインに対する認知度の低さに加え、実際に「飲みすぎた経験がある人」や「飲みすぎないように意識していること」などのデータを交え、社会課題としての側面が取り組みの背景として丁寧に描かれています。そのうえで、「個人の努力に頼るだけでなく、ビールメーカーとしてできることがあるのではないか」という企業の問題意識がしっかり語られ、その解決策として、あえて「飲みにくいグラス」を開発したというストーリーが展開されているのが特徴です。
さらに、グラスの効果に対する専門家のコメントも盛り込まれており、メディアとしてはこのプレスリリースだけで取材のイメージができ、企画が1本できてしまうほど情報が整理されています。
私が特に高く評価したのは、これが一過性の企画ではなく、同社がこれまでも継続的に適正飲酒に向き合ってきたという会社としての一貫性が書かれている点です。単なる一発の打ち上げ花火ではなく、長期的にこのテーマに向き合おうという本気度や強い意志を感じることも、高評価につながりました。
一般的に「長いプレスリリースは読まれない」と言われることもありますが、同社のプレスリリースはストーリーや背景、企業の姿勢、専門的見解など、読み手が知りたい要素が一貫して網羅されており、長さを感じさせません。ほかの企業にも参考にしてほしい好事例と言えるでしょう。
「なぜ?」という問いを引き出し、取材につなげる構成力
三島さん(以下、敬称略):このプレスリリースを読んでまず印象的だったのは、インタビューを引き寄せるような構成になっている点です。「なぜビール会社が飲みにくいグラスを作ったのか」という、メディア側からの問いを引き出すような設計がされていると感じました。
しかも、その問いに対する答えもしっかりと用意されていて、開発に至った社会背景や課題、グラスを試せる場所の案内、アンケート調査の結果、さらには専門家のコメントまで、メディア視点で取材に必要な要素がすべて網羅されています。実際にこの取り組みは国内外のメディアで大きく取り上げられ、話題となりました。その実績も踏まえると、「インフルエンス賞」にふさわしいプレスリリースだったのではないでしょうか。
矢嶋:「PR TIMES MAGAZINE」の記事も読んだんですが、こういう取り組みはパブリシティを取るための人気取り施策と思われがちです。しかし、きちんとエビデンスをつくるのに力を入れたとおっしゃっていて、だからこそ説得力がある。単純な上っ面の人気取りのための施策ではなく、会社として本気で取り組んでいることが伝わりましたね。
ヤッホーブルーイングの評価ポイント
- 意外性あるタイトルと「なぜ?」を引き出す構成:意外性のある切り口で、取材したくなる問いと解がある
- 社会課題に根ざしたストーリー設計:社会課題に対しての企業姿勢を表現している
- 継続的な取り組みによる本気度の伝達:一過性の企画ではなく、過去の取り組みからの延長として展開されており、企業の本気度と信頼性が伝わる
同社広報の渡部さんは、「ゆっくりビアグラス」を通して「ゆっくり飲む」という認識や行動の変容を起こすためにも、「確かさ」を特に大切にされたそうです。アンケート結果や有識者のコメントなど裏付けとなるファクトが盛り込まれたプレスリリースからも、そのこだわりが感じられます。矢嶋さんからコメントがあった取材では、企画からプレスリリース発表までの過程を伺っているので、ぜひ参考にしてみてください。
ソーシャル賞:株式会社ヘラルボニー
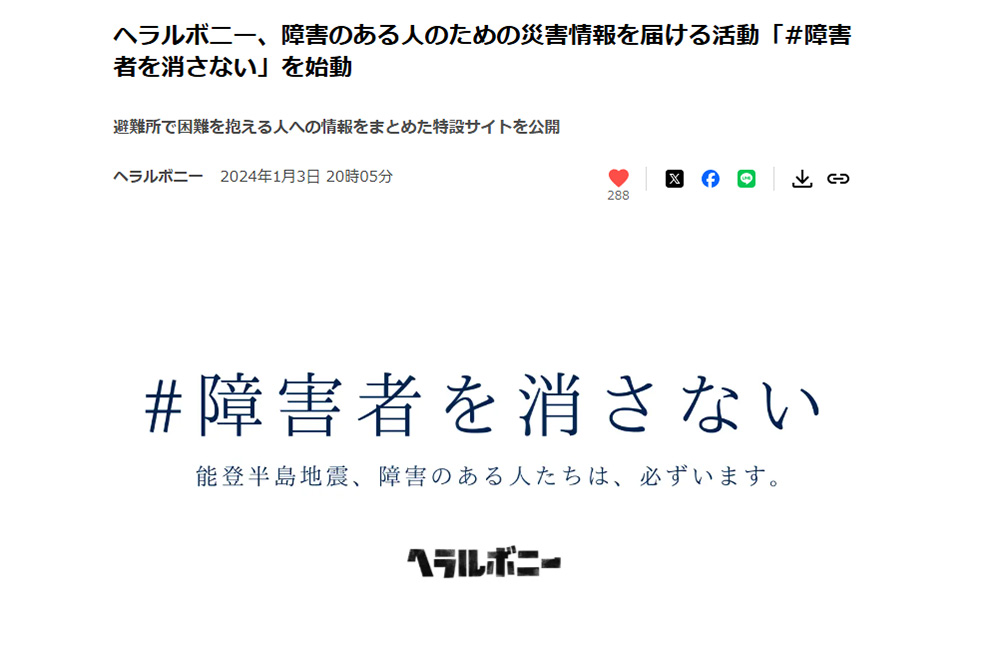
参考:ヘラルボニー、障害のある人のための災害情報を届ける活動「#障害者を消さない」を始動
一貫した企業姿勢
三島:次に紹介するのは、「ソーシャル賞」を受賞した株式会社ヘラルボニーのプレスリリースです。ヘラルボニーは、2025年6月に開催された世界最大級のクリエイティビティの祭典「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」にて、「Glass: The Lion for Change」部門でゴールドを受賞している企業です。障害のある作家のアート作品を起点に、福祉のイメージを変えることを目指す事業やビジョンが国境を超えて高く評価されたわけですが、このプレスリリースからも、同社の姿勢を強く感じることができます。
内容は、2024年1月1日に発生した能登半島地震に対し、わずか2日で支援サイトを立ち上げたことを伝えたもの。このような緊急時には「スピード感」が称賛されがちですが、私が強く感じたのは「継続性」です。日頃から障害のある方の社会参加や、取り巻く環境について深く考え、行動してきた企業だからこそ、休暇中という制約の中でも即座に、そして本質的な支援につながる動きができたのではないでしょうか。
プレスリリースでは、東日本大震災の際の課題を振り返りながら、「今、何ができるのか」に真摯に向き合っている点が印象的でした。現実的に動けるリソースが限られている中、シンプルでタイムリーな発信が、結果的に多くの人の心を動かし、力を持った情報となったのではないでしょうか。引用されたコメントは胸が苦しくなる内容でしたが、それでも「ここから何かを始められる」と信じさせてくれるようなプレスリリースになっていたと思います。
社会課題に鋭く切り込み、当事者以外にも問題提起
矢嶋:障害のある方々をエンパワーし、アート作品やファッションを展開している企業が、障害のある方のための特設サイトをつくったというのは、ある意味で王道の取り組みにも見えるでしょう。しかし、このプレスリリースが特に注目されたのは、東日本大震災の事例を挙げて、見過ごされがちな現実の「闇」の部分に光を当てた点です。「障害者が消えた」「ガムテープで娘の口をふさごうと思った」といった非常に強い言葉を使うことで、当事者以外の人たちを巻き込む力強さがありました。
単に情報を伝えるだけでなく、より多くの人に届く強い語り口で問題提起をする構成になっていて、プレスリリースのあるべき姿を体現していると感じました。取り組みそのものの素晴らしさはもちろん、この社会課題を広く届けようとする強い意志が高く評価されたポイントです。
ヘラルボニーの評価ポイント
- 「継続性」と「信頼感」:一時的な対応ではなく、平常時の事業の延長である
- 当事者以外にも響く強いメッセージ性:「障害者が消えた」「ガムテープで娘の口をふさごうと思った」など、強い言葉で社会全体に問題提起している
- プレスリリースとしての完成度の高さ:伝えるべき本質を押さえ、多くの人に広く伝える設計になっている
同社代表の松田崇弥さんは、広報PRには「意思を宿すことが重要」だと考えているのだそう。その姿勢がプレスリリースにも表れているのではないでしょうか。松田さんの取材もあわせてご覧ください。
ヒューマン賞:ピジョン株式会社

参考:口唇裂・口蓋裂や疾患などで哺乳が困難な赤ちゃんと家族のための哺乳器 病院と家族の声をもとに、より使いやすい仕様に改良した「ロングフィーダー」新発売
読み手に届く要素を網羅
三島:「ヒューマン賞」を受賞したのは、ピジョン株式会社のプレスリリース。これは、まさに「お手本」と呼べるプレスリリースではないでしょうか。いくつもの重要な要素が的確に押さえられており、情報設計の完成度が非常に高いと感じました。
まず注目すべきは、タイトルです。プレスリリースはタイトルがとても重要で、特に冒頭の10〜20文字には、読み手の目を引くためのアイキャッチとしても非常に大切な役割があります。このプレスリリースでは、「口唇裂・口蓋裂」という疾患名をタイトルの最初に明記することで、まさにその情報を探している人たちに届きやすい設計になっていました。情報があふれる中で、数秒で「これは読むべき」と判断してもらえる工夫がなされている点が、高く評価できます。
また、商品自体はマイナーであっても、その背景や意義が丁寧に語られている点も印象的です。なぜこの商品が生まれたのか、企業としてどのような想いで長年取り組んできたのかが明確に伝わってきました。さらに、商品の特徴を図解と文章の両方でわかりやすく説明しており、視覚的にも理解を助ける構成になっています。加えて、利用者の声として医療従事者と家族双方のコメントが掲載されることで信頼性を高めているのもポイントです。単なる商品紹介にとどまらず、企業としての姿勢やプロジェクト全体の文脈の中での位置づけも伝わってくる内容でした。
客への愛情や寄り添う姿勢が自然と伝わる
矢嶋:こうしたプレスリリースは、リニューアルの事実やスペックだけに終始してしまうことが多い中で、非常に説得力のある構成になっていました。取り上げられている疾患は、500人に1人と発生頻度が高く、なおかつ成長に合わせて長期的な治療を必要とするという現実があります。そうした課題にきちんと光を当てたうえで、「だからこそこの商品が必要なのだ」という必然性が明確に示されており、非常に説得力のある内容になっていたのではないでしょうか。
また、この領域に40年以上取り組んできたという事実も重要で、一過性のCSR活動ではなく、子どもとお母さんの成長を一貫して見守ってきた企業としての姿勢が、しっかりと伝わってきました。お客さまへの愛情や寄り添う姿勢が、文章の節々から自然と感じられるプレスリリースだったと思います。
ピジョンの評価ポイント
- ターゲットに届くタイトル設計:必要な情報を探している人に確実に届くタイトルになっている
- 図解と文章の両方でわかりやすく解説:商品の特徴が視覚的にも伝わる工夫がされている
- 医療従事者と家族の声を紹介:両者の立場からのコメントによって製品の信頼性・必要性が補強されている
- 企業の姿勢とブランド哲学がにじみ出ている:企業の継続的な姿勢や、子どもと家族に寄り添う企業としての愛情が伝わる
イノベーティブ賞:株式会社オレンジ

参考:オレンジ、総額29.2億円のプレシリーズA資金調達を実施
自分たちらしさを大切にした発表
矢嶋:資金調達のプレスリリースは、構成がある程度テンプレート化しているケースが多必要な情報を探しているく見られます。「どの投資家から出資を受けたか」「資金の用途は何か」「投資家のコメント」といった要素を順番に並べるスタイルが一般的で、それに関心を持つ読み手もスタートアップ界隈や専門メディアに限定されがちです。
しかし、株式会社オレンジのプレスリリースは、「どういう世界を目指そうとしているのか」「日本のどういう課題を解決したいのか」など、資金調達の「先」にあるビジョンが描かれている点が非常に印象的でした。日本のマンガを翻訳し、海外にエンタメカルチャーを届けることをミッションに掲げている企業らしく、プレスリリースもマンガで表現されていて、自社の立ち位置と一貫した発信スタイルが確立されている点が高く評価されました。
マンガという手法は、奇をてらった印象を与えることもありますが、同社の場合は事業内容と手段がしっかりと結びついているため、単なるギミックではなく、説得力のある伝え方として機能しています。スタートアップ界隈以外の人たちも応援したくなるプレスリリースだったのではないでしょうか。「自分たちらしさ」をプレスリリースでどのように表現するのかは、「プレスリリースアワード」においても評価ポイントのひとつになると思います。
事業との連動性の高さが評価ポイント
三島:既成概念にとらわれない発表の仕方を、自社の事業に連動させた形で実現している部分が、高く評価されたポイントです。
マンガのプレスリリースは時々見かけますが、ここまでリッチな内容のものは珍しいのではないでしょうか。縦スクロールで読み進められる点も、Webの特徴をいかに活かすのかという視点でつくられていて、素晴らしいと思います。
イノベーティブ賞にどのプレスリリースを選ぶのかは、毎年の審査会で議論になりますが、発表の形が珍しいというだけでなく、それをどう活かしているのかという点において、非常に連動性の高い事例でした。
オレンジの評価ポイント
- 事業と手法の一貫性:事業内容やミッションと結びついており、表現方法と企業の立ち位置にブレがない
- ビジョンの明確な提示:「どんな世界を目指すのか」「どの社会課題を解決したいのか」という資金調達の「先」が描かれている
- テンプレートに頼らない表現の工夫:縦スクロールなどWebの特性を活かしたリッチな構成で、オリジナリティと訴求力を発揮
最終審査に進出!「Best101」プレスリリースを振り返る
最終審査に進んだプレスリリースを讃える「Best101」は、どのような基準で選ばれたのでしょうか。ここではノミネート作品のうち、4件の実例を交えて、審査のポイントを紹介していきます。
東海電子株式会社

参考:【飲酒運転できないクルマ専門店】アルコールインターロック搭載中古車販売事業を始めました
引っかかりのあるタイトルで読み手の関心を集める
矢嶋:こちらは、東海電子株式会社がアルコールインターロック搭載の中古車販売事業を開始したことを伝えるプレスリリースです。「飲酒運転できない車専門店」というタイトルで関心を引きつけ、内容で納得させる構成が素晴らしいと思いました。飲酒運転による死亡事故という社会課題に対して単なる予防では限界がある中で、「飲酒していると物理的に運転ができない仕組み」を開発したというストーリーが、エビデンスとともに丁寧に描かれています。千葉県八街市の事故をきっかけに「安全な車を求める声が増えてきた」というリアルな背景も盛り込まれており、この取り組みが生まれた必然性が、説得力を持って伝わってくるのではないでしょうか。
特に印象的だったのが、将来的には自動運転で飲酒運転がなくなるかもしれないが、「そんな未来を待っていられない」という企業姿勢が、「自動運転まで、待てない、待たない。企業やテクノロジーは、明日のいのちにも責任があります。」というメッセージで表現されていたこと。社会を少しでも前進させるために、今できることに取り組むという姿勢は、ほかの企業にも広まってほしいと感じました。
一方で、あと一歩だった点を挙げるとすれば、アルコールインターロックの仕組みについての情報が少なかったこと。例えば、実際にどのように作動するのか、どんな精度なのかといった情報があると、より説得力が増したと思います。また、実際に導入したお客さまの声や導入効果などがあると、読み手の納得感がさらに高まったのではないでしょうか。
読み手の認識変容を促す
三島:今起きている社会問題に対して、自社の事業を通じてどう向き合うのか。この点をしっかりと入れ込んでいただいたプレスリリースだったと思います。読み進めることで、現状を知ることができ、読み手の認識変容にもつながっていく構成が評価されたポイントです。
テーマが素晴らしいことはもちろん、タイトルで「飲酒運転できない車専門店」という引っかかりをつくって、読み手を引き込んでいくという、よく作り込まれたプレスリリースだったのではないでしょうか。
東海電子の評価ポイント
- 社会課題への真摯な取り組み:社会問題に対し、顧客の声も含めて説得力あるストーリーを構成
- 認識変容につなげるタイトル・構成:「飲酒運転できない車専門店」という強いタイトルで読み手を引き込む工夫がされている
- 企業の姿勢を力強く表現:社会に対する責任感と行動力を明確に発信
東海電子株式会社の中山春美さんは、プレスリリース配信において「一過性ではない継続的な啓発」と、「誰もが自分ごととしてとらえられるメッセージを届け続けること」を大切にされているそうです。受賞プレスリリースからも、中山さんのそのような思いが感じられます。
株式会社一の坊

参考:CO2排出量42%削減、地球にやさしいサステナブルな温泉リゾートへ【東日本の温泉宿初!省エネ大賞受賞】
実効性ある取り組みをわかりやすく
矢嶋:こちらは、温泉リゾートを展開する株式会社一の坊が、省エネ大賞を受賞したことを伝えるプレスリリースです。受賞リリースは多くの企業が発信していますが、同社は受賞理由や具体的な取り組みについてしっかりと書かれている点に好感が持てました。特に、温泉の熱エネルギーに着目した取り組みや、それを「快適エコ活動推進委員会」という現場主導で全社一丸となって進めたという背景まで丁寧に解説され、プロセスが可視化されている点が印象的でした。
また、「オーダービュッフェスタイル」の導入により、作り置きせずにその場で調理することで、フードロスを実現しているだけでなく、できたてを食べられるという顧客満足も両立。単に「エコに取り組んでいます」という一方的な発信ではなく、利用者側にもメリットがある取り組みとして描かれている点が秀逸です。
一方で惜しかった点を挙げるなら、タイトルにもうひと工夫あるとよかったかもしれません。たとえば、「地熱活用で省エネ大賞」「全社員の創意工夫で受賞」といった、もう少し注目を集める表現ができたのではと感じました。
働く人の顔を見せることで温度感が伝わる
三島:同社は「地方の宿泊施設のロールモデルを目指す」という想いを持っており、その姿勢がプレスリリースにも強く表れていたのではないでしょうか。詳細な取り組みや実績をまるで「どうぞまねしてください」と言わんばかりに紹介しており、ほかの施設にとっても非常に参考になる内容です。
特に印象的だったのは写真の使い方です。単に施設を美しく見せるだけでなく、現場で働く社員の姿がしっかりと写っていることで、誰がどのようにこの施設を支えているのかが伝わってきます。「人の顔が見える」構成によって、非常にハートフルなプレスリリースになっていました。
一の坊の評価ポイント
- 具体的な取り組みと受賞理由の明示:単なる受賞報告にとどめず、背景やプロセスを丁寧に説明している
- 利用者側のメリットも発信:エコの観点だけでなく、利用者視点の実利が描かれている
- 人の顔が見える写真で温度感を演出:現場で働く社員の姿を写すことで、企業の姿勢や温度感を発信している
ポケットフーズ株式会社
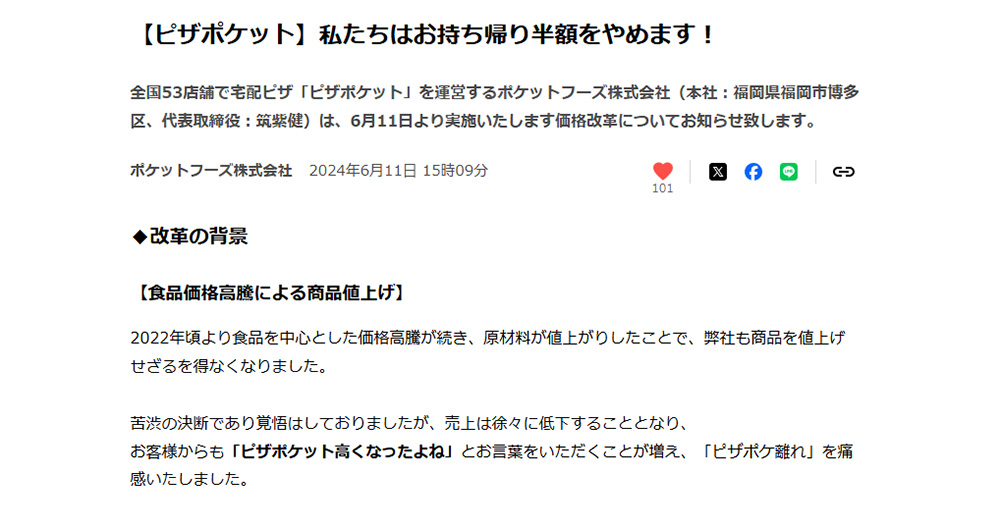
情報共有で「共感」を醸成
三島:ポケットフーズ株式会社のプレスリリースは、価格改定という一見ネガティブに捉えられがちな情報を、背景を語りながら共有することで共感を生む構成になっており、今の時代感にとても合ったプレスリリースだと思いました。
一般的に価格改定のプレスリリースは事実のみを最小限で伝えるケースが多い中で、「なぜそうしたのか」「どんな想いがあるのか」を開示することで、読み手に対してフラットに向き合おうとする姿勢が伝わってきます。
また、「業界では持ち帰り半額が通例」としたうえで、タイトルで自社のスタンスを打ち出した点もユニークです。前半は文章中心で静かに語り、後半でビジュアルを活用して印象を強める構成の切り替えも巧みでした。文章の流れも起承転結が明確で、読み手に伝わりやすい設計になっている思います。
価格改定を「企業姿勢」として伝えた好例
矢嶋:価格改定のプレスリリースは多くの場合「原材料高騰のため価格を改定しました」という事実のみの羅列になりがちですが、同社はそれを「会社のスタンスを発信する機会」として活用していた点が印象的でした。
「お持ち帰りは半額」という業界慣習をリセットし、そのうえで価格を全面的に見直す。そして、ただ値上げするのではなく、「安くておいしい」というミッションを守るために、味は落とさずサイズで調整する。そうした誠実な姿勢を明確に言葉にしており、読んだ人の信頼につながる内容だったのではないでしょうか。
ポケットフーズの評価ポイント
- 背景や想いを丁寧に伝え共感を創出:価格改定に至る理由や企業の考えをしっかりと説明し、読み手との信頼関係を築く姿勢が伝わる
- 業界慣習に対する自社のスタンスを明確に提示:「持ち帰りは半額」という通例を見直した自社の方針を打ち出している
- 読みやすさを意識した構成:画像を使って補足されており、視覚的にも伝わりやすさが意識されている
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン
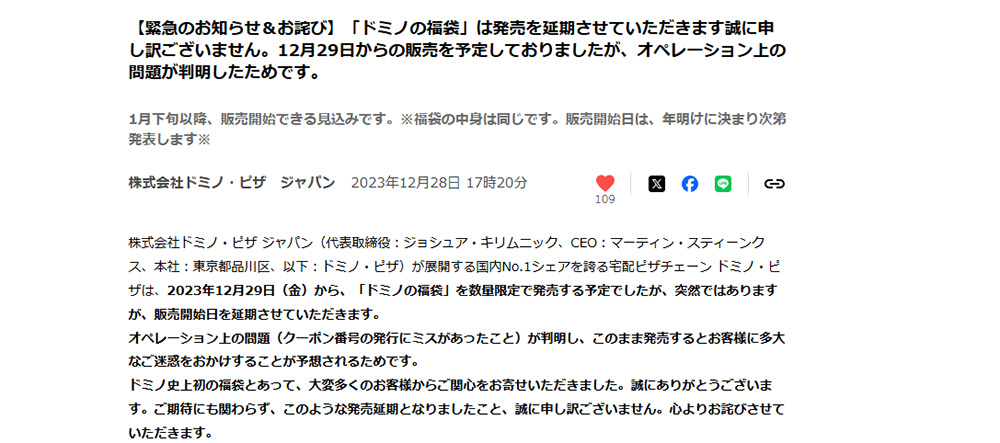
参考:【緊急のお知らせ&お詫び】「ドミノの福袋」は発売を延期させていただきます誠に申し訳ございません。12月29日からの販売を予定しておりましたが、オペレーション上の問題が判明したためです。
危機対応に現れる企業姿勢
三島:最後にぜひ取り上げておきたいと思ったのは、何かトラブルが発生した後の広報対応として参考になる事例です。お詫びや訂正などのネガティブ対応は、広報のあり方次第でその後の流れが変わります。そういう意味でも、ドミノ・ピザ ジャパンのプレスリリースは、参考になる事例のひとつといえると思います。
印象的だったのは、スピード・正確性・企業姿勢という危機広報において重要な3要素をしっかり押さえていた点です。発表されたのは12月28日17時20分という年末のぎりぎりのタイミング。プレスリリースは、限られた状況で今出せる正確な情報を取捨選択し、事実と予定を分けて整理したコンパクトな構成になっています。
また、内容もお詫びとお礼、決定事項に絞って、無駄のない表現でまとめられており、混乱を抑えるための誠実な広報対応だったと感じます。年末のタイミングで出すということは、批判や炎上のリスクもあったはずです。しかし、それでも逃げずに向き合おうとした企業の姿勢が伝わるプレスリリースでした。
「伝える相手」を第一に考えた異例の構成
矢嶋:ネガティブな事象が起きたとき、多くのプレスリリースはメディアのことを意識して、「発生経緯・原因・対策」といったテンプレート的な構成になりがちです。しかし、今回のプレスリリースは、形式よりも「誰に何を今すぐ伝えるべきか」という視点で構成されていました。
タイトルもいわゆる定型の枠を超え、「お客さまに伝えたい」という強い意志が感じられます。文章は急ぎ書きのように五月雨的ですが、だからこそ緊急性と真剣さが伝わり、お客さまへの誠実な姿勢がよく表れていたと思います。
会社にとっては「危機」だったかもしれませんが、「お客さまにきちんと向き合う会社」だということが伝わり、むしろ好感を持つきっかけになったのではないでしょうか。そういう意味でも、プレスリリースの価値が最大化された事例だと言えます。
ドミノ・ピザ ジャパンの評価ポイント
- 「スピード・正確性・姿勢」を押さえた対応:今出せる情報を整理して迅速に発信することで企業姿勢を伝えている
- 形式よりも「伝える相手」を優先:テンプレートにとらわれず、相手に必要な情報を最優先で届けることを意識した構成になっている
まとめ:2024年プレスリリースアワード審査から見えた評価基準
今回のセミナーでは、プレスリリースアワードの審査員のおふたりから、2024年のプレスリリースアワード受賞作品や「Best101」に選出されたプレスリリースの具体的な評価ポイント、審査会で交わされた議論の視点などについて詳しくお話を伺うことができました。
2024年受賞作品の主な評価ポイントは以下の通りです。
- 社会課題への向き合い方と企業姿勢の提示:単なる商品やサービスの紹介にとどまらず、「その取り組みはなぜ必要なのか」という社会的背景や企業のスタンスが明確に語られているか
- 意外性や共感を生む「ストーリー性」:意外性のある切り口や、読み手の心を動かすストーリーを通し、「思わず続きを読みたくなる」内容になっているか
- 読み手ファーストの構成・伝わりやすさ:情報が整理され、読みやすく、ビジュアルや図解も駆使し必要な情報が届く構成か
- 継続性や一貫性のある取り組み:一過性の話題づくりではなく、過去から積み上げた実績や姿勢がにじみ出ているか
- メッセージ性と「誰に届けたいか」を明確に:タイトル・語り口・構成などを通して、「誰に何を届けたいのか」が明確になっているか
これらは、プレスリリースを配信する際にぜひ参考にしていただきたいポイントです。プレスリリースアワードのエントリー時に限らず、これから配信を予定しているプレスリリース作成の際には意識してみてください。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする