本記事は、公益財団法人筑波メディカルセンターで広報を担う、遠藤友宏氏に監修いただきました。
広報誌は、病院から発行することで患者・地域住民はもちろん医療関係者・施設にも認知拡大を見込める広報PR施策です。病院広報誌のメリットを発揮するためには、その目的や読者層を理解したうえでコンテンツ・構成などを検討しなければなりません。
今回は、病院広報の役割やメリットのほか、制作における具体的なフローを解説します。企画段階で役立つコンテンツのアイデアと広報誌の活用方法もご紹介していますので、病院のブランディングを思索している方はぜひ参考にしてみてください。
病院の広報誌とは?
病院広報誌のおもな目的は、認知拡大と正しい医療知識の発信。外から見えづらい自院のよさを伝えるために有用な広報PR活動です。目的と役割を理解し、想定する読者層に届く広報誌を作り上げていきましょう。まずは病院広報誌の基本的な役割と、念頭に置いておきたい読者層について解説します。
病院広報誌の基本的な目的・役割
病院から発行する広報誌には、以下のような目的・役割があります。
- 病院そのものの認知度を高める
- 通院患者やその家族の信頼感・安心感を高める
- 地域住民へ自院の情報を届ける
- 地域の自治体・関連施設へ情報を届ける
認知拡大という目的は一般的な広報誌と同じですが、病院広報誌においては信頼感・安心感を高める役割が大きいといえます。院内スタッフの様子を写真で紹介したり、コラムを掲載したり、通院のみでは見えづらい内面を広報誌で可視化することにより「自院らしさ」「自院のよさ」を伝えているためです。
病院広報誌の読者層
病院広報誌は通院患者のほか、以下のような読者層を想定しています。
- 現在の通院患者
- 過去に来院・通院した患者
- 来院経験のないの生活者
- 医療施設や地域の関連施設関係者
- 潜在的な求職者(医療従事者)
現在の患者や地域住民が読者層の中心といえますが、紹介元となる医療・地域施設の関係者も重要な読者です。さらに、潜在的な求職者に自院の情報が届けば、働く場所としての意義・魅力を伝えるきっかけにもなるでしょう。
広報誌と他広報PRツールとの違い
広報PR施策においていくつかのツールがあげられますが、それぞれ以下のような違いがあります。
- 広報誌:雑誌のような冊子を特定エリアで配布
- チラシ:1枚の紙を特定のエリア、折込チラシで配布
- マスメディア:テレビCMや新聞などで不特定多数に発信
- Web広告:SNSやWebサイトで画像・動画を掲載
- プレスリリース:メールや配信サービスで発信
広報誌の特徴は、多くの場合カラー印刷であり、複数ページにわたって複数のコンテンツが収録されているという点です。雑誌のような冊子である広報誌に対しチラシは1枚であるため、印刷コストは抑えられるものの掲載情報が少ないデメリットがあります。
テレビCMや、Webサイトに掲載する広告も広報PRツールのひとつ。特定の企業・団体に送付する公式文書だけでなく、Webサイト・サービスを通したプレスリリース配信も多くの病院が活用しています。
広報PRツール全体で見ると、配布場所は限られるものの掲載内容・ページ数・配布エリアを調整しやすい点が病院広報誌の特徴といえるでしょう。
企業の社内報・自治体広報誌との違い
病院の広報PR活動に類似するものとしてあげられるのが、自治体の広報誌や企業の社内報です。広報PRとして認知を広める目的は同じですが、細かい目的や対象者は異なります。
- 病院広報誌:患者や地域住民、自院の関連施設・医療関係者
- 自治体広報誌:地域住民や自治体関係者
- 企業の社内報:自社の従業員
自治体広報誌のように同じ地域住民を読者層とする場合でも、健康に直接関わる情報を扱う点において病院広報誌は信頼性が特に重要です。
また社内報は自社の従業員に向けて発信しますが、病院広報誌は患者・地域住民・院内スタッフのほか、院外の関係者に情報を届ける機会にもなるため読者層に大きな違いがあるといえるでしょう。
病院が広報誌を発行する3つのメリット
病院が広報誌を発行するメリットとしては、院内・院外ブランディングやコミュニケーション機会の強化といった点があげられます。自院以外の施設に設置することで間接的なアプローチも見込め、地域とのつながりを深めたり、来院を促したりするきっかけになるかもしれません。病院における広報誌のメリットについて、3つの項目に分けて解説します。
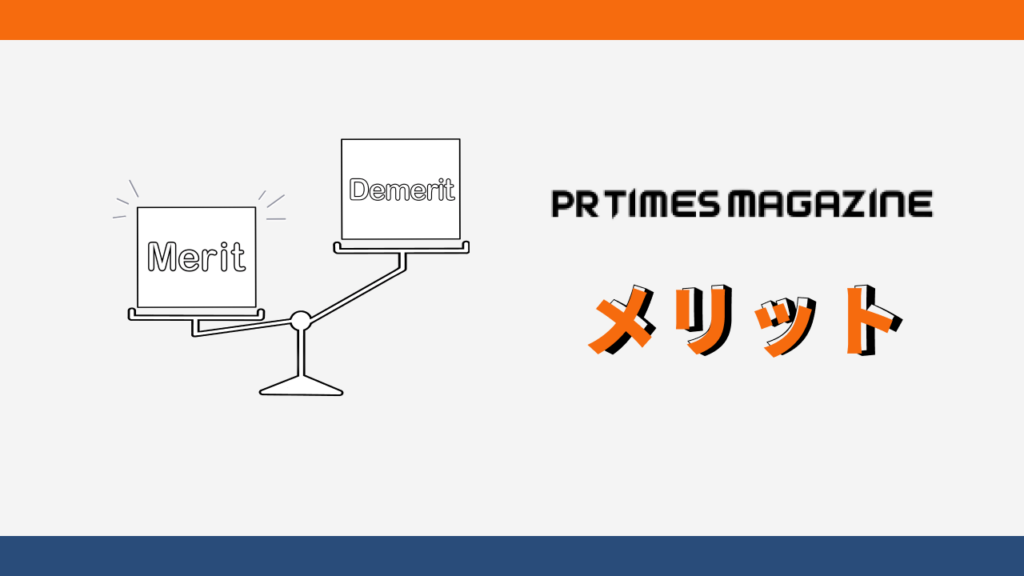
メリット1.内面的な強み・魅力を可視化できる
病院の広報誌における大きなメリットのひとつは、内面的な部分を表面化しやすいという点です。生活者は病院の外から実態をつかみにくいため、病院そのもののイメージを外観や周辺の様子など外面的な要素に頼ってしまいます。
「病院の建物が古いため最新機器の導入を知られていない」「アクセスが悪く遠方からの来院が極端に少ない」といった場合、広報誌の発行は認知拡大・利用促進を図る有用な施策といえるでしょう。広報誌で自院のよさや取り組みなど内面的な部分を発信することで、来院経験のない生活者にも情報を届けられます。
メリット2.病院以外の場所でコミュニケーションを図れる
すでに来院経験がある生活者や現在通院中の患者にも、広報PR施策としてのメリットを享受できます。自院の出入り口や待合室に広報誌を配置することで、患者やその家族が帰宅後にゆっくり読む時間を確保しやすいためです。
普段通院のみで病院の情報を深く知らない人でも、広報誌を通してさまざまな取り組み・人物について知るきっかけになるでしょう。患者や家族自らが病院の情報を知ることで、「〇〇健診・検査を受けてみよう」「別の症状のときに〇〇科へかかってみよう」と促し、さらに病院のイメージアップにつなげる効果も期待できます。
メリット3.間接的なアプローチで来院を促せる
自院以外の関連施設に広報誌を配置できれば、間接的なアプローチが可能です。関連の医療施設や地域の施設を利用した人に広報誌を読んでもらうことで、自院の強みや力を入れている診療科目などの認知を拡大できるでしょう。
すでに別の病院へかかっている患者も、広報誌をきっかけに自院を利用する機会を得られるかもしれません。自院の利用を見込める潜在層だけでなく、地域住民を中心とする幅広い層にアプローチできるのが広報誌のメリットでもあります。
病院広報誌の基本的な構成
広報誌を制作する際には、基本的に以下のような構成を組み立てていきます。
- 表紙:タイトルやキャッチコピー、メインビジュアルなど
- 目次:企画一覧とページ数
- コンテンツ:記事・企画・特集
- 裏表紙:自由(自院の情報など)
コンテンツは広報誌の核となる部分ですが、具体的な内容はコラム・特別企画・連載企画・特集ページなどさまざまです。上記は広報誌全般にいえる構成であるため、病院広報誌の場合は「自院ならでは」を意識することが重要。
特に広報誌は手に取って、開いて初めて目に届く情報でもあります。生活者が興味を持つ表紙写真を掲載したり、次号が楽しみになる連載企画を考えたりといったコンテンツ力が必要です。発行する一部のみならず、バックナンバーや次号以降も継続的に手に取ってもらえるような内容と構成を考えていきましょう。
なお、一般的な広報誌・広報紙の違いや制作のポイントについては以下の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧になってみてください。
参考:広報誌とは?「広報紙」との違い・制作時の7つのポイント【事例紹介あり】
病院広報誌の企画・コンテンツアイデア
病院広報誌の内容を考える際は、魅力的かつ独自性の高いコンテンツを盛り込むことが大切です。オリジナリティを高めるには、自院が強みとする設備を紹介したり、院内で働くスタッフの様子を取材したりといった企画が提案できます。人物紹介やイベント関連など4つのカテゴリをピックアップしますので、アイデア出しの参考にしてみてください。
院内の人物を紹介するコンテンツ
「この病院でどんな人たちが働いているか」を可視化するためには、医師・看護師やその他スタッフを取り上げたコンテンツが有用です。
- 院長のあいさつ
- 常勤医師・看護師の紹介/インタビュー
- 新任医師の紹介/インタビュー
- 介護・リハビリなどその他スタッフの紹介
病院はどうしてもいきづらいイメージを抱きやすいため、院長・医師の実績やスタッフの明るさなど、人となりが見える企画があれば信頼感・安心感につながります。人物を紹介するだけでなく「この病院の魅力は?」「心がけていることは?」など個人にフォーカスしたインタビューを掲載してもよいでしょう。
病院での働き方・過ごし方が見えるコンテンツ
院内スタッフからさらに視野を広げ、病院全体での過ごし方を紹介するコンテンツもおすすめです。病院でどのような設備を導入しているか、医師・看護師が利用している写真もあわせて紹介できるとイメージしやすくなるでしょう。
- 院内スタッフの1日密着取材
- 医療現場の裏側
- 病院の設備紹介
生活者の不安を解消する企画
広報誌への関心を高めるためには、読み手にとって有用な情報であるかどうかが重要です。医療広告ガイドラインに注意したうえで、医師が監修したコラムを連載したり「〇〇の症状がある人でも食べやすい」といったテーマでレシピを紹介したりしてみてはいかがでしょうか。
このようなコンテンツは、読み手が有意義に感じるだけでなく、日頃の不安を解消するきっかけにもなります。通院中の患者や来院経験がある人を対象にアンケートを実施し、その結果を紹介すると客観的な評価を発信できるでしょう。
- 医師による健康コラム・豆知識
- 健康レシピの連載
- 患者の満足度アンケート
イベントや医療制度などに関するコンテンツ
病院が主催・共催するイベントがある場合は、その様子を広報誌で紹介することで対外的な取り組みを発信できます。また、健康診断や予防接種の案内情報があれば、「この機会に行ってみよう」と潜在層へ来院を促せるでしょう。
- 院内イベントのレポート
- 健康診断や予防接種の案内
- 医療制度や保険制度に関する解説
病院広報誌の制作から配布までのフロー
病院広報誌の制作をスタートした時点で、「誰に届けたいか」を明確にしなければなりません。発行する目的と読者層がわかれば、取り上げるべきテーマや適切な企画アイデアを考えやすくなります。完成・配布に至るまで複数のステップを踏む必要があるため、ひとつずつ段階的に進めていきましょう。ここでは配布前のフローを8つの項目に分けて解説します。
STEP1.発行目的・読者層を整理する
病院広報誌の読者層はおもに地域住民や患者ですが、細かいペルソナは複数パターンあげられます。以下のように、誰に届けたいのかを整理しておきましょう。自院の情報を発信する理由・目的がわかれば、読者層もイメージしやすくなるはずです。
- 現在通院している患者やその家族
- 来院経験はないが健診などを検討している人
- 病院のエリア全域に住む地域住民
- 自院と関連の深い医療関係者
STEP2.掲載する企画・構成を決める
届けたい層を整理したあとは、特集テーマを決めたり、連載枠・時事テーマを検討したりといった企画選定に移ります。構成も同時期に進行しますが、多くの場合写真も複数掲載するため、文章と写真を含めたレイアウトも決めておきましょう。
ページ当たりのレイアウトだけでなく、広報誌全体の構成も重要です。特に連載企画がある場合は、冒頭・真ん中・後半のどのページに配置するかある程度決めておくと、次号以降の広報紙と統一しやすくなります。
なおインタビューなどで医師やスタッフの協力を仰ぐ場合は、対象者のスケジュール調整も必要です。撮影や執筆の担当者を仮決めし、外部委託であればこの段階で具体的な依頼内容を整理しておきましょう。
STEP3.取材実施&ビジュアルコンテンツを用意する
企画内容や構成が固まったあとは、原稿作成に向けて素材の準備に進みます。録音機器や撮影機材をそろえて、医師や院内スタッフの取材を実施しましょう。なおこのとき、感染対策はもちろん、肖像権にも配慮が必要です。二次利用の許可も同時に取っておくと、プレスリリースやSNSなど広報誌以外の広報PRにも活用できます。
広報誌に掲載するビジュアルコンテンツは写真やイラストといった静止画に限られるため、特に写真は動きを意識することが大切。撮影時のピントや構図はもちろん重要ですが、必要であれば編集ソフトなどを活用して広報紙にふさわしい写真をそろえていきましょう。
STEP4.構成案に沿って原稿を作成する
ビジュアルコンテンツをはじめとする素材がそろった段階で、いよいよ原稿作成のスタートです。STEP2で決めた構成案に沿って、各コンテンツの文章を入れていきましょう。
インタビュー形式のまま執筆する際は、取材者と話者の区別を全体で統一するなどの書き方も重要。適宜チェックを入れながら進めるとのちの手間が省けるため、誤字・脱字などがないか確認しておくとよいでしょう。
また、生活者を対象としたコンテンツの場合、専門用語を避けてわかりやすい表現を心がけることも大切です。情報の正しさはもちろん「読み手にとって読みやすいかどうか」も意識しながら原稿を作りましょう。
STEP5.原稿をチェックして編集・校正する
広報紙に原稿を入れたあとは、表紙から裏表紙まで全体的に細かくチェックしていきます。原稿を執筆した担当者ではなく、別の編集・校正者を決めて確認できると安心です。
自院の情報をはじめ、数値・名称・用語の表記に誤りがないか、医学的に不適切な表現がないかダブルチェックを前提に進めていきましょう。コンテンツの内容に応じて、看護部長・院長・法務など確認ルートを確保することでスムーズに進行できます。
STEP6.広報誌のデザイン・レイアウトを作成する
原稿のチェックが完了し全体が固まったあとは、ビジュアルコンテンツを含むデザイン・レイアウトに進みます。各企画の見出しをわかりやすい大きさに変更したり、読者層に応じたフォントを本文に使用したり、読みやすさ・親しみやすさを重視しながら決めていくとよいでしょう。写真で視認性を高めるのが難しい場合は、イラストや図を掲載するのも一案です。
ただし、外部委託の有無にかかわらず、この段階で大幅な変更が発生する可能性もあります。魅力的な写真が多ければ予定より掲載数を増やしたり、必要であれば一部コンテンツを次号以降にまわしたりといった変更も柔軟に対応することが大切です。
STEP7.最終校了を行い、印刷会社に手配
原稿からレイアウト案、入稿までの準備が整ったあとは最終校了に移ります。広報紙のすべての関係者に校了確認を取ったうえで、印刷会社へ入稿しましょう。入稿したデータをもとに、印刷会社がレイアウトの最終調整を行います。
部数が多ければよいというものでもなく、予算はもちろん配置場所・配布人数を想定して決めなければなりません。必要な部数を印刷会社に依頼し、院内の編集メンバー全員が納品スケジュールを把握できるよう共有しておくと安心です。
STEP8.配布・設置・オンライン公開を進める
印刷会社から広報誌が届き次第、配布作業に取りかかります。院内の出入り口や待合室のほか、関係施設への設置やオンライン公開も順に進めていきましょう。物理的な配布は印刷した広報誌で行いますが、オンラインで公開する場合はプレスリリース配信が有用です。「広報誌を発行しました」のようなタイトルとともに、対外的な発信を実施するとよいでしょう。
配布後は、広報誌の反響を確認することで次号に向けた振り返りができます。来院した患者にアンケートを募るだけでなく、医師やスタッフに反響の程度・コンテンツ内容の意見などを求めてもよいでしょう。発行してから受動的に構えるのではなく「伝えたい人に読んでもらえているか」「伝えたいことが伝わっているか」を検証することが大切です。
病院広報誌を配布する方法とチャネル
広報誌の配布先として、オフライン・オンラインで以下のような場所があげられます。
- オフライン:院内とほかの関連施設
- オンライン:自院のホームページ・公式SNS・プレスリリース配信
配布先はなるべく多いほうがよいといえますが、あくまでも読者層に合った方法・チャネルを選ぶことが重要です。院内での配布は必須としたうえで、ほかのチャネルは「どこで読んでほしいか」「誰に読んでほしいか」を軸に選定していきましょう。
広報誌に関する情報をオンラインで発表する場合は、文章・写真両方の視認性を確認する必要があります。読みづらいページをWebの文章で補足したり、広報誌に掲載した写真データを用いたりしてオンラインの特性を活かしましょう。
魅力的な病院広報誌の事例3選
病院広報誌の発行を検討している方は、実際に配布されている広報誌を参考にしてみると構成・企画のイメージがつくのではないでしょうか。掲載すべきポイントや魅力的な要素がわかれば、自院の広報誌へ活かすために役立ちます。ここからは、病院広報誌の事例を中心に、参考になる点をピックアップして解説していきます。
事例1.院内イベントや治療法の導入など最新情報を豊富に掲載
高知県高知市にある社会医療法人・近森会は、広報誌『ひろっぱ』を毎月発行。病院でのイベント企画や周年記念など、さまざまな情報を親しみやすい写真と文章で豊富に紹介しています。
例えば2024年11月には、看護の仕事を離れた人を対象とした「看護のお仕事相談カフェ」を開催(※1)。事前にプレスリリースで開催日をお知らせし、翌年1月号の広報誌に開催レポートを掲載しました。
そのほかにも、同会の大きな実績となる新しい治療法の導入は、プレスリリース・広報誌ともに大々的に取り上げています。四国初の導入・症例であることを明記し、イラストを用いた治療イメージの解説で読み手の理解力を高めた好事例です。先進的な取り組みを広報誌で発信することで、地域住民はもちろん医療関係者の関心も引いています。
参考※1:【近森会グループ】11/17(日)「看護のお仕事相談カフェ」を開催します!
事例2.地域の病院ならではの外来情報や新人スタッフ情報を掲載
大阪府大阪市西淀川区で地域の病院として運営する社会医療法人・愛仁会千船病院は、千船病院広報誌『虹くじら』を発行しています。制作時にプロのクリエイターを起用し、職員一人ひとりにスポットを当てたコンテンツを掲載。
株式会社CBホールディングスが主催する「病院広報アワード2024」では、同病院が優秀賞を受賞しました。自院ならではの「頭痛外来」を取り上げたり、検査技師2年目のスタッフに密着したりといった独自コンテンツが魅力的です。
参考:千船病院広報誌~プロのクリエイターと制作する『虹くじら』4号
事例3.記念日や季節に応じたコンテンツ・企画を展開
公益財団法人・筑波メディカルセンターで広報PRを担う遠藤友宏氏は、広報誌をはじめ幅広い手段を用いた施策を展開しています。年に4回発行する季刊の病院広報誌『アプローチ』では、タイムリーかつわかりやすい内容に配慮した情報を掲載しているのが特徴です。
以下の記事では、地域住民へはもちろん、院内の広報PR活動についても言及していますのでぜひ参考にしてみてください。
病院広報誌を広報PRで活用する際の5つのポイント
病院から広報誌を発行する際には、広報PR施策としてブランディングを強化したり、採用広報に展開したりといった業務が重要です。院内の配布に限定せず、地域住民や医療関係機関にも積極的に発信して関係構築に役立てましょう。ここからは、病院広報誌を広報PRで活用するポイントを5つご紹介します。

ポイント1.病院ブランディングの一環として位置づける
病院広報誌によるメリットを発揮するためには、ブランディングの一環として位置づける意識が必要です。単に情報を発信するのではなく「自院にどんなイメージを持ってもらいたいか」を念頭に置き、広報誌のトーンやビジュアルを整えていきましょう。
病院全体としての想いを伝えるには、院長のメッセージや理念を丁寧に発信する構成も大切です。レイアウト作成の段階など構成のバランスによって大幅な変更はあるものの、優先度の高いコンテンツはなるべく省略せずに信頼性・一貫性の維持と向上を意識することが重要となります。
ポイント2.社内広報や採用広報にも展開する
広報誌はおもに院外の生活者や医療関係者に向けて発信するものですが、インナーブランディングにも活用できます。職員紹介や理念紹介のページで院内の現状を可視化することで、「どんな人が働いているか」「どんな想いで働いているか」を発信できるためです。
インナーブランディングに有用なコンテンツを掲載した広報誌は、採用イベントや合同説明会といった場で配布するとよいでしょう。自院のよさを伝えられれば、将来院内スタッフになるかもしれない潜在層の印象形成に役立ちます。
ポイント3.WebやSNSと連携して発信力を高める
病院広報誌の配布場所を自院にとどめるのは、広報PR施策として惜しいところです。院外の関連施設はもちろん、Web・SNSといったオンラインサービスも最大限に有効活用して発信力を高めていきましょう。
オンラインでの発信は読み手との接点を増やしやすいため、地域を問わないコンテンツにおいては特に有用です。プレスリリース配信のほか、電子版を公開したり、広報誌の内容をSNSアカウントで紹介したりすることでさらなる認知拡大を図れます。
ポイント4.病院広報誌の制作サービス活用も検討する
病院広報誌の制作には複数の業務工程が生じるため、制作サービスへ外部委託するのも一案です。取材・原稿・レイアウトなど依頼の幅はさまざまですが、外部委託により人的・時間的なコストの削減につながります。
また、病院広報誌の制作を強みとするサービスであれば、薬機法をはじめとする表記等ルールを熟知しているケースがほとんどです。ガイドラインに遵守しており、トラブルのリスクを低減できるメリットは外部委託に依頼する魅力のひとつといえるでしょう。
ポイント5.病院広報誌はメディアや地域機関との関係構築に使う
病院広報誌は、地域住民への周知だけでなくメディアや地域機関との関係を構築する機会になります。地域の新聞社やフリーペーパーはもちろん、自治体や医師会といった団体・機関に広報誌を配布して継続的な接点を作りましょう。
例えば地域医療や社会課題をテーマにしたコンテンツがあれば、プレスリリースの題材やメディアへの発信素材として再活用できます。メディア関係者の関心を引く内容は報道につながる可能性も高いため、地域にとどまらず積極的に発信していくことが重要です。
病院広報誌で自院の魅力・強みを広く発信しよう
病院の広報誌は、患者をはじめとする地域住民へ情報を発信する手段として非常に有用な広報PR施策です。しかし、届けたい層に届けるためには適切なコンテンツ・企画の設定と、これに応じた掲載内容の熟考が重要となります。
制作コスト削減のために外部へ委託したり、配布先を増やすためにプレスリリース配信を活用したり、「自院らしさ」を届ける選択肢は複数想定できるでしょう。今回ご紹介した制作フローやポイントを参考に、病院の魅力を積極的に発信してみてください。
【監修者のご紹介】
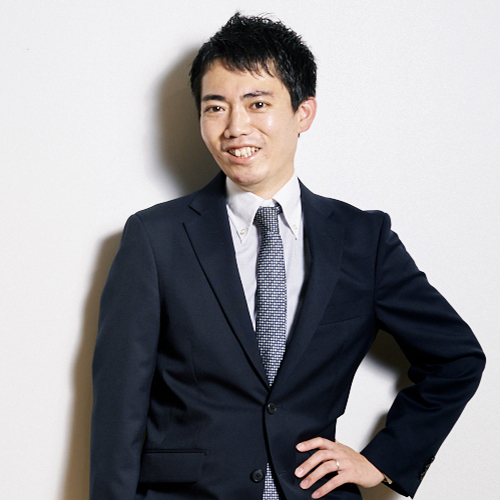
公益財団法人筑波メディカルセンター 総務部 経営企画課 広報係
2009年、近畿日本ツーリスト株式会社に入社。教育旅行分野の添乗・営業を経て、2012年、公益財団法人筑波メディカルセンターへ入職。2015年6月より法人広報部門にて、広報誌の企画編集、動画制作、公式SNSの運営、プレスリリース配信などを担当。2021年に実施したクラウドファンディングでは広報・PR実務を担い、プロダクト完成後に配信したプレスリリースが、株式会社PR TIMES主催のプレスリリースアワード2022「ヒューマン賞」を受賞。2023年10月よりPR TIMES公認プレスリリースエバンジェリストとして活動。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする


