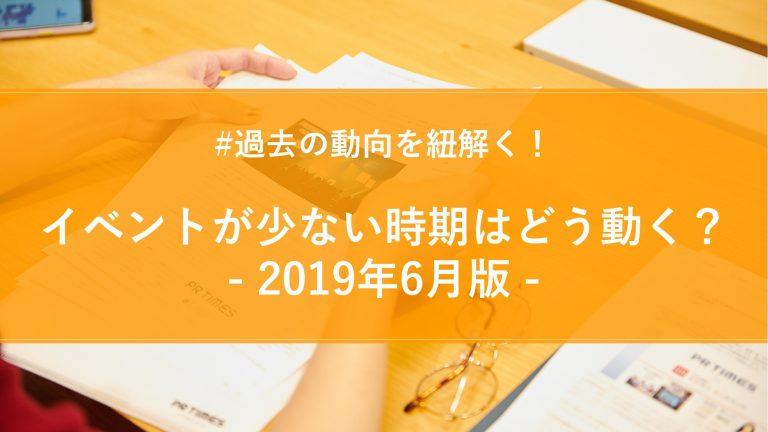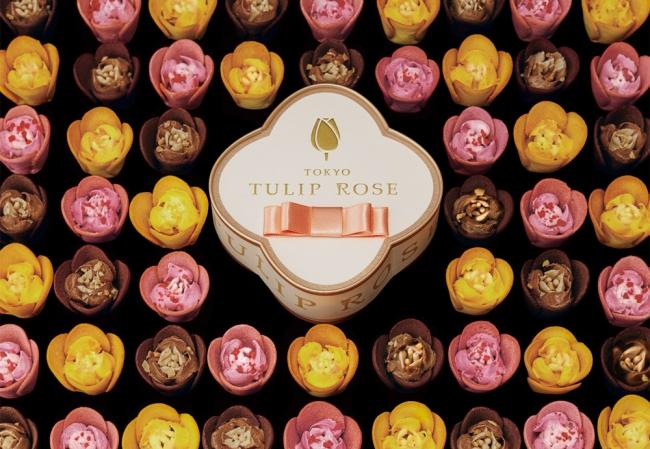論文の発表は、研究者や大学、研究機関にとって成果を社会へ伝える重要な機会です。しかし、専門誌への掲載だけでは、せっかくの研究内容が一部の関係者にしか届かないことも少なくありません。そんなときに有効なのが、研究成果をわかりやすく社会に伝える「プレスリリース」です。近年では、大学や公的研究機関だけでなく、企業の研究部門や個人研究者による論文リリースも増えています。
本記事では、論文発表を効果的に広報するためのプレスリリース作成ポイントをわかりやすく解説します。配信によって得られるメリット、研究成果を正確かつ魅力的に伝えるための工夫、そしてすぐに使えるテンプレートまで、実践的なノウハウを網羅。研究の価値をより多くの人に届けたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
論文発表でプレスリリースを配信するメリット
近年、研究や論文をプレスリリース配信する大学や研究者も増加しています。では、なぜ論文発表でプレスリリースを配信するのでしょうか。
まずは、大学や研究者がプレスリリースを配信する3つのメリットを解説します。
1.研究の意義を広く知ってもらえる
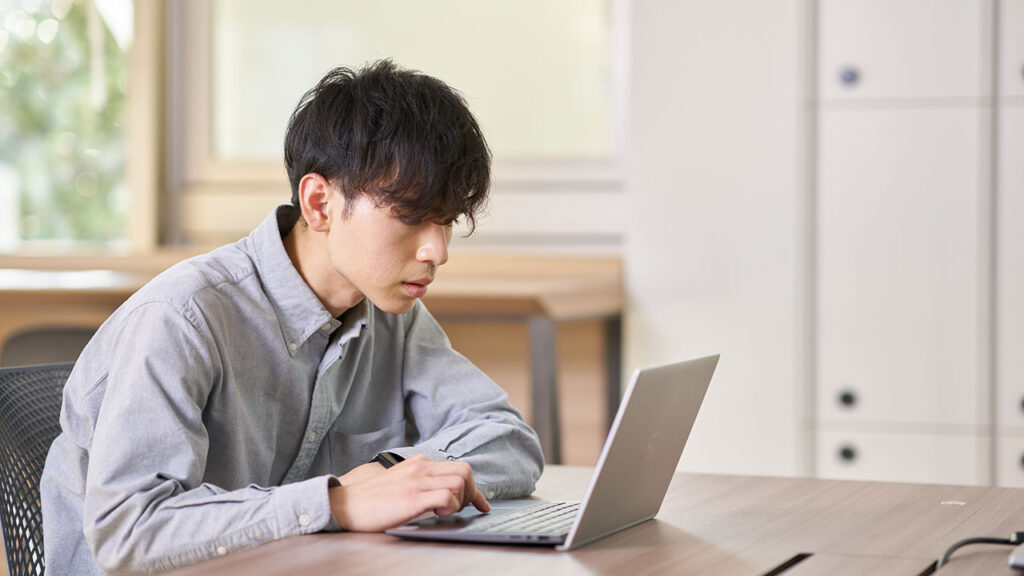
一般的に研究発表や論文発表に目を通すのは、興味を持っている人物や関係者が中心です。クローズドな一面によって、どうしても研究内容や意義を広い範囲に発信できないことが多いのです。
プレスリリースを利用するメリットは、性別・年代・職業などを問わず幅広い読み手がプレスリリースに目を通す可能性が高まること。これまで研究テーマや論文内容に興味を持っていなかった読み手にも、研究意義を知ってもらえるのです。
2.マスメディアや専門誌への露出機会が高まる
プレスリリースを使った論文発表や研究発表の発信は、大学や研究者の知名度アップにも繋がります。
なかでも、新規性や話題性の高い論文の場合は、一般の読み手だけでなくマスコミ関係者や専門誌の編集者に注目される可能性があります。論文のプレスリリースがマスコミ報道や専門誌掲載に繋がり、結果的により多くの人に論文を認知してもらえるのです。
3.専門家・研究者ネットワークに届き、共同研究・開発の機会創出
前述したように、プレスリリースの配信は多くの読み手に情報を発信できること。プレスリリース配信サービスで発信・SNSを使った二次拡散・ニュースサイトへの転載によって、自身の研究発表や論文を一般の読み手だけでなく専門家にも届けられます。
研究発表や論文が専門家の目に留まった場合、共同研究や共同開発の誘いを受ける可能性があります。論文のプレスリリースは、自身のスキルアップに繋がるチャンスを掴むきっかけにもなるのです。
有意義な研究のためには、同じ志を抱いている人物との情報共有が欠かせません。論文を読んだときに「一緒に研究したい」と感じる、未来の仲間からの連絡もあるかもしれませんよ。
配信タイミングとスケジュール管理
論文のプレスリリースでは「いつ配信するか」が成果を左右します。掲載誌の公開日や報道解禁日に合わせて計画的に準備を進めることが重要です。理想的なスケジュールは、「論文受理」→「掲載決定」→「公開・報道解禁」という流れに沿って、少なくとも受理段階で原稿を準備し始めることです。
特に、報道解禁日を設定している学術誌や学会もあるため、配信前に編集部や大学広報と連携を取り、公開時期を調整することが不可欠です。タイミングを逃さず配信できれば、報道各社の注目度も高まり、取り上げられる確率が上がります。
論文受理~公開~報道解禁までの理想スケジュール
論文が受理された段階でプレスリリース案を作成し、掲載日が確定したら広報部署やメディア配信サービスと連携してスケジュールを決めていきましょう。理想は、掲載日または解禁日の前日に配信を行い、当日の報道を狙うことです。
また、英文論文を海外誌に掲載する場合には、時差を考慮して配信時間を設定するのも効果的です。配信後は、アクセス数やメディア掲載状況を分析し、今後の研究発信に活かす体制を整えておくと良いでしょう。
配信後は、記者対応・モニタリング・フォローアップ対応の実施
配信後のフォローも、研究リリースの成功を左右します。メディアからの問い合わせに迅速かつ正確に対応できるよう、研究担当者・広報担当者間で情報共有を徹底しておきましょう。
また、掲載記事をモニタリングして反響を把握することも重要です。報道件数やSNSでの拡散状況を分析し、次回以降のプレスリリース改善につなげます。問い合わせをくれた記者や編集者に対しては、フォローアップを行い、次の取材機会につなげることが信頼関係構築の第一歩になります。
論文発表のためのプレスリリースを作成するときの5つのポイント
熱意を込めて作成した論文をプレスリリースとして配信するのであれば、できるだけ多くの人に目を通してもらいたいもの。プレスリリース作成時には書き方を意識して、読み手の興味を引くリリースを作成しましょう。
次は、大学や研究者がプレスリリースを作成するときの5つのポイントを解説します。

1.論文掲載がわかり次第プレスリリースの配信準備をする
研究発表や論文のプレスリリースは、論文が学術雑誌などにアクセプトされた時点で配信の準備をしましょう。論文公開日のプレスリリース配信が理想的です。公開後になる場合はできる限り早いタイミングでプレスリリースを配信できるように、作成を進めていきましょう。
また、先ほどご紹介したように新規性や話題性のある論文の場合には、プレスリリースの配信以降にマスメディアや専門誌からの取材依頼が届く可能性があります。取材対応を円滑に進めていくためにも、プレスリリースの文末に問い合わせ先を記載しておきましょう。
【問い合わせ先として記載したいこと】
- 担当部署名
- 担当者名
- 電話番号やメールアドレス
- 取材対象者(研究者への直接取材が難しい場合は明記)
2.研究成果が社会にどう役立つかを明記する
マスコミや一般の読み手に少しでも興味を持ってもらうためには、研究成果の新規性や話題性の記載だけでなく、有益性や背景の説明も必要です。自身の論文内容や研究発表に記載されている内容が世間にどう役立つのかを明記しましょう。
【研究成果の有益性を説明すると?】
誤 ○○を××に転換することによって、新たに△△遺伝子が誕生した
正 これまで医療現場で課題とされてきた~~を解消するために、△△遺伝子を生み出した。
上記例は、同じ「△△遺伝子」について発表した一文ですが、後者は研究成果や解決できる課題が明記されています。前者と比較すると、専門知識を持たない一般の読み手にも伝わりやすい後者の方が望ましいでしょう。
3.専門用語は補足や注釈を入れて幅広い年齢層の人が読める文章にする
学内イベントや新たな取り組みの発表だけでなく、研究発表を学外に広く発信するためにプレスリリースを利用することも多いですよね。
発表内容を丁寧かつ詳しく記載することは大切ですが、難しい用語を多用してしまうとかえってわかりづらいプレスリリースになってしまう可能性があるので要注意。難しい用語を使用した場合には、用語の意味を補足しましょう。
4.研究フローを図式化する
研究の流れを可視化するためにも、テキストに加えて図式化された「研究フロー」を付け加えるのも一案です。誰がどの段階から関わっているのかもわかりやすく、研究の流れを時系列で確認できます。
ただし、図式化された研究フローは必ずしもプレスリリースに記載すべき事項ではありません。必要があれば記載するようにしましょう。
5.キーパーソンのプロフィールを記載する
プレスリリース配信サービスでは、毎日数十~数百通のプレスリリースが配信されています。何百通もあるプレスリリースに自身の論文や研究発表を埋もれさせないためにも、論文のキーパーソンとなる人物をプレスリリース内に記載しましょう。
取材できる関係者がいる場合には、複数名記載してもOKです。マスコミや専門誌取材を受けられる人物を明確に伝えるようにしましょう。
論文発表のプレスリリーステンプレート
はじめてプレスリリースを作成するときには、書き方や記載事項が分からず苦労してしまうもの……。テンプレートを利用して、効率的にプレスリリースを作成しましょう。
最後に、論分発表時に活用できるプレスリリースのテンプレートをご紹介します。
研究成果のリリースの場合
報道関係各位
2024年xx月xx日
学校名
《研究成果のうち、もっとも印象的なポイントを端的に説明》
「研究発表、論文名」研究成果の発表
〜 研究から明らかになった動向や結果などを補足〜
学校法人○○(住所)では、(研究を行った背景・研究部署名、研究対象、対象人数を明記)に―――(研究発表名、論文名)を実施しました。研究により、~~~~~(研究成果を明記)が明らかになりました。
【URL】http://
・研究内容
・研究に至った背景(関係する教員や学生も紹介)
・その他、関連する取り組み(あれば記載する)
【研究トピックス(グラフや図を交えて、3つほどのポイントを箇条書きで記載)】
1.
2.
3.
【キーパーソンの紹介】
【学校の概要】
学校名:
所在地:
代表者:
設立:
URL:
本プレスリリースに関するお問い合わせ、取材依頼に関しては下記の窓口にお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
担当者:○○大学 事務部+担当者名
電話番号:000-000-000
メールアドレス:~~~~~@
シンポジウム開催案内やイベントの場合
報道関係各位
2024年○月○日
大学名
〇〇シンポジウム「イベント名」開催のお知らせ
(イベントの特徴を具体的に追記)
学校法人○○(住所)は、―――(シンポジウム名)を、2024年○月○日に開催いたします。ゲストスピーカーとして、本校卒業生で現在はアナウンサーとして活躍する△△さんを迎え、~~ついて来場者とのトークディスカッションを行う予定です。
・イベント情報詳細
・イベント開催の背景
【ゲストのプロフィール(写真と共に経歴を紹介)】
【シンポジウムプログラム】
9:00 受付開始
9:15 シンポジウム開始
9:20 ゲスト△△さん登壇
・
・
・
12:00 シンポジウム終了
【「シンポジウム名」実施概要】
シンポジウム名:
開催日:
会場名:
アクセス:(住所と最寄り駅からの所要時間)
申し込み方法:
本プレスリリースに関するお問い合わせ、取材依頼に関しては下記にお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
担当者:○○大学 事務部+担当者名
電話番号:000-000-000
メールアドレス:~~~~~@
プレスリリースの配信チャネルと英語対応
論文発表リリースの配信先は、学内広報だけでなく、ニュース配信サービス、専門誌、業界メディア、さらには海外メディアまで多岐にわたります。研究テーマに応じて適切なチャネルを選ぶことで、届けたい層に確実に情報を届けられます。
国際誌に掲載された研究であれば、英語版プレスリリースの作成も有効です。英語リリースでは「簡潔さ」と「文化的な表現の違い」に注意し、必要に応じてプロ翻訳者に依頼すると良いでしょう。海外のメディアや研究者からの問い合わせにも対応しやすくなります。
国内メディア・専門誌・学会広報を網羅するチャネル設計
国内の新聞社や通信社、Webメディアへの配信はもちろん、学会や研究機関の広報ネットワークを通じた発信も効果的です。特定の分野に強い媒体(例:医療・化学・AIなど)を事前にリスト化し、ターゲットに合わせて配信を最適化しましょう。
また、大学や研究所のオウンドメディア、SNSアカウントでも二次発信を行うことで、一般層への認知を広げられます。メディア別に配信内容を調整する「チャネル別最適化」を意識することで、反響の質と量の両方を高められます。
英文プレスリリース対応のポイントと留意点
英文リリースでは、「専門用語を過度に翻訳しない」「簡潔で明快な文体を使う」「文化的に誤解を招く表現を避ける」といった点に注意が必要です。
また、海外メディアでは「社会的・グローバルな意義」に重点が置かれるため、研究がどの国・地域に影響を与えるかを明確に記載すると良いでしょう。英語タイトルには、研究の独自性を示すフレーズを入れることで、国際的な注目度をさらに高められます。
大学広報と連携を取りながら、研究成果を広く発表しよう
論文や研究成果を広く発信するためには、プレスリリースの配信は非常に効果的です。読み手を増やす効果だけでなく、専門家からの共同研究の依頼や取材誘致など、さまざまなメリットが期待されています。
取材対応やプレスリリース内容の確認など、すべての作業をひとりでするのは難しいもの。大学広報と上手く連携を取りながら、研究成果を広く発信していきましょう。
<論文発表プレスリリースの配信前チェックリスト>
- 発表内容と掲載誌情報に誤りがないか
- 社会的意義・成果のポイントが冒頭に明示されているか
- 図表・数値・引用元に出典があるか
- 記者対応・問い合わせ先が明確か
- 配信日時・解禁日の設定が適切か
論文発表のプレスリリースを作成する時のポイントに関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする