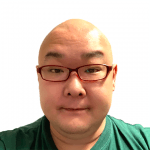情報発信や日々の業務において、私たちは常に誰かと関わり、言葉や行動を通じて多くのメッセージを伝えています。しかしその一方で、無意識のうちに自分の価値観や思い込みが表現に反映され、相手に意図とは異なる印象を与えてしまうこともあります。このような「無自覚な偏り」は「アンコンシャスバイアス(無意識のバイアス)」と呼ばれ、近年、個人や組織の信頼性を左右する大きな要因として注目されています。
発言や行動に悪意がなかったとしても、バイアスが原因で不適切と受け取られたり、誤解を招いたりすると、職場での人間関係やチームの信頼、さらには企業や組織全体の評判に影響を及ぼすリスクもあります。
本記事では、アンコンシャスバイアスの基礎知識に加え、職場で起こり得る具体的な事例を紹介しながら、その悪影響と背景を解説します。さらに、バイアスによる誤解や摩擦を防ぎ、多様性を尊重したコミュニケーションを実現するための6つの対策方法もあわせてご紹介します。
アンコンシャスバイアスとは?
「アンコンシャスバイアス」とは、さまざまな価値観の存在を尊重するなかで非常に大切な概念です。とはいえ、初めてこの言葉を目にする方もいるでしょう。いったいどのような意味で、具体的にはどういったことを指すのでしょうか。
アンコンシャスバイアスの意味
アンコンシャスバイアスとは、本人が自覚していないまま抱いている先入観や偏見が、行動や判断に影響を与えることです。
「アンコンシャスバイアス」を直訳すると「無意識の偏見」となります。私たちは、さまざまな環境や集団に囲まれて生活するうちに、知らず知らずのあいだに個人の意識に価値観や思考の偏りが個人の意識に刷り込まれていきます。この「価値観の偏り」がアンコンシャスバイアスです。
人の価値観は大なり小なり、他者や環境からの影響を受けて培われるものです。それは、かけがえのない個性を生み出す一方で、摩擦を生み出すきっかけとなります。
昨今、企業や組織などの広報を発端とする炎上騒ぎの多くは、この「アンコンシャスバイアス」を起因とするものが少なくありません。たとえ、考えそのものを直接的に表明するものではなくても、偏った考えのもとに発せられたメッセージは、それを受け取る人々を傷つけてしまう可能性があります。公的なメッセージである広報においては、アンコンシャスバイアスについて十分に理解しておかなければなりません。
アンコンシャスバイアスの具体的な事例
アンコンシャスバイアスの身近な例には以下のような考え方があります。
- 赤いランドセルは女の子用、黒いランドセルは男の子用
- 血液型がAB型の人は、変わった性格の持ち主
- 雑用は新入社員の仕事
- 育児中の女性社員に営業の仕事は任せられない
- 一定の学歴を経ていない人は知的な能力に乏しい
また「性別や年齢、職種、職域によって接し方を変える」ということも、アンコンシャスバイアスにあたります。
生まれつき持った身体的な特徴は、その人本来の性別や性格を決めることには必ずしもつながりませんし、出自がその人の優劣を直接的に決定づけることはありません。ましてや、それに基づく振る舞いを一方的な価値観のもとに決めつけることは正しくありません。ある人にとっての「常識」は、そうでない人にとって「非常識」であると認識することが大切です。
アンコンシャスバイアスが注目される理由
近年、企業や組織において「多様性(ダイバーシティ)」や「公平性(エクイティ)」の重要性が急速に高まり、年齢・性別・国籍・価値観などが異なる人々が共に働く環境が一般的になってきました。こうした環境のなかで、誰もが働きやすく、能力を発揮できる組織を実現するためには、無意識に他者の可能性や信頼を狭めてしまう「アンコンシャスバイアス」の存在を正しく理解し、適切に対処することが欠かせません。
特に、採用や評価、マネジメント、日常のコミュニケーションといったあらゆる場面で、バイアスによる不公平な判断や対応が問題視されるケースが増えており、そのリスクを回避するために、組織全体で意識を高める動きが広がっています。アンコンシャスバイアスは誰にでも存在し得るものであるからこそ、それを「自覚する力」が個人にも組織にも求められているのです。
関連用語との違い:ステレオタイプや偏見との違い
「アンコンシャスバイアス」は、似た言葉である「ステレオタイプ」や「偏見」と混同されることがありますが、それぞれ意味には明確な違いがあります。
ステレオタイプとは、ある集団や属性に対して抱く固定的なイメージや一般化された印象のことを指します。たとえば「男性は論理的」「若い人は経験が浅い」といったような一括りの見方が該当します。これ自体は必ずしも否定的な感情を含まない場合もありますが、個人を正しく評価する妨げになり得ます。
一方、偏見は、根拠が不十分なまま他者や集団に対して否定的・敵対的な感情や態度を持つことを指し、差別につながるリスクも高い言動です。
アンコンシャスバイアスは、こうした固定観念や感情的な評価が「無意識のうちに」行動や判断に影響を与える点が特徴です。本人に悪意や自覚がなくても、結果的に他者の機会を不当に制限したり、不公平な扱いにつながることがあるため、より慎重な対処が求められています。
アンコンシャスバイアスが職場や組織にもたらす悪影響とは?
アンコンシャスバイアスはコミュニケーションの価値を大きく損なうだけでなく、関わる人々同士の信頼関係をお互いに大きく低下させ、正しい関係の構築を妨げるもととなります。
アンコンシャスバイアスが組織にもたらす悪影響を確認しておきましょう。

個人に対する影響
偏った価値観をもって相手に接することは、お互いのコミュニケーションや、言葉の認識に埋められない溝を生むことにつながります。
仕事へのモチベーションが下がるだけでなく、「どうせ言っても無駄だ」「自分はここに居場所がないのではないか」といった不信感やストレスが生まれやすくなります。
さらに、その感情が蓄積されると、上司や同僚との関係性にも影を落とし、信頼関係が崩れ、パフォーマンスの低下や離職意向の高まりといった形で表面化していきます。
組織に対する影響
組織全体に目を向けると、アンコンシャスバイアスは評価や登用の公平性を損ない、意思決定の質を低下させる要因となります。特定の属性や価値観を前提とした判断が続くことで、多様な視点や異なる意見が排除され、結果としてリスクの見落としやイノベーションの停滞を招きやすくなります。
また、個人の何気ない振る舞いがきっかけであっても、それが是正されないまま放置されると、「この組織は偏った考え方を許容している」という印象が内外に広がります。これは採用活動や顧客からの信頼、さらにはブランドイメージの毀損にも直結する問題です。
組織としては、特定の誰かを責めるのではなく、日常の判断や会話の中に偏りが入り込んでいないかを点検し合い、互いに気づきを共有できる習慣や仕組みを持つことが、長期的な信頼と健全な文化を守るうえで不可欠だといえます。
アンコンシャスバイアスの代表的な例
アンコンシャスバイアスに対して、具体的にどのような考え、行動に気をつけていくべきなのでしょうか。
次に、アンコンシャスバイアスにつながる代表的な心理バイアスの例を7つ挙げて説明します。
どれも特別なものではなく、日常生活で思い当たることの多いものです。広報活動を行う際、また広報としてメッセージを発する際、これらにあたる考えをしていないか、そう受け取られてしまう可能性のある表現を用いていないか、つねに照らし合わせる習慣をつけていきましょう。
正常性バイアス
正常性バイアスとは、事態が悪化しても「まだ大丈夫」と楽観的に考え、適切な判断を見失うことを指します。
具体的には、大きな災害が起きても「そのうち収まるだろう」と考えて避難のタイミングを逃したり、大きなトラブルの発生を予感しながらも「以前もなんとかなったから、今回も大丈夫だろう」と考え、未然に防ぐ対策が取られないまま問題が顕在化するというものです。いわゆる「性善説」が悪い方へ作用したものともいえます。
ハロー効果
ハロー効果とは、好感を抱いた人物の考えや行動を、疑うことなくすべて肯定してしまうことを指します。
好感を抱いた人の行いを肯定することは自分自身を肯定する気持ちにもつながりやすく、たとえ違和感を抱いたとしても「この人が言うならば間違いない」「この人を疑うのは間違っている」という気持ちで、違和感を押し留めてしまいがちです。その結果、思考が相手に大きく依存し、主体的な判断ができなくなってしまいます。
ハロー効果を回避するためには、「この人がどのような背景を持ち、どのような立場にあるのか」「どのような意図をもってメッセージを発しているのか」「その行動を通じて、何を達成しようとしているのか」といった洞察の気持ちを持って向き合うことが大切です。
確証バイアス
確証バイアスとは、自分の信じる考えを補強する材料ばかり集めてしまい、客観的な視点を欠いていくことを指します。
たとえば、「Aという考えが優れている」という論説に対して、「Aにはこのような問題点がある」「Bという考えも存在する」といった反証材料に目を背け、「Aをよいという人がこれだけいる」「著名人もAという考えだ」という都合のよい材料ばかりを取り入れることで、考えの偏りはますます強まってしまいます。
確証バイアスを回避するためには、正反対の論証を意識的にあたり、自らが確かめようとする考えと同じ以上の否定材料に触れ、考えのバランスを中立に保ったうえで、客観的に見て有効だと思われる情報を取捨選択し、判断していくことが大切です。
ステレオタイプバイアス
ステレオタイプバイアスとは、「男性は強くて決定権がある」「女性は弱くて知識に乏しい」など、特定の性別や属性、職業などに対する偏ったイメージ(ステレオタイプ)にもとづいた決めつけを行うことを指します。
「AといえばBなのだから、AはBだ」という考えは、相手の存在を認めないばかりでなく、「AといえばBでなければならない」と、自分自身の考えをも大きく縛り付けていくことになります。
ステレオタイプバイアスを回避するためには、「そうではない場合」にも意識的に目を向け、必ずしもひとつの価値観だけでは判断できないケースがあることを念頭に置くことが大切です。「自分にとっての常識は、ほかの人にとっては非常識である可能性がある」ということを常に考えるようにしましょう。
権威バイアス
権威バイアスとは、上司や組織の長、特定の肩書を持つ人の意見はつねに正しいと思い込むことを指します。
「有名なこの人が言っているのだから、間違いない」といった考えにはじまり、特に組織においては「社長が言うことなのだから、間違っているはずがない」「この組織でこれだけの地位の人なのだから、きっとその通りだ」と、ついつい考えがちです。
権威バイアスを回避するためには、価値観や物事の前提はつねに変化しており、同様に、同じ人物でも考え方がよくも悪くも「変化していく」ものだという考えが欠かせません。特に価値観の変化が加速し続けている現代においては、長年にわたって支持されてきた権威が、ものの数日、数ヵ月でガラリと変化することも決して珍しくありません。常に考え方をアップデートする必要があるといえるでしょう。
集団同調性バイアス
集団同調性バイアスとは、所属する集団のなかに存在する価値観や行動に、個人としても影響されてしまうことを指します。
具体的には、「社長がそういうのなら、そうなのだろう。違う考えを抱くことは、自分が間違っているからだ」と、組織の考えと自らの考えを鏡写しにしてしまう例が挙げられます。集団同調性バイアスにかかる要因には、感情的な要素も少なからずあり、対抗する考えや存在に対して、ついつい客観性を欠いた衝動的な行動にも出てしまいがちです。
組織にとっては「常識」でも、その外では必ずしもそうとは限りません。集団同調性バイアスを回避するためには、組織や集団の考えに対して反証的な視点を意識的に設定し、「その考えに対して否定的な立場から見た場合、どのように感じるか」という考えのものもと、メッセージを検証していくことが大切です。
アインシュテルング効果
アインシュテルング(ドイツ語で「心構え」)効果とは、これまでの考えに固執し、新たな考えを受け入れないことを指します。
年長者が「若い人は何もわかっていない」と頭ごなしに否定したり、「営業部署の人間は開発部署の人間の都合を何も考えていない」といった組織間の対立などにも見受けられます。
背景の理解なしに相手を一方的に否定することは、自らの不安を一時的に遠ざけることができたとしても、物事の本質的な解決にはつながりません。
アインシュテルング効果を回避するためには、目の前の相手に対して、ひとりの人間としてきちんと向き合い、「なぜこのような考えを持つのか」「その考えは、相手のどのような背景から構成されているのか」、そして「相手にとって、もっとも大切としていることは何か」をきちんと見極め、受け入れる姿勢が大切です。
職場で起きやすい場面別のアンコンシャスバイアス事例
採用から発信まで、アンコンシャスバイアスは「個人の性格」ではなく「判断の場面」に入り込みやすいのが特徴です。特に職場では、短時間で結論を出す必要がある場面や、暗黙の前提が共有されている場面ほど、過去の経験や固定観念に頼った判断が起きやすくなります。
次に、広報PR担当者・人事・マネジメント層が、現場で起きやすい典型例を「場面別」に整理し、どこでズレが生まれやすいのかを具体的に確認できるようにします。自社の制度や会話に置き換えながら読むことで、見直すべきポイントが見つかりやすくなります。
採用・面接で起きる例
採用・面接は、限られた情報で候補者を評価するため、アンコンシャスバイアスがもっとも混入しやすい領域です。特に「違和感」「合いそう / 合わなさそう」といった直感は、合理的判断に見えても過去の成功体験や、既存メンバー像への同一化が影響していることが少なくありません。
結果として、能力よりも「似ているかどうか」で選抜が進むと、多様な視点が入りにくくなり、組織の学習力や意思決定の質にも長期的な影響が出ます。採用広報の発信内容や選考基準の言語化も含め、入口の設計が組織の公平性を左右します。
「カルチャーフィット」を理由に同質性を強める
「カルチャーフィット」は本来、価値観や働き方のすり合わせを行うための概念ですが、運用を誤ると「自社に似た人だけを採る」合言葉になりがちです。たとえば「ノリが合う」「空気が読める」「うちっぽい」など、定義が曖昧なまま判断材料にすると、既存メンバーの属性やコミュニケーション様式に近い候補者が有利になり、多様性が削られます。
また、異なるバックグラウンドの人材が入ったときに生じる摩擦を「合わなかった」と片づけると、組織側の受け入れ設計の課題が見えなくなります。カルチャーは固定物ではなく育てるものだと捉え、評価軸を「価値観の一致」ではなく「行動原則への共感」「学習姿勢」「対話のスタイル」など観察可能な項目に落とすことが重要です。
話し方・外見・出身で能力を推測してしまう
面接では「受け答えが上手い」「話が流暢」「見た目が整っている」といった印象が、能力評価に過剰に影響することがあります。これはハロー効果や確証バイアスと結びつきやすく、たとえば緊張しやすい人や、言語・文化的背景が異なる人、自己表現のスタイルが控えめな人が不利になりやすい構図を生みます。
また、特定の学校名や前職企業名に引っ張られ、スキルの実態確認が甘くなるケースも起こり得ます。採用の公平性を高めるには、会話の印象ではなく、職務に必要な要件を分解して質問設計を行い、評価表を用いて「どの回答がどの能力に紐づくか」を面接官間で揃えることが有効です。
評価・昇進・配属で起きる例
評価・昇進・配属は、個人の将来機会を左右するため、アンコンシャスバイアスの影響がもっとも高コスト化しやすい場面です。ここでの偏りは、当人の納得感を損ねるだけでなく、組織内の信頼や心理的安全性を下げ、離職やモチベーション低下にも直結します。
特に評価制度が整っていても、運用の会話や推薦の仕方に曖昧さが残ると、暗黙の期待役割や「伸びしろ」判断が入り込みやすくなります。広報PR担当者にとっても、人的資本開示や採用ブランディングの観点で「公平な評価・育成ができているか」は対外メッセージの信頼性に結びつくため、見過ごせない論点です。
経験を積める人が固定化することによるチャレンジ機会の偏り
「重要案件は安心できる人に任せたい」という判断は自然に見えますが、積み重なると特定の人だけが経験を得て、さらに任せられるという循環が生まれます。たとえば、育児や介護などの事情がある人に対して「負荷が高いから外そう」と配慮したつもりが、本人の希望確認なしに機会剥奪になっているケースも少なくありません。
結果として、経験の差が評価の差として固定化され、「やらせてもらえない→実績が作れない→評価されない」という不公平が生じます。
機会の偏りを減らすには、本人の意思確認を前提に、難易度の異なる案件を段階的に配分する仕組みや、サポート体制をセットで設計し、挑戦の入口を広げる運用が欠かせません。
成果より「期待役割」で評価が揺れる
評価面談で「頼りになる」「リーダーっぽい」「調整が上手い」といった言語が並ぶ一方、成果の定義や貢献の中身が曖昧なまま評価が決まると、期待役割に合致する人が有利になりやすくなります。
たとえば、発言が多い人や自己主張が強い人が過大評価され、裏方の貢献やチームの成功に不可欠な仕事が評価に反映されにくい構図が生まれます。
また、性別や年齢による「こうあるべき」像が混入すると、同じ行動でも「積極的」と「生意気」「慎重」と「消極的」のように解釈が割れることも。評価の納得感を高めるには、成果指標と行動指標を分け、評価理由を具体事実に紐づけて言語化し、複数評価者でバランスを取る運用が有効です。
会議・日常コミュニケーションで起きる例
会議や日常のやり取りは、制度よりも「空気」が判断を支配しやすく、アンコンシャスバイアスがもっとも見えにくい形で蓄積します。本人に悪意がなくても、発言の扱われ方や、会話の主導権の偏りは、心理的安全性や参加感を左右し、組織の学習力を低下させます。
特定の人が話す前提の会議は、異論やリスク指摘が出にくく、意思決定の質にも影響しがちです。広報PRの観点でも、社内の対話文化は発信の一貫性や危機対応の初動速度に関わるため、コミュニケーションの偏りは「内部の課題」で終わりません。
発言量の偏り(遮り、言い換え、手柄の横取りに見える構図)
会議で一部のメンバーが発言を占めたり、誰かの発言が遮られたり、別の人が言い換えて「自分のアイデア」として扱われると、当事者は発言意欲を失いやすくなります。特に「意図せず遮る」「まとめ直しただけ」のつもりでも、受け手には手柄の横取りや軽視として伝わることがあります。
また、声の大きい意見が「正しい」と見なされると、慎重な意見や少数派の指摘が埋もれ、組織としてのリスク感度が落ちることも。対策としては、発言順の設計、ファシリテーターの介入ルール、議事録での発言者明記、アイデアの帰属を丁寧に扱う運用など、会議の設計で偏りを抑えることが現実的です。
冗談のつもりが排除になる
「冗談」「いじり」「軽いノリ」は、内輪では親しみの表現でも、受け手の背景や立場によっては排除や嘲笑に感じられます。特に「普通はこうだよね」「みんなそうしてる」といった言い回しは、暗黙の基準に合わせられない人を周縁化し、発言しづらい空気を作ります。
また、指摘された側が「そんなつもりじゃない」で終わらせると、意図と影響のズレが放置され、関係修復が難しくなるケースも。職場で重要なのは、ユーモアを全面否定することではなく、誰かを前提から外す表現になっていないかを点検し、指摘が出たときに受け止めて調整できる対話の作法を持つことです。
広報・発信で起きる例
広報・発信は、アンコンシャスバイアスが「組織の公式見解」として受け取られるため、影響が社外に拡張しやすい領域です。文章やビジュアルは、受け手の多様な前提の上で解釈され、意図しない傷つきや反発を生むことがあります。
特に採用広報、周年発信、CSR/DEI関連のメッセージは、期待値が高い分だけ整合性への目も厳しくなります。広報PR担当者は、表現だけでなく、発信の背景にある意思決定や事実の整合性まで含めて「説明可能性」を担保することが求められます。
前提が特定層に寄る(家族像、働き方、性別役割の固定化)
採用ページや社内紹介記事で「理想の社員像」や「働き方」を描く際、無意識に特定の家族像や生活前提に寄ることがあります。たとえば「育児は母親が中心」「長時間働けることが前提」「飲み会や部活的活動が当たり前」といったメッセージが混ざると、読者は自分が前提から外れていると感じ、応募やエンゲージメントに影響します。
さらに、写真や事例の登場人物が特定属性に偏ると、意図せず「この会社はこういう人向け」というシグナルになります。発信では、誰を標準として置いているかを点検し、複数の生活前提が共存できる表現と事例設計にすることが重要です。
「良かれと思った」表現が当事者を傷つける
善意の表現ほど、ズレが起きたときに修正が難しくなる場合があります。たとえば、障害・病気・ジェンダー・国籍などに関する表現で、励ましや称賛のつもりが「当事者を特別視する」「差を強調する」受け取られ方をすることがあります。また、社会課題への取り組みを語る際に、実態が伴っていないと「ポーズ」「利用」と見なされ、信頼を大きく損ねるケースも。
広報では、意図の説明だけでなく、当事者にとっての影響を想像し、用語選定・ストーリーの立て方・根拠となる事実を揃えることが欠かせません。指摘が出た際は、防御ではなく事実確認と対話を優先し、必要なら速やかに訂正・補足を行う姿勢が、結果としてブランドの信頼を守ります。
アンコンシャスバイアスを生み出してしまう要因とは?
アンコンシャスバイアスは、特定の個人に限らず誰にでも生じ得るものであり、その背景には私たちの思考や情報の受け取り方に深く関係する要因があります。
脳の省エネ思考と過去の経験による自動判断
人間の脳は膨大な情報を効率的に処理するために、過去の経験や既存の知識をもとに素早く判断する「省エネモード」を備えています。これにより、「前にこうだったから、今回も同じだろう」と無意識に結論を出してしまうことがあるのです。こうした直感的な判断はときに有用ですが、誤解や不公正な扱いにつながるリスクもあります。
社会的・文化的背景からくる価値観の刷り込み
育ってきた家庭環境や地域社会、所属する集団の価値観は、知らず知らずのうちに私たちの物の見方に影響を与えています。たとえば、「女性は家庭を優先すべき」「上司は年上であるべき」といった価値観は、個々の選択を狭めるアンコンシャスバイアスとして現れる可能性があります。
メディアや教育による間接的な影響
テレビや映画、ニュース、教科書などを通じて繰り返し目にするイメージや物語も、私たちの認知に大きな影響を与えています。特定の職業に就いている人の性別や、成功者の人物像などが偏って描かれることで、それが「普通」として刷り込まれ、無意識の前提として定着してしまうことがあります。こうした間接的な影響も、バイアスの形成に大きく寄与しています。
行き過ぎた自己防衛による思考の偏り
ときに人は、自分と異なる意見や価値観に触れたとき、それを「自分自身が否定された」と感じてしまい、防衛的な反応として相手の意見を退けたり、自分の考えに固執したりすることがあります。
これは一種の無意識的な自己防衛であり、アンコンシャスバイアスを強める要因となります。このような思考の偏りを防ぐためには、異なる価値観や否定的な意見が存在することを前提に受け止め、自分の人格とは切り離して考える姿勢が重要です。
「偏りに気づき、認識する」ことが、アンコンシャスバイアスを乗り越える第一歩となります。

職場でアンコンシャスバイアスを防ぐ・改善する6つの対策方法
アンコンシャスバイアスを改善するためには、自分の無意識の偏見に気づき、行動や考え方を意識的に見直すことが重要です。最後にアンコンシャスバイアスを防ぐ6つの対策方法について紹介します。
1.対抗意見にも目を配り、自分の判断が偏っていないかチェックする
アンコンシャスバイアスを防ぐ前提としてもっとも大切なのは、「自分の考えは偏っているのではないか」という視点を持つことです。不必要に自分の考えやメッセージを否定しすぎる必要はありませんが、それでも「誰かを傷つけてしまう可能性を持っていないだろうか」と、相手の立場にたった検証は欠かせません。
考えのバランスを取るために有効なのは、自分の考えと正反対ものや、批判的な視点を持つ意見に目を配ることです。全部とは限りませんが、批判的な意見の多くは、自分がこれまで気が付かなかった考えや視点の存在を示唆する貴重な材料となります。
「まったくことなる立場から見たとき、自分の判断はどう見えるだろうか」という考えのもと、微調整を繰り返していくことで、自分の判断の偏りを最小限に抑えることができ、それを受け取ってもらえる相手の数を増やしていくことができます。
2.肩書のみを信頼の担保とせず、客観的な立場からの視点を意識する
組織や集団の長であったとしても、その判断がつねに正しい方向性を指しているとは限りません。特定分野の専門家や、その経験者を名乗る人であっても同様です。肩書はあくまで対外的な役割や立ち位置を示すものであり、その人物の人格や考えの確実性を絶対的に保証するものではないという点に注意する必要があります。
社会や人の価値観は常に変化しつづけています。数年前にはあたりまえとされてきたことが、現在は通用しないという場合も少なくありませんし、同じ人物の考えも、時間や状況によって変化していきます。「この肩書の人が言うのだから間違いないだろう」という考えからは脱却し、反証材料や批判的な意見にも目を通しながら、客観的な立場からの視点を意識することが大切です。
3.多様な考えの存在を認め、常にひとつ以上の角度から物事を見る
人の数だけ、さまざまな考え方が存在します。自分を含め、ある人々にとって「常識」とされることは、ほかの人々にとって「非常識」かもしれません。「AはBであるべき」「CといえばD」といった、特定の考え方を前提とするメッセージは、多くの場合において反発を生み出すもととなります。円滑なコミュニケーションにおいて大切なのは、「世の中には多様な考えがある」という考えです。
不必要に自分の考えを抑圧する必要はありませんが、「このメッセージを、ほかの立場の人々はどう受け取るだろうか」という考えを念頭に置くことは必要です。公にメッセージを発信する場合は、自分のなかに「他者」を存在させ、常にひとつ以上の角度から物事を見ることを心がけていきましょう。
4.組織や集団とは関係のない立場からの視点を持っておく
組織や集団に所属していると、個人の考えも組織に強く影響を受け、同一化してしまうことが少なくありません。特に組織や集団を代表する広報という立場においては、その傾向がさらに強くなるでしょう。しかしながら前にも挙げた通り、自分たちにとっての「常識」が、外の人々に対しても同じものだとは限りません。
外に向けたメッセージでは、無数の異なる価値観のもとにメッセージが見られることを意識する必要があります。組織や集団の考えをいったんリセットしてフラットな視点を持ち、まったく組織と無関係な立場から見た際に引っかかる表現がないか、自分たちのメッセージが、ある価値観や属性の人々を否定し、傷つけていないか、つねにチェックを繰り返す姿勢が大切です。
5.自分と異なる価値観を否定せず、その背景を考える
自分と異なる価値観を目にしたとき、場合によっては不快感を感じることもあるでしょう。しかし、異なる意見を頭ごなしに否定するだけでは、自分の不安から一時的に逃れることこそできても、本当の意味で問題の解決にはつながりません。
自分にとっての「常識」が他者にとっての「非常識」である場合があるように、自分にとっての「非常識」が、他者にとっては「常識」とされることも少なくなりません。人の価値観は突然に生まれるものではなく、そこに至るまでに、必ず何かしらの背景が存在するのです。
私たちがとるべき行動は、価値観や属性などによって目の前の相手を決めつけることではありません。相手がなぜその価値観に至ったのか、そこにはどのような背景があるのかを洞察し、しっかりと受け入れたうえで行動することが、お互いの信頼へとつながります。
6.研修やトレーニングを受ける
アンコンシャスバイアスを改善するためには、専門的な研修やトレーニングを受けることが効果的です。外部の専門家を招いたセミナーやワークショップを通じて、自分の偏見を客観的に認識する機会を得ることができます。特に、ロールプレイや具体的な事例を用いたトレーニングは、バイアスが実際にどのような影響を及ぼすかを理解するうえで有用です。
また、こうした研修は、個人だけでなくチーム全体や組織レベルでの意識向上にも役立ちます。定期的に研修を実施することで、職場の誰もがアンコンシャスバイアスについての理解を深め、共通の課題として取り組む文化を築くことが可能です。学んだ内容を日常業務に活かすことで、職場全体のコミュニケーションや意思決定の質が向上します。
アンコンシャスバイアスを防ぐためには「そうではない人もいる」という視点を持つことが大事
私たちは日々、さまざまな人と関わり、情報を発信したり、意見を共有したりしながら生活しています。その中で重要なのは、「自分にとって当たり前のことが、他の人にとっても同じとは限らない」という視点を持つことです。
アンコンシャスバイアスに対処する第一歩は、「ある人にとってポジティブなことが、別の人にはネガティブに受け取られる可能性がある」と認識すること。そのうえで、「この情報や行動は、別の立場の人にどう映るだろうか?」「この言い方で誰かを傷つけることはないか?」と立ち止まって考える姿勢が欠かせません。
多様な価値観を尊重する社会を築くためには、個人の意識レベルでもバイアスを減らす努力が必要です。他者の視点に立って見直す習慣を持つことで、より良い関係性と公平な環境づくりにつながっていきます。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
アンコンシャスバイアスに関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする