会社の経営や人事を左右する意思決定の場である、株主総会。ステークホルダーが一堂に会するなど、企業にとっては「一大イベント」と言っても過言ではない場です。本記事では、株主総会の開催に際して必要な広報の仕事を5つのポイントで解説します。
そもそも株主総会とは?
経営の意思決定のために株主をはじめとするステークホルダーが一堂に会する株主総会。ニュースなどでもよく耳にしますが、そもそも誰が何を実施しているのでしょうか。株主総会を理解する上で欠かせない3つの基本情報を解説します。
定時株主総会・臨時株主総会の2種類ある
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会の2種類があります。それぞれの違いは、実施が義務かどうかと、実施のタイミングです。
【2つの株主総会の違い】
- 定時株主総会:会社法で定められた、必ず実施すべき総会。毎事業年度の終了後、一定の時期に招集される。
- 臨時株主総会:任意で実施される総会。タイミングを問わず、必要に応じて招集される。
また、次に説明する通り、それぞれの株主総会で行うことや決定することには大きな違いはありません。
株主総会で行うこと・決定すること
株主総会とは、株式会社の「最高意思決定機関」です。主に以下の3点を決定します。後述する通り、株式会社に対して株主権を保持している株主とともに、経営の行く先を決定する重要な場です。
【株主総会における決定事項】
- 会社の根本に関わる事項:定款の変更、事業譲渡、組織再編行為など
- 会社の役員の人事に関する事項:役員の選任や解任
- 株主の利害に大きく影響を与える事項:剰余金の配当に関する事柄、役員の報酬など
また、株主総会の決議の種類には「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の3種類があります。上記の決定事項によって採られる決議とその要件が異なります。
【株主総会の決議と決議要件】
- 普通決議:出席株主の議決権の過半数
- 特別決議:出席株主の議決権の3分の2以上(※)
3-1. 特殊決議-a:①頭数 > 株主総会で議決権を行使できる株主の半数以上(※)/②議決権 > 株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上(※)
3-2. 特殊決議-b:①頭数 > 総株主の半数以上(※)/②議決権 > 総株主の議決権の4分の3以上(※)。
※定款に別段の定めがある場合を除く
参考:http://www.bizup.jp/solution_h/stockholders/01/01_05.html
株主総会に参加する人
株主総会を構成するのは、株主です。株主は株式会社に対して「株主権」という権利を持っており、これを根拠に株主総会に参加できます。「株主権」は「自益権」と「共益権」の2項からなる権利で、いわば「会社の所有者」として間接的に株式会社の経営に携わる権利です。なお、前述の「決議権」は「共益権」に含まれます。
【株主権の詳細】
- 自益権:株式会社から経済的な利益を受ける権利
- 共益権:株式会社の重要な意思決定に参加したり、経営を監督・是正したりできる権利
株主総会を行う時期
多くの企業が例年6月末に株式総会を実施します。これは、企業の決算後3ヶ月以内に株主総会を実施するよう会社法に定められているからです(※)。日本では3月末に決算を行う企業が多いため、6月末に株主総会が集中するのです。

※正確には「基準日から3箇月以内に行使するものに限る」と記されているものの、一般的には決算日=事業年度末日であり、かつ、定款の中で株主総会における権利の行使者の基準日を「事業年度の末日」と定めていることが多いことから、決算日から3ヶ月以内に開催しなければならないと解釈できます。
参考:https://houmu-bu.com/convene-shareholders-generalmeeting-1687
株主総会の開催に向けて会社が決めること
株主総会は役員や株主を中心として経営の重要事項を決定する場ですから、当然入念な準備が必要です。株主総会の実施に向けて会社が予め決めておくべきことを4つご紹介します。
1.議題
議題なしに株主総会を実施することは出来ません。議題がそのまま株主総会の実施目的となるのです。
議題は多岐に渡るものの、前述の通り主に以下の3つに分類できます。剰余金の配当についてや定款の変更、決算報告書の承認、取締役会の選任、役員報酬の改訂など、経営に関わる事項と株主の利害に関わる事項がそれぞれ株主総会の議題となります。これらの議題をあらかじめ提示しておくことで、株主が自らの決議権をもってどのように経営判断を実施するか事前に検討できます。
- 会社の根本に関わる事項
- 会社の役員の人事に関する事項
- 株主の利害に大きく影響を与える事項
2.決算数値
株主総会では決算に関する数値の報告を行うので、参加者に向けたプレゼンテーションの準備が必要です。
数値やその他データに誤りがないよう、正誤を管理しながら社内の情報を収集することはもちろん最重要事項ですね。また、参加者にとって分かりやすく情報を共有する必要があるため、プレゼンテーションのトーン&マナーや体裁をしっかりと整えておくことも大切です。
3.株主からの想定FAQ
株主総会には、株主から経営陣に向けた質疑応答の時間が用意されています。当日、スムーズかつ正確に応答できるよう、想定される質問と回答を予めドキュメント化しておきましょう。また、それらについて事前に経営陣とコンセンサスを取っておくことも忘れないようにしましょう。
4.その他のコンテンツ決め
近年では、株主総会を「ステークホルダーとのコミュニケーションの場」として活用する企業も増えています。自社製品に触れる場を設けたり、イメージキャラクターを務める著名人のトークショーを取り入れたりするなど、各社とも工夫して「ただの報告会」に終始しないコンテンツを編み出しているのです。

例えば、株式会社ほぼ日の「株主ミーティング」。講演や特別授業、年表の展示、試食コーナー、フォトスポット、ポップアップストアの出店など、ほぼ日らしさを存分に散りばめた株主総会を実施しています。
メインの議題と照らし合わせながら、株主の満足度をアップできる+αのコンテンツを検討できると良いですね。
株主総会開催に向けて広報が関与すること
全社を上げて開催する株主総会に際して、一見すると広報担当者の仕事はあまり多くないようにも思えます。しかし、実は広報としてスキルやバリューを発揮できる仕事はもちろんあるのです。ここでは、5つの仕事を解説します。
1.招集通知の作成
株主総会を実施する際は、招集通知を出す必要があります。
招集通知の発送期限は、株主総会の開催日の2週間前(※)。株主に出席と準備の機会を提供するために、期限が定められています。ただし、議題に対して議決権を行使できる株主全員の同意がある場合は、招集の手続きを省略したり、発送期限を短縮したりすることができます。
※株式譲渡制限がない会社の場合は開催日の2週間前。譲渡制限がある会社の場合は1週間前。
2.会場の準備
会社の規模や株主の人数によってまちまちですが、多い場合では数百人〜数千人の株主が株主総会に参加します。そのため、会場の選定や準備が非常に重要です。
参加予定の株主の人数や当日の議題やコンテンツをもとに、必要なキャパシティと設備を洗い出して早めに会場を押さえておけると良いですね。
3.当日のオペレーション整備
多くの人が集まる株主総会ですから、当日は参加者数に見合った人手も必要です。会場内の案内パネルや受付などの人員配置、司会進行役のアサインなど、株主総会がスムーズに進行できるよう細かな配慮も忘れずにオペレーションを設計しましょう。

4.株主の導線確認
前述の通り、株主総会の当日には非常に多くの株主がひとつの会場に集まります。どんなに大きな会場でも混乱が生じる可能性があるので、事故やトラブルを防ぐためにも、導線は丁寧にシミュレーションしておく必要があります。会場に到着してから帰路につくまでの参加者の全てのアクションや導線を確認しておきましょう。
5.株主通信の郵送
株主総会では、当日のプレゼンテーションとは別に、後日あらためて株主通信を郵送するのが通例です。プレゼンテーションだけでは把握しきれなかった詳細を株主通信で把握してもらい、より正確に情報を理解してもらうことで、株主の利益に資することが出来ます。その株主通信の構成や体裁について、広報担当者としての知見を活かせると良いですね。
株主とのリレーション形成の場になるなら、広報視点でのコンテンツ設計を
ここまで、株主総会の基本から実施方法までをご紹介してきました。
株主総会は、経営陣を筆頭に全社の大勢のメンバーが関わる一大プロジェクトです。そんなプロジェクトの中で、広報担当者としてどんな価値を発揮できるのか迷ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、株主総会を「株主とのコミュニケーションの場」として捉えれば、広報としての経験と知見を最大限活かしてプロジェクトに関わることが出来るはずです。どんな形でなら価値を発揮できるのか、工夫しながら取り組んでみてくださいね。
(編集:PR TIMES MAGAZINE編集部)
株主総会に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事決算発表の日時は平日の日中?金曜の夕方?広報PR担当者がすべき3つのこと

- 次に読みたい記事観光関連のプレスリリース、今どう発信すべき?事例や注意すべきポイントを紹介
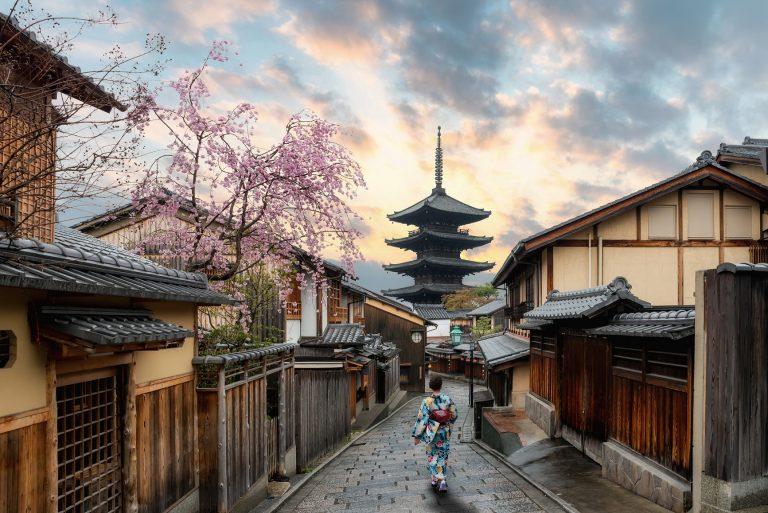
- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

