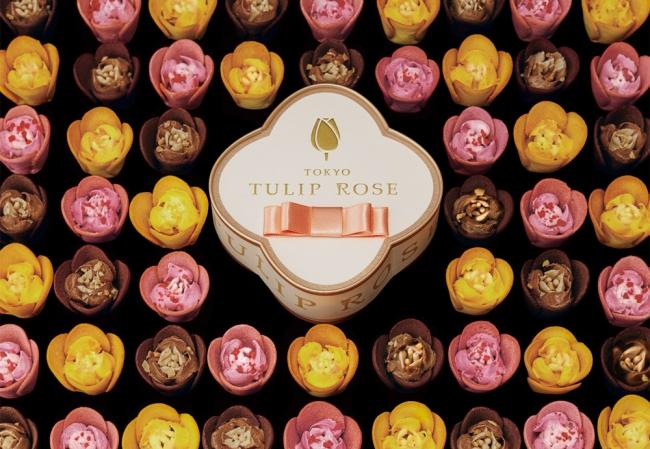事業活動報告書の発行を伝えるプレスリリースを配信することで、非営利団体としての取り組みや社会的な意義、今後の展望を幅広い層に伝えることができます。プレスリリースの効果を最大限に発揮するには、事実を並べるだけでなく、支援につながるような共感を呼ぶ表現を意識することも大切です。
とはいえ、どのような内容を盛り込めばよいか悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、非営利団体の事業活動報告書に関するプレスリリースを配信するメリットやポイントを、配信事例とともにご紹介します。
非営利団体の事業活動報告書に関するプレスリリースを配信する3つのメリット
事業活動報告書の発行に合わせたプレスリリースの配信は、団体の活動を支えるステークホルダーとの関係性を深める良いきっかけとなります。1年間の取り組みや成果、今後の展望を詳しく伝えることで、支援者や関係者に向けて信頼と共感を築く手段として有効です。
ここでは、事業活動報告書の公開にあわせてプレスリリースを配信するメリットを、3つの視点から解説します。
メリット1.信頼性・透明性が担保される
非営利団体の運営には公共性が不可欠であり、特にNPOは社会課題の解決を目的に活動しています。そのため、信頼に基づく支援(寄付・ボランティア・協働)が欠かせません。
団体の取り組みや成果、使途報告などを公に発信することで、「きちんと活動している団体」であることを示すことができます。プレスリリースを配信することにより、情報開示への姿勢を示し、さらに信頼感が高まります。
メリット2.組織の健全性・ガバナンスを強化できる
情報発信によって組織の透明性が確保されると、外部からの信頼を得るだけでなく、内部のガバナンスや事業管理の質を高める効果もあります。プレスリリースを配信し、情報公開の仕組みを整える過程で、団体内の業務や財務の整理が進むと、より健全で持続可能な組織づくりが可能となるでしょう。
ガバナンスを強化することで、企業の管理にまとまりができ、競争力の向上や長期的な事業成長が見込めます。
メリット3.団体の認知度が向上する
事業活動報告書単体では、既存の支援者など限られた層にしか届かないことが多いですが、プレスリリースとして発信することでメディア関係者や一般生活者などの目に留まるチャンスが生まれます。
報告書は、団体として大事にしたい理念や実現したい未来を、支援者や団体を知らない方々に丁寧に説明できる場です。プレスリリースの配信を通じて、団体を知らなかった人々にも活動の認知が広がり、新たな支援者や共感者を獲得するきっかけとなります。次年度の展望や今後必要な支援を明示すれば、さらに読み手の関心を引くことも期待できるでしょう。
非営利団体の事業活動報告書に関するプレスリリース作成の3つのポイント
これまで紹介したメリットを得るためには、活動報告としてどのような内容をプレスリリースに掲載すべきかが重要。具体的なポイントを以下で詳しくお伝えします。

ポイント1.報告書の概要をわかりやすく、数字を用いて記載する
メディア関係者や支援者には、長い報告書を全文読む時間がないことが多いです。プレスリリースの中で要点を素早くつかめる形式にすることで、取材や掲載につながる可能性が高まります。
どのような団体がどのような活動を行っているのかがひと目で伝わると、読み手はさらに詳細を知りたくなるでしょう。それがきっかけとなり、報告書のダウンロードや団体サイトへの訪問、支援行動などにつながります。
ポイント2.事業活動報告書への導線を設ける
プレスリリースは、事業活動報告書の内容をすべて見せる場ではなく、関心を持ってもらい、次のアクションへと導く入り口です。そのため、事業活動報告書への導線は、読み手の目に留まりやすい箇所に配置することが重要なポイント。
事業活動報告書の表紙をメイン画像として大きく掲載するのも、興味を引く工夫のひとつです。メイン画像付近にオフィシャルサイトや事業活動報告書をダウンロードするURLを掲載すれば、閲覧数の増加が見込めます。
ポイント3.支援の呼びかけや支援方法を明記する
プレスリリースを読んで共感してくれた方に向けて、具体的な支援方法を提示することが重要です。ただ支援を呼びかけるだけでなく、どのような行動が支援につながるのかを具体的に示すことがポイントになります。
また、支援方法は寄付やボランティア募集、物資支援、SNSでのシェアなど、大小問わず幅広く掲載しましょう。読み手が「この支援なら自分にもできる」と思ってもらえれば、支援者を増やすきっかけとなるでしょう。
下記の記事では、NPO・NGOにおけるプレスリリース配信の目的を紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
非営利団体の事業活動報告書に関するプレスリリース作成の注意点
プレスリリースを作成する際に、単なる事業活動報告書を発行したことを告知するだけでは、なかなか関心を引くことはできません。活動の背景にある社会的な課題や、それに対して団体がどのようにアプローチしているのかを伝えることが肝心です。
事業活動報告書の目次を紹介するだけで終わることがないように、報告書の中でも特に伝えたいトピックやエピソードを抽出し、ストーリー性を持って掘り下げてみましょう。
担当者推薦!プレスリリース配信事例10選
事業活動報告書の発行をプレスリリースで配信する際の参考となる事例を紹介します。活用できる点をポイントとしてまとめましたので、あわせてご覧ください。
事例1.特定非営利活動法人おてらおやつクラブ:インパクトレポートを公開
- 連携する支援団体数や受取寄付金額の前年度比の数値で概要を説明
- 「2024年度 インパクトレポート」への導線を三角記号で強調
- 支援を受けた方の実際の声を紹介することで活動の有用性の伝達と報告書への興味喚起
- 赤字の経緯をオープンに共有し、ファンドレイジングを強化
参考:【草の根で活動を広げ地道に支援を集めるも、大幅な赤字転落へ】認定NPO法人おてらおやつクラブ インパクトレポート公開
事例2.認定NPO法人SOS子どもの村JAPAN:財務報告のサマリーを掲載
- 冒頭で活動内容を簡単にまとめ、取り組みを紹介
- メイン画像の上部に事業活動報告書や寄付への導線を設置
- プレスリリース下部での寄付案内による読み手への自然な誘導
参考:SOS子どもの村JAPANの1年間の活動実績を掲載した「ANNUAL REPORT 2023」を発行いたしました。
事例3.NPO法人Clean Ocean Ensemble:支援の呼びかけが多様
- 冒頭に活動内容の概要を示し、理解を促進
- アイキャッチに事業活動報告書の表紙・裏表紙を使用し、視覚的に訴求
- 支援方法を4つに分類して紹介し、それぞれの詳細ページへの導線を設置
参考:NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、「2023年度事業・会計報告書」を発行いたしました
事例4.特定非営利活動法人 二枚目の名刺:参加者のアンケート結果を掲載
- 報告書の概要を3つのトピックに分けて箇条書きで記載し、内容を整理
- プロジェクトの参加者の声をグラフで提示し、客観的な評価として信頼性を向上
- 今後の取り組みを明記することで、活動に対する期待感の増加
参考:NPO二枚目の名刺が15周年を迎え、今後の取り組み指針をまとめた報告書を発表
事例5.NPO法人eboard:外国人をはじめとする多様な方に向けた報告書を公開
- 多様な背景を持つ読み手を意識し、タイトルで読みやすさと独自性をアピール
- 「生成AIで作成した事業活動報告書」という話題性のある切り口で関心を喚起
- 月間配信数や動画の総再生回数などを、図表でわかりやすく表現
参考:NPO法人eboard:生成AI作成の「やさしい日本語」版事業活動報告書を公開
事例6.一般社団法人ケアと暮らしの編集社:掲載ページを一部画像で紹介
- 事業活動報告書の一部を抜粋し、プレスリリースで紹介し、PDFのダウンロードを促進
- 関心を持った読み手にを寄付への導線を明確に設計
- 支援内容について、目標人数や対象機関を明示し協力の依頼
参考:「ケアするまちをデザインする」2023年度 年次報告書の発行のお知らせ
事例7.一般社団法人日本中小企業金融サポート機構:タイトルに成果を記載
- 過去最高実績となる支援総額をタイトルに記載し、主なメッセージを強調
- 実績データを太字で示し、視線を誘導しやすく工夫
- 取引者数や支援額の推移をグラフで可視化し、わかりやすさを向上
参考:【日本中小企業金融サポート機構2024年実績報告】支援総額318億円を達成
事例8.一般財団法人みらいこども財団:スライドを用いて説明
- 年間で交流した子どもの人数や施設数を示し、活動の規模を明確化
- 事業活動報告書の抜粋4点に補足説明を加え、関心を高める構成
- ホームページへの導線を設置し、団体やプロジェクトの認知を拡大
参考:ボランティアで社会を変える。児童養護施設の子ども支援の「みらいこども財団」は、設立10周年の年次活動報告を発表しました!
事例9.公益財団法人資生堂子ども財団:財団の紹介が詳しい
- 子ども家庭庁による調査をもとに活動画用を掲載し、社会的意義を訴求
- 多様な活動内容を画像付きで簡潔にまとめ、報告書公開を機に認知を拡大
参考:資生堂子ども財団、「2023年度 事業活動報告書」を発行
同財団は、2024年度からより多くの方に活動内容を知ってもらうため、冊子をデジタル仕様にしたことを発表。活動の成果や新たな企画、企業・団体との協働などをオンラインで閲覧できる年間活動報告書の特設サイトを開設しています。
参考:資生堂子ども財団「2024年度 年間活動報告 特設サイト」を開設!
事例10.NPO法人アクセプト・インターナショナル:具体的な寄付依頼
- 「数字で見る成果」やグラフでまとめられた報告書の一部を提示し概要を伝達
- CTAボタンで活動報告書への導線をつくり、閲覧を促進
- 寄付について具体的な方法や金額を伝えて支援への障壁の軽減
参考:パレスチナ和平や在日外国人支援など、国内外で紛争解決・平和構築に取り組むNGOが2024年度の活動報告書を公開。
非営利団体の事業活動報告書の発行時に広報が行いたい3つの広報PR施策
事業活動報告書を発行時には、プレスリリースの配信に加えて、ほかの広報PR施策を組み合わせることで、より多くの方に活動に興味を持ってもらい、支援の輪を広げることができます。
ここでは、事業活動報告書の発行にあわせて実施したいおすすめの広報PR施策をご紹介します。プレスリリースの配信とあわせて、ぜひご活用を検討ください。

1.活動報告会の開催
興味を持ってくれた方々と実際に顔を合わせて、取り組みの説明や感謝、成果の報告を行うことで、文章では伝えきれない熱意や誠意を直接届けることができます。寄付者やボランティア、助成団体、企業、行政などとの関係性が深まり、継続的な支援や新たな紹介につながる可能性もあるでしょう。
また、当日の対話を通じて質問や改善案をもらえるほか、報告会自体が取材の機会になることもあります。たとえば、認定特定非営利活動法人底上げのように、インターン生による卒業研究発表やゲスト講話など、参加者の体験を交えた報告を行うことで、より活動内容への共感を得ることができるでしょう。なお、報告会の開催にあたっては、プレスリリースに参加方法や申し込みフォームを掲載することで、参加者の獲得にもつながります。
参考:[活動報告会]福島県双葉郡楢葉町の子どもの居場所「ならはこどものあそびば」活動報告会を3/16(日)に実施
2.SNSでの情報発信・キャンペーンの実施
プレスリリースとSNSを連動させることで、情報の拡散力が高まり、より多くの人に活動を知ってもらうことができます。事業活動報告書の要点を図解や写真にアレンジして投稿すれば、長文を読むことに抵抗がある方や、読む時間がない層にもリーチが可能です。
また、独自のハッシュタブを活用して社会貢献活動への参加を呼びかけるキャンペーンも効果的。検索やシェアを通じて、関心の高い方たちに自然と認知してもらうきっかけにもなります。
認定NPO法人ロシナンテスのプレスリリースでは、ハッシュタグを活用したSNS投稿を通じて社会貢献ができるキャンペーン情報を掲載。これにより、寄付や支援に踏み出せなかった人に働きかけています。
参考:SNS投稿で社会貢献できるキャンペーン「#ノーサイドアクション」、協賛企業を募集
3.活動報告動画の公開
事業活動報告書に加えて、実際の活動内容を撮影した動画を公開することで、文字や写真だけでは表現しきれない現場の空気感や臨場感を、音声や映像を交えて効果的に伝えられます。
短い時間で多くの情報を届けられるうえ、言語の壁を越えられるのも動画ならではの利点です。小さな文字が読みづらい高齢者や、子ども、外国人の方にも、ビジュアルや音を通してイメージを感じ取ってもらうことができます。
社会福祉法人中央共同募金会は、各団体の活動内容について本編動画に加え、30秒のショート動画を作成し。URLをプレスリリースで公開することで、活動内容を容易に理解できるよう工夫しています。
参考:「ボラサポ・令和6年能登半島地震」助成団体の活動報告動画を公開しました
さいごに
作成には多くの工数や時間を要する事業活動報告書。1年の活動実績だけでなく、取り組みに込めた想いや関係者への感謝など、多くの想いが詰まった報告書だからこそ、広報PR施策として効果的に活用することで、より多くの方の目に触れ、支援や共感につながる可能性が高まります。
今回ご紹介したようなプレスリリースの活用事例を参考に、報告書の内容を丁寧に伝えるとともに、活動報告会やSNSでの情報発信、動画による発信なども組み合わせることで、活動の認知拡大が期待できるでしょう。
【監修者のご紹介】

株式会社PR TIMES メディアリレーションズグループ 非営利団体サポートプロジェクト担当
学生時代は国際協力団体に所属しボランティア活動やファンドレイジングに従事。2023年4月に新卒入社し、PR TIMESカスタマーリレーションズ部にてご利用企業様のプレスリリース配信の効果的な配信に向けたサポートやアドバイス、配信ネタの考え方・プレスリリース作成の勉強会講師を担当。2024年9月にメディアリレーションズグループ新設に伴い部署異動し、PR TIMESを日々の情報収集に活用いただくメディア記者との関係構築・深化を担うメディアリレーションズを担当。同年12月からは非営利団体サポートプロジェクトの責任者を担当。旅行と編み物、おいしい食べ物がすき。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする