広報PRに興味を持ったとき、広報になってすぐのとき、日々の仕事にモヤモヤを抱えたとき。みなさんはどうやってモチベーションを高めたり、必要な情報を収集したりしていますか。営業職やマーケティング職などと比較すると少数精鋭のチームであることが多い広報は、アドバイスをもらえる先輩や同僚がいない場合もありますよね。
日常業務に必要なスキルアップはもちろん、さまざまな会社の事例をキャッチアップするなど、スキマ時間に広報PRを学ぶのに最適なのが「本」です。今回はPRパーソンとしてキャリアを築くうえでおすすめな書籍13冊を、PR TIMES社員の推薦ポイントとともにご紹介します。
本は広報PRを学ぶ有効な手段
広報PRを学ぶ手段として、まず思いつくのは勉強会やセミナーへの参加でしょう。たしかに勉強会やセミナーでは、リアリティのある最新の事例を学べたり、その場で情報交換できる人脈を得られたりとさまざまなメリットがあります。
しかし、勉強会やセミナーは日時が決まっていたり、会場場所や地域も限定的であることから、業務との折り合いがつかず参加が難しいケースもあるはず。
そこでおすすめなのが、書籍です。書籍では最新の事例が反映されにくい分、成果が出やすい・出にくい事例や戦略立案に役立つフレームワークなど体系化された情報を得られます。ただ、たくさん存在している広報PRに関する書籍の中から今の自分にぴったりな本を選ぶのは難しいですよね。この記事では、広報PRの熟練度別にピックアップしてみたので是非参考にしてみてください。
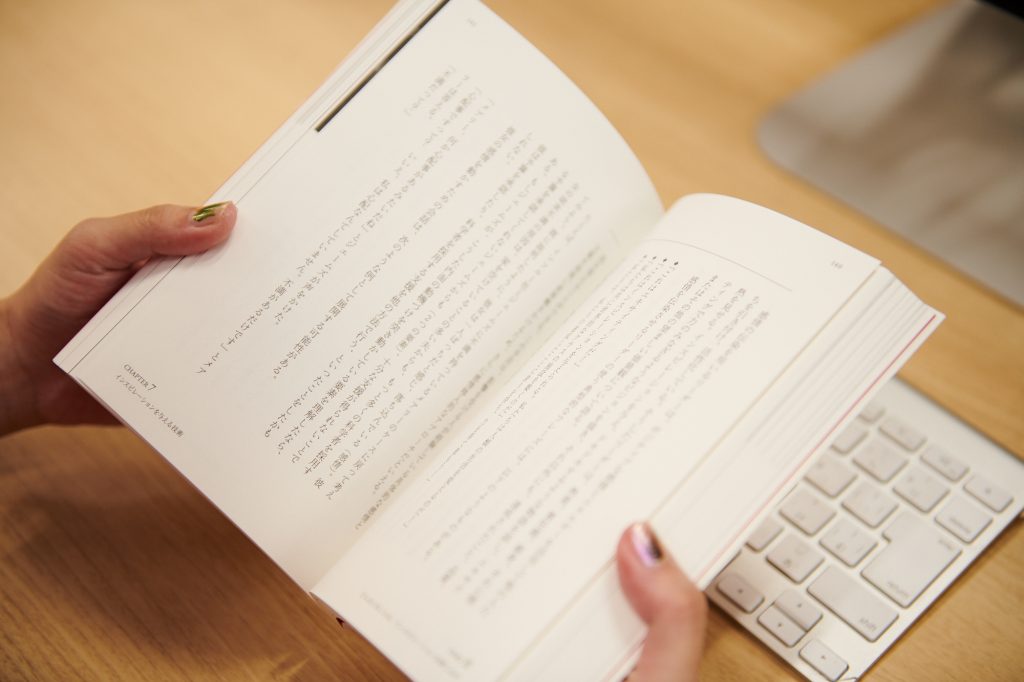
【基礎編】広報初級者の方が読むのにおすすめな本6選
広報になったばかりの方向けの書籍は「広報とは」「PRとは」といった概論をレクチャーするものが多く、どれを選ぶか迷ってしまうことも。本を読みたくても、悩みすぎて読み始められなかったという広報経験者もいるほどです。
そこでこの章ではPR TIMES MAGAZINE編集部が広報1年目だったらこれを読むと良かったな…という観点で、広報初級者のみなさんに読んでほしいとっておきの6冊をピックアップ。おすすめの順番でご紹介していきます。
広報・PRの基本
広報担当になったばかりの方の入門書とも言えるのが、『広報・PRの基本』です。業界について学べるのはもちろん、プレスリリースの作成方法、マスメディアへの連絡方法、インターネット広報のやり方、広報効果測定の仕方、リスク対応方法、ブランド戦略の立て方など、広報担当として進めていくべき業務について網羅的に学ぶことができます。
実際の広報担当者のインタビューや事例も多く掲載されているため、実際の業務とも関連付けやすく、まるで先輩広報担当者から話を聞いているように読み進められる一冊です。
パブリックリレーションズ 第2版 戦略広報を実現するリレーションシップマネージメント
『 パブリックリレーションズ 第2版 戦略広報を実現するリレーションシップマネージメント 』は「PR=パブリックリレーションズ」の概念や役割を説明してくれる、PRパーソンを目指したい人にとってマストリードの書籍です。
2015年に出版された第2版では、今日の視点を反映したSNSとパブリックリレーションズの関係や、インターネットやグローバルといった時代背景を踏まえた新しいパブリックリレーションズ、メディアリレーションズの在り方を提示しています。すぐに実践に生かしたい!という人よりは、じっくりと広報の知識を蓄えたい人におすすめです。
新人研修の対象図書にしています。広報の実務だけでなく概念や在り方まで感じさせてくれる本は多くないので重宝しています。 (PR TIMES CR本部・小暮)
危機管理、戦略PR、PR活動の評価、現代の企業PRのあり方など、広くさまざまな内容が網羅されており、パブリックリレーションズへの理解を深めるうえで、初めて読む書籍としておすすめです。(PR TIMES Jooto事業部)
広報入門―プロが教える基本と実務
広報担当としての経験と実績のある方の目線で、「広報とは」という初歩的な内容が書かれている『広報入門―プロが教える基本と実務』。
広報担当として知っておくべき基本や、広報とはどのような業務を遂行していかなければいけないのかが書かれています。経験者だからこそわかる広報の難しさや乗り越え方が書かれているため、今後のキャリアをイメージしやすい一冊となっています。
広報のお悩み相談室
「広報担当者になったら、まず何をすればいいの?」という疑問に答えてくれる『 広報のお悩み相談室 』。
目標設定の仕方のような基本事項から取材時のトラブル対応、社内報の書き方や後任への引継ぎまで、これを読めば広報の業務が丸わかりの一冊です。一問一答形式で読み進めやすく、新人広報さんは1冊デスクに置いておくと安心なのではないでしょうか。
質問に答える形式でライトなタッチなので、読みやすいとともに現場感を感じやすい内容でした。(PR TIMES CR本部・小暮)
広報・PR概論(PRプランナー認定試験公式テキスト)
広報PRの基本知識から実践スキルまでを3度に分けて検定する「PRSJ認定PRプランナー」検定試験の対策用テキスト、『広報・PR概論』。アメリカでPR=パブリック・リレーションズの概念が生まれ、日本に輸入されるまで導入されるまで、そして日本国内でどう広がったのか。意外と知らないPRの歴史からIRや社内広報など広報PR担当者として網羅しておくべき基本が凝縮された一冊。広報PRを体系的に学ぶのに最適です。
資格試験の勉強用書籍ということもあり、初心者でもわかりやすくまとめられています。このテキストを読んだことをきっかけに、PRプランナー試験に挑戦してみるのもおすすめです。
どう伝わったら、買いたくなるか
テレビや新聞でたびたび目にする「○○ブーム」。『どう伝わったら、買いたくなるか』を読むとそんなブームが誕生する裏側が丸わかり。いち消費者としても、いち広報担当者としても、読み進めながら驚きと学びが得られること間違いなしです。
実際にブーム化できた商品や取り組みの事例が多く紹介されているため、消費者行動を意識した効果的なPR戦略や、PRの裏側にある社会の動きの捉え方をケーススタディとしてしっかりと学べます。明日からの実務に役立つヒントを得られることでしょう。
【課題別編】広報経験者におすすめしたい、現場で使える本
広報担当としての経験を積み、ある程度広報実務がこなせるようになっても、悩みは尽きないもの。プレスリリースを極めたい、広報戦略の立案方法を習得したい、メディアリレーションでの悩みを解決したい…いまの自分に足りないものがはっきりしてきた時は概念的な本ではなく、具体的な業務や課題ごとのノウハウやナレッジがまとめられた書籍を読むのがおすすめです。
本章では課題ごとに日々の業務ですぐに活かせるより実践的な内容が盛り込まれた本を7冊紹介していきます。

戦力思考の広報マネージメント
広報担当としての経験や実績を積んだからこその「伸び悩み」を感じている方に読んでほしいのが、『戦力思考の広報マネージメント』です。日本国内での「広報力調査」をもとに、いまの広報担当に足りないものや弱み、それらを脱却するための方法が書かれています。今後の広報活動の方向性に迷っている方であれば、進むべき方向の道しるべともなりうる本です。
大手企業の広報担当者を想定した内容ではありますが、調査を元にした本書は多くの広報担当者に共通化する指摘も多く、ベンチャー企業やスタートアップの広報担当者にとっても気づきや共感が得られる一冊と言えるでしょう。
実践!プレスリリース道場 完全版
月刊『広報会議』の人気連載を書籍化した「実践!プレスリリース道場 完全版」。実際にメディアに取り上げられた38社のリリースがピックアップされ、プレスリリースの基本の書き方からメディアにもっと注目してもらうためのポイントまで、プレスリリースのいろはが学べる一冊です。
目的・タイプ別にもプレスリリースが紹介され、プレスリリースを書くのは初めてという方でもすぐに応用できるポイントが見つけられます。
プレスリリースについて改めて理解を深める上で非常に役立ちました。辞書的に使える点もオススメポイントです。 (PR TIMES 営業本部)
メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!(DO BOOKS)
広報担当者として避けては通れないプレスリリース。そんなプレスリリースに焦点をあてて詳しく説明しているのが『メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!(DO BOOKS)』です。
どのようなトピックスで構成を組むべきなのか、コンテンツはどのような内容で作成するべきか、ストーリーはどのように組んだらいいのかなど、プレスリリース作成時に必要な情報が揃っています。プレスリリースの作成に悩んでいたり、より効果を出したいと思っている方におすすめの一冊です。
新版 実践マニュアル 広報担当の仕事: すぐに役立つ100のテクニック
初版刊行から10年経っても未だに人気を誇っているのが『新版 実践マニュアル 広報担当の仕事: すぐに役立つ100のテクニック』です。最近改訂され、さらにパワーアップした内容になっています。広報担当であれば必ず一度は読んでおきたいバイブルとも言える本書は、一社に一冊は保持しておきたいですね。
メディアにおける広報PRの対策はもちろんのこと、インターネットやソーシャルネットワークサービスにおける対策もしっかりと押さえられています。また、広報担当であれば必ず習得しておきたい炎上時の対策方法やリスクヘッジの対策方法も学ぶことができます。
6 RULES OF STRATEGIC PR 戦略PR 世の中を動かす新しい6つの法則
戦略PRを提唱した本田哲也氏による「6 RULES OF STRATEGIC PR 戦略PR 世の中を動かす新しい6つの法則」は、人の行動を変え、世の中を動かす新しい6つの戦略PRの法則を、筆者の経験や世界中の事例をもとに解説しています。
平易な説明でありながらも実際のハイレベルな国内外の事例を紹介しているため、PRの事例を知りたい初心者さんからスキルをつけてレベルアップしたい中級者さんにもおすすめの書籍です。
事例を通してPR発想をインプットできるので非常に勉強になりました。定期的に読み返しています。 (PR TIMES 営業本部)
デジタルPR実践入門 完全版 (月刊広報会議MASTER SERIES)
『デジタルPR実践入門 完全版 (月刊広報会議MASTER SERIES)』は、インターネットを活用したPR活動に特化した一冊。めまぐるしく変化するインターネットの今更聞けない基本からソーシャルリスクとの向き合い方・コーポレートサイト改革などの応用まで。経験者はもちろん、インターネットが欠かせない現代では初心者の方でも読んでおいて損はないでしょう。
広報業界唯一の専門誌である『広報会議』とPR業界の第一線をゆく嶋浩一郎氏をはじめとした業界のプロフェッショナルたちが執筆されたこともあり、内容が濃くわかりやすいと定評があります。具体的なポイントやすぐ実践に移せる内容が多く、何度でも読み返せる一冊です。
【小さな会社】逆襲の広報PR術
中小企業やベンチャー企業の広報担当者は、専任ではなく他の業務と兼務して活動しているケースも多いでしょう。十分に時間をかけられない中でも、広報活動の結果を出さなければいけない!そんな広報PRパーソンにおすすめなのが『【小さな会社】逆襲の広報PR術』です。
言葉の使い方から戦略の立て方まで細かく記されており、多くのノウハウを習得できる一冊となっています。広報担当者はもちろん、経営にも役立つような内容も盛りだくさん。読み終わったら上司や社長にもおすすめしてみてください。
成長する企業がやっている 分析する広報 ~独自リサーチ10年以上でわかった「伸びる会社、伸びない会社」の違い~
広報活動を「感覚」ではなく「データと戦略」で捉えていきたいと考えている方には、『成長する企業がやっている 分析する広報 』がおすすめです。
10年以上にわたり1000社もの上場企業の広報を分析してきた筆者が、成功する企業に共通する広報の仕組みや考え方を明快に解説しています。特に「なぜこの施策を実施するのか」といった意図の可視化や、社内への説明力を高めたい広報担当者におすすめです。
広報を「分析」していく実践的なステップを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
プロフェッショナル広報の仕事術 経営者の想いと覚悟を引き出す
経営視点で広報を捉えたい方には『プロフェッショナル広報の仕事術 経営者の想いと覚悟を引き出す』がおすすめできる実用書です。経営者の「想い」や「覚悟」を引き出し、それを社内外にどう伝えていくかという、戦略広報の根幹に迫る内容が展開されています。
企業のパーパスやビジョンといった抽象度の高い情報を、広報担当者がどう言語化・発信していくかに悩む方にとっては、非常に有益な指針となる一冊です。ベンチャーから大手まで、すべての企業規模に対応した視座が得られます。
広報を学ぶ本の選び方&活用の3つのコツ
本記事で紹介したように、広報PRに関する専門的な知識に関する書籍は多数あるため、知識を深めたいとき、本は非常に心強い味方になります。ただし、書籍の数が多いため「どれを選べばよいのかわからない」「読んだ内容をどう実務に活かせばいいのか」と悩む方も少なくありません。
最後に、自分のレベルや目的にあわせた本の選び方と、読んだ内容を業務に活かすための工夫、さらに最新情報を効率よくキャッチアップするためのコツをご紹介します。読書を“学び”で終わらせず、“実務に活きる知恵”として活用していきましょう。
レベル感や知りたい内容に合ったものを選ぶ
広報を学ぶ際には、自身のレベルや目的に応じた本を選ぶことが重要です。初心者であれば「広報とは何か」から丁寧に解説されている入門書を、実務経験のある中級者であればプレスリリースの書き方や危機管理などテーマ別の実践書がおすすめです。上級者やマネジメント層には、戦略PRやブランド構築といった、企業視点での思考が求められる専門書を選ぶとよいでしょう。
また、読み進める際は順番に読み進めるだけではなく、冒頭・目次を見て、興味があるところから読み進めることも効果的です。
読書後には、社内に向けてアウトプットする
本で得た知識は、自分の学びだけに留めず、社内に還元していくことで広報チーム全体のスキルアップにもつながります。
まず有効なのが「要約共有」。読んだ本の重要ポイントを資料にまとめ、チームで共有しましょう。次におすすめなのが「ワークショップ形式での実践」です。例えば、実在するプレスリリースを見ながら分析する時間を設けると、知識が定着しやすくなります。
最後に、OJT形式で実際の業務に反映させることで、自分自身の学びを広報活動に自然と組み込むことができます。インプットをした後はアウトプットをするところまでセットで行うことで、知識と経験として定着させていきましょう。
最新版やトレンドの書籍は継続的にチェックする
広報に関係する環境は、常に変化しています。特にデジタル広報や危機管理、ESG対応などは最新のトレンドに合った書籍を選ぶ必要があります。
最新版を見つけるには、専門出版社の新刊情報や、業界誌・広報系イベントで紹介される書籍を定期的にチェックするとよいでしょう。
また、SNSやビジネス系の書評サイト、PRプランナーなどの有資格者が紹介しているブックレビューなども参考になります。検索時には「広報+トレンド」「広報+危機管理」など具体的なキーワードで絞り込むと、必要な本にたどり着きやすくなります。
広報PRを本から体系的に学ぶ
「広報PR」と一言でいっても、その領域はとても広く、どこから手をつけていいかわからなくなってしまいますよね。
まずは、自分の広報PRの仕事での経験値や、具体的な業務の悩みを切り口に、気になる本を手にとってみてください。
今のご自身の状況とマッチしている本は、あなたの学びをより深くしてくれ、より広報PRへの関心を生んでくれることでしょう。

本記事で紹介したポイントやおすすめ書籍を参考に、今のあなたにぴったりの一冊を選んでみてください。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
広報PRが学べる本に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事リモートワークが拡大するいま、広報活動への影響は?広報PR担当者への臨時アンケート結果

- 次に読みたい記事広報のキャリアパス|代表的な4つのルートから、評価されるポイントを解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

