少子化が進み競争率が激しくなる教育業界では、ブランディングの需要もますます高まっています。多くの企業と同じく学校ブランディング(スクールブランディング)を強化したいと考える方も見られますが、教育機関としてどのように展開すべきか悩むこともあるでしょう。
本記事では、学校ブランディングの定義から実践のための要素、成功に向けたポイントまで詳しく解説。広報PRの役割や具体的な事例もピックアップしていますので、これからブランディングを担う方はもちろん、情報発信に悩んでいる学校関係者の方もぜひ参考にしてください。
学校ブランディングとは
まずは「学校ブランディングとは何か」という部分を理解しておきましょう。自校の強みを発信するだけでなく、明確な目的を持って戦略的に展開しなければなりません。ブランディングの例として挙げられる企業との違いを知ることも重要です。学校ブランディングの基本的な定義と、企業ブランディングとの共通点・違いについて解説します。
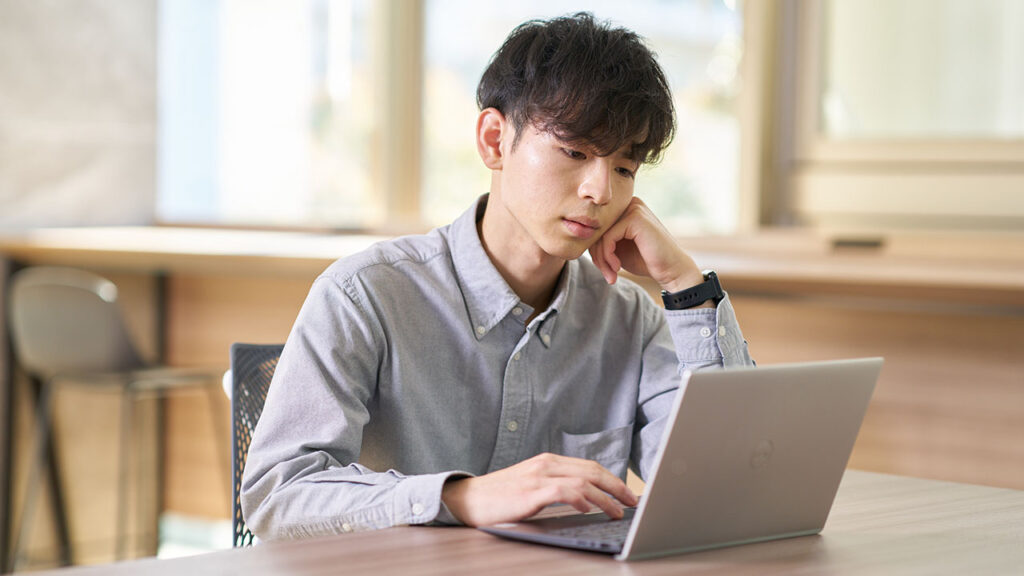
学校ブランディングの基本的な定義
「学校ブランディング」は「スクールブランディング」とも呼ばれ、独自性・新規性をはじめ魅力的な強みを発信する活動のこと。発信自体が目的ではなく、一貫性のあるイメージを定着させるための戦略的な取り組みです。
実際に発信する内容はさまざまですが、「この学校といえば」というイメージをあらゆるステークホルダーに持ってもらうアプローチが要となります。自校に対して抱いてほしいイメージと、実際に抱かれるイメージを統一させることが、学校ブランディングにおける重要な役割といえるでしょう。
企業ブランディングとの共通点と違い
学校ブランディングと企業ブランディングは、どちらも価値を示して知ってもらう・利用してもらうという目標があります。大きな違いは、目的とステークホルダーの属性です。企業ブランディングは自社の商品・サービスを利用してもらう利益追求が主な目的であるのに対し、学校は「憧れ」を生み出して教育機関としての価値を認知してもらうことを目的としています。
また、学校ブランディングのステークホルダーが多岐にわたるのも特徴的。例えば私立高校のステークホルダーは受験期の中学生であり、その保護者であり、さらに地域住民でもあります。中学生から高校生、大学生へと属性が変わる点も学校ブランディングの特徴といえるでしょう。
今、学校のブランディングが重要になっている背景・理由
少子化が進み生徒の人数が減少している昨今、学校間の競争率も高まっています。学校側が選ぶのではなく、生徒・保護者から選ばれる時代に突入したことが、学校ブランディングの必要性を高めた理由といえるでしょう。
またSNSをはじめとする多様なツールが普及し、情報を集める手段も増えました。ツールに応じた発信方法と内容を見極め、ステークホルダーに合ったコンテンツを提供する戦略も必要です。時代が大きく変化しているからこそ、ブランド力を固めて展開していく施策が重視されています。
学校ブランディングに必要な要素
学校ブランディングを進めるうえで、教育方針を整理したりコミュニケーション戦略を立てたりといった作業が必要です。カラースキームのようなビジュアル面も重要なポイントとなるため、具体的に何が必要であるか把握しておきましょう。学校ブランディングにおける5つの要素について解説します。
教育方針の明文化
自校の強みや魅力を発信するためには、教育方針を明文化しなければなりません。教育機関としての考え方・目標・こだわりなどを明確にしたうえで、生徒や保護者といったステークホルダーに伝える素材を組み立てていきましょう。
教育方針の明文化は、魅力を知ってもらうだけでなくステークホルダーとのミスマッチを防ぐためにも役立ちます。学校全体に浸透させることができれば、カリキュラムをはじめとする教育活動の一貫性を高める結果にもつながるでしょう。
校風や特色の可視化と統一感のある発信
教育方針のほか、校風やスローガンといった要素にも一貫性を持たせる必要があります。ブレが生じると、特に生徒や保護者の不安を募らせかねません。学校として力を入れている取り組みとその理由、目指すところなどを明文化し、齟齬を生じさせるリスクがないかチェックしておきましょう。
学校の情報はホームページをはじめ、パンフレットやプレスリリース、SNSなどさまざまなチャネルで発信できます。発信者によって違いが出ないよう、学校ブランディングに携わるすべての関係者が同じ意識を持つことが大切です。
ステークホルダー別のコミュニケーション戦略
学校のステークホルダーには複数の属性があり、生徒・保護者・地域住民など対象によってコミュニケーション戦略も異なります。在学生はもちろん、卒業生、受験生をはじめとする未来の生徒も想定すべきステークホルダーです。
- 生徒:自校で過ごす意義、将来性や楽しさ
- 保護者:進学実績や校内外の安全対策
- 地域住民:地域貢献活動や生徒と住民のつながり
このように「誰に伝えたいか」を明らかにしたうえで、適切なコミュニケーションを行うことが大切です。良好なコミュニケーションが継続できれば、ブランドの定着や支持にもつながるでしょう。
自校をイメージしやすいロゴデザイン・カラー
学校での取り組みや理念がイメージに結び付くよう、視覚的に伝えることも大切なブランディングのひとつです。スローガンやキャッチフレーズのほか、ロゴデザイン、パンフレットといった部分まで統一感を意識しましょう。
学校の場合、暗い色を多用するのは適切といえません。とはいえ明るすぎる色が多ければよいというものではないため、あくまで教育機関としての立場を前提に「自校らしさ」を構築する必要があります。生徒や保護者などステークホルダーが違和感を抱くことのないよう注意しながら、校風や特色を可視化していきましょう。
魅力的な体験価値の設計
生徒が獲得する体験価値は、学校のよさを直接的に伝えるために有効なブランディング要素です。受験生に向けたオープンキャンパスや学校説明会など、実際の体験を通じて自校らしさを知ってもらう機会を設けましょう。
課外活動や進路指導の内容を見直したり、教職員のスキル向上を図ったりといった施策も提案できます。受験生や在学生の体験価値を高めることで充実感・達成感が得られ、学校の魅力を強化する結果につながるでしょう。
学校ブランディングを推進する3つのステップ
実際に学校ブランディングを展開する際には、自校の強みを知ったり対象者を明らかにしたりといった工程が重要です。より多くの人に魅力を届けるために、複数のチャネルを活用した広報PR活動にも取り組んでいきましょう。学校ブランディングの流れを3つのステップに分けて解説します。

STEP1.差別化できる強みを知る
ブランディングの初期段階で重要なステップが、現状を分析して学校の強み・魅力を知ることです。教育方針やスローガンはもちろん、他校と差別化できる要素をなるべく多くピックアップしておくとよいでしょう。
このとき、ブランディングを強化する目的・目標を定めることも大切。生徒数を増やしたいのか、新しいカリキュラムを知ってほしいのかなど、自校がブランディングを必要としている理由が明確になれば、差別化すべきポイントやアプローチすべき対象者像も見えやすくなります。
STEP2.「どんな生徒に来てほしいか」を明らかにする
自校の強みを洗い出したあとは、「どんな生徒に入学して欲しいか」を考えていきます。ステークホルダーを生徒と保護者に絞り、差別化できる強みをより深掘りしていく重要なステップです。
学力レベルや進学率を示すのはもちろん、近年比重が高まっている社会ですぐに活きる経験を積めるようなカリキュラムや「〇〇部が〇年連続全国大会出場」と打って特定のスポーツに強みを見いだしたり、留学プログラム情報を提示して海外留学に興味がある生徒にアプローチしたりといった施策が検討できます。学力面ではもちろん、広い視点から生徒の将来につながる強みが提示できれば、学校が望む生徒像とマッチングしやすくなるでしょう。
STEP3.複数のチャネルで学校情報を発信する
学校のブランドを確立させたあとは、あらゆるステークホルダーに向けて魅力や強みを発信していきます。学校説明会や地域イベントで直接会話する機会を設けるほか、ホームページ・SNS・プレスリリースといった多様なチャネルを活用しましょう。
このとき「在学生に向けたSNS運用」「メディア関係者に向けたプレスリリース」など、内容や対象者に応じた発信内容を考えることも重要。例えば保護者は信頼性を重視しますが、情報源が多く複雑に感じるかもしれません。新しい取り組みに対してプレスリリース配信を行っていることで、信頼できる十分な情報を一覧で見てもらうことができます。
その後は自校の意図に合ったイメージを発信できているか、改善すべき点はないかなど、PDCAサイクルを回して継続的に取り組んでいきましょう。
学校ブランディングにおける広報PRの役割と情報発信の重要性
学校の強みや魅力を広く知ってもらうためには、広報PR活動を積極的に展開することが大切。在学生とその保護者はもちろん、受験生に入学を検討してもらったり、地域住民や企業に活動を認知してもらったりすることで確かなブランドへと育てていけるためです。
例えば、自校独自のカリキュラムを強みとする学校でも、認知度が低ければステークホルダーは情報をキャッチできません。ホームページやプレスリリースといったチャネルを通じて広く発信することで、より多くの人へ魅力を伝えられるようになります。
学校ブランディングの成功事例・具体的な取り組み5選
学校の強み・魅力を知ってもらうブランディングは今や必須ともいえる取り組みですが、実際にどう進めるべきかわからないという方もいるのではないでしょうか。全国各地の教育機関が多様な活動を展開しているため、自校に活かせそうなものがあれば積極的に取り入れていきましょう。学校ブランディングの成功事例と、参考になる具体的な取り組みを5つご紹介します。
事例1.幼稚園児~高校生を対象に、音楽を体験できる無料イベントを開催
学校法人・同朋学園は、愛知県の名古屋音楽大学にてイベントを開催しました。幼稚園児・小学生・中学生・高校生を対象に、ピアノについて学んだりパイプオルガンを体験したりといったプログラムを展開した無料イベントです。
大学進学を考える高校生だけでなく、幼稚園児から幅広い年齢層を想定したコンテンツが特徴。体験価値を高める効果が期待でき、多くのステークホルダーに「行ってみたい」という気持ちや憧れを想起させています。
参考:【名古屋音楽大学】「ドキドキ❤ワクワク♪キッズ音楽たいけん!」を開催します。
事例2.剥製の展示企画について準備時点から段階的に公開
大阪芸術大学は、「大阪芸術大学 動物ジオラマ館『芸大Zoo』」と題した展示企画を実施。日本の動物園ではあまり見られない動物の剥製を展示し、一般向けに公開するプロジェクトとしてスタートしました。
大阪芸大ならではの取り組みとして目を引くコンテンツですが、準備段階の様子をプレスリリースで発信したのが特徴的です。開館に先駆けて段階的に情報を発信することで、学校ブランディングの効果を高めた好事例といえるでしょう。
参考:2025年10月中旬に「大阪芸術大学 動物ジオラマ館『芸大Zoo』」がオープン決定!第1弾レポート「現地取材編」を本日公開
参考:「大阪芸術大学 動物ジオラマ館『芸大Zoo』」2025年10月1日(水)に開館決定!第2弾レポート「建設中編」を本日公開
事例3.地域と次世代の子どもたちをつなぐ教育モデル
子ども園や小学校、短期大学などを運営する学校法人・新渡戸文化学園は、「スタディツアー」と名付けた自校ならではの教育モデルを展開しています。地域と連携し、高校生にインターンシップの機会を与える取り組みです。
「地域の大人と次世代の子どもたちをつなぐ場所になる」ことを学校の存在意義としており、生徒・保護者・地域住民の方へ体験価値を提供しているといえます。活動内容の独自性が高く、教育機関としての役割も可視化できているのが特徴的です。
参考:「旅と出会いで高校生に火をつける」都農町で始まった、未来をつくる学びのデザイン。 修学旅行から、“スタディツアー”に改革し
事例4.デザイン専門学校のイベント情報をSNSで発信
東京都千代田区の山脇美術専門学校は、学校最大の行事である「山脇祭」を3日間にわたって開催。2025年は「Aqua World」をテーマに掲げ、海の世界をモチーフにした作品展示や装飾、販売ブースなどを展開しました。
学生が主体となって企画・運営するイベントで、毎年異なるテーマや校内装飾はデザイン専門学校ならではのコンテンツといえます。プレスリリースだけでなく、公式Instagramを活用して準備の様子を発信した広報PR施策もGOODです。
参考:山脇美術専門学校 学校最大行事「山脇祭」9月5日(金)~7日(日)開催決定
事例5.現役女子高生らによるバーチャルアイドルユニット活動
学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校は、バーチャルアイドルユニット「SO.ON project LaV」のミュージックビデオを公開しました。JIKEI COMグループの全国⾼等課程・⾼等専修学校に通う女子高生たちからなるユニットで、メタバース空間でのライブやYouTube配信といった活動も展開。
ARやVRが普及する現代ならではのコンテンツがユニークで、業界の最先端が学べる音楽専門学校としての強みも発信できています。在学生の体験価値を高めると同時に、受験生や保護者に自校らしさを知ってもらう効果も期待できるでしょう。
参考:バーチャルアイドル「SO.ON project LaV」、第6弾楽曲「アイドルマニフェスト」のミュージックビデオを公開
上記以外にも参考になる事例をピックアップしますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。
参考:関西大学のプレスリリース
参考:学校法人先端教育機構のプレスリリース
参考:学校法人 大正大学のプレスリリース
参考:武蔵野美術大学のプレスリリース
学校ブランディングを成功させる7つのポイント
学校ブランディングを円滑に進めるためには、ニーズの理解やストーリーの組み立てなども必要です。ステークホルダーとの関係構築にも配慮しながら、Webコンテンツを充実させたり適切な掲載内容を検討したりといった施策を丁寧に実施していきましょう。学校ブランディングの成功に向けて押さえておきたい7つのポイントをご紹介します。

ポイント1.ステークホルダーが求めているものを知る
自校のブランド力を効果的に発信するためには、「ステークホルダーが何を求めているか」をなるべく正確に把握しなければなりません。生徒・保護者・地域住民など、それぞれの属性に応じたニーズを理解しておきましょう。
ステークホルダーの要望を直接知る方法としては、学生や地域住民を対象としたアンケート調査が有効です。学校に求められていることがわかれば、自校の強みや特色とニーズをリンクさせたブランディング戦略を構築できます。発信内容とニーズの一致率が高いほど、満足度もアップさせやすいといえるでしょう。
ポイント2.学校の歴史や創立者の想いにストーリー性を持たせる
ホームページなどに掲載する学校の歴史は、ストーリー性を持たせるのがおすすめです。設立から現在までの歩みを時系列にまとめ、特別な出来事があったときは具体的に紹介できる構成にするとよいでしょう。
ストーリーテリングは事実を並べるよりも印象に残りやすく、学校に対する誇りを育みやすいというメリットがあります。創立者や現校長の想いを記載したり、卒業生が活躍している姿を取り上げたりといった内容も有効です。
ポイント3.在学中の生徒も巻き込んだブランディングを進める
学校のよさや自校らしさを発信するために、在学生を巻き込んだブランディングも取り入れましょう。理念・スローガン・校風といった要素は、生徒が具現化しているものでもあるためです。
例えば、高校の説明会で在学生が発表する機会を設けられれば、受験生は自身の、保護者は子どもの未来をイメージしやすくなります。在校生がアンバサダーのような役割を担うことにより、学校への親近感・安心感を高めるメリットが期待できるでしょう。
ポイント4.学生だけでなく地域住民との関係も構築する
学校におけるステークホルダーの中心は学生と保護者ですが、地域住民と関係を築くことも大切です。学生が主体となってコミュニケーションを図る機会があれば、学生を通じて自校らしさや校風を認識してもらえるでしょう。
例としては、学校周辺の清掃をはじめとするボランティア活動や、地域住民を対象としたイベントなどが挙げられます。生徒と社会との接点を作ることで体験価値を高め、さらに地域に根差した学校というイメージの定着にもつながるでしょう。
ポイント5.公式サイトのコンテンツを充実させる
学校のホームページは定期的に記事コンテンツを掲載しているケースも多く見られますが、情報量だけでなく読みやすさに配慮することが大切です。教育方針・カリキュラム・学校行事の様子などカテゴリも多岐にわたるため、知りたいページへすぐにアクセスできる導線も整えておきましょう。
コラムやブログのような記事であれば、ビジュアルコンテンツを活用して視認性を上げるのがおすすめです。顔や名札などの映り込みには注意が必要ですが、生徒が学校生活を送る様子や校内の雰囲気を視覚的に伝えられます。
ポイント6.チャネルに応じた掲載内容を考える
学校ブランディングを展開する広報PRにおいては、チャネルに応じた内容の検討が必要です。ホームページ・パンフレット・プレスリリースなど掲載場所によってステークホルダーの属性も変わるため、読み手に応じた情報であるか見極めましょう。
例えば、説明会で配布するパンフレットであれば、教員情報を掲載し、自校の方針に適した人材であることを示すのも一案です。ホームページで行事のお知らせを掲載したうえで、SNSでは生徒が主体となり写真・動画を投稿するというかたちを取ってもよいでしょう。
ポイント7.長期的な取り組みを前提に進める
学校の理念や校風は短期間で大きく変化するものではありませんが、ブランディング自体は長期的な取り組みが前提です。魅力・強みを発信する段階に進んだあとも、イメージをより強固にするための活動を継続していきましょう。
ブランディング効果を高めるためには、定期的な振り返りと改善が不可欠です。進捗を定期的に振り返り、維持すべき点・見直すべき点などを教職員全体で共有することで一貫性を保ちやすくなります。時流に柔軟に対応するためにも、地道な施策を積み上げていきましょう。
選ばれる学校になるためのブランディングを実践しよう
学校ブランディングが重要視されている背景には、少子高齢化やSNSの普及といった社会的な理由があります。学校の強み・魅力を具体的に把握し、ステークホルダーのニーズに合った情報を発信する戦略的活動が必要です。
また、ブランディングは一時的なものではないため、PDCAサイクルを回しながら長期的に取り組まなければなりません。まずは差別化できるポイントを知り、「選ばれる学校」になる一歩を踏み出しましょう。プレスリリースをはじめとする広報PRも積極的に取り入れながら、自校ならではのブランディングを構築してみてください。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする



