プレスリリースを作成するときやメディアへの掲載を報告するときなど、広報PR活動の中で注意しなければならない「著作権」。広報PR担当者なら知っておくべき知識ですが、詳細を知らないという方も多いかもしれません。著作権の侵害によるトラブルを防ぐため、この記事では著作権に関する9つのポイントを解説します。
著作権法とは?
著作権は、「著作権法」という法律のもとで定められる権利です。文章や写真・イラストに関して、著作権侵害が疑われるケースはニュースなどで話題になることも少なくありません。プレスリリースの配信やプレスキット、社内報などを作る現場においてトラブルを防ぐためにも、著作権法について把握しておく必要があります。
著作者の権利を守るための法律
著作権法は、小説や音楽といった著作物に関連する著作者等の権利を保護し、またそれらの文化の発展に寄与するための法律です。また、「著作権」は「知的財産権」の一つであり、「著作者の権利」と「著作隣接権」という2つの権利を含んでいます。
【知的財産権の構造】
著作権:著作者の権利、著作隣接権
産業財産権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権
その他:回路配置利用権、育成者権、営業秘密等
参考:文化庁 知的財産権について
「著作物」と「著作者」の定義
著作権法を理解するためには、「著作物」と「著作者」の定義も理解しなければなりません。著作権法で保護される対象が「何」と「誰」なのかを確認してみましょう。
【著作物と著作者】
著作物:「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 第2条第1項第1号)。具体的には以下a〜dの条件に当てはまるもの。
(a)「思想又は感情」を表現していること(自然物や事実それ自体は対象ではない)
(b)「創作的」に表現していること(ほかの作品の模倣やありふれた表現は対象ではない)
(c)「表現したもの」であること(表現を行う前の「アイデア」は対象ではない)
(d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること(工業製品などは対象ではない)
著作者:「著作物を創作する者」のこと(著作権法 第2条第1項第2号)。以下a〜eの条件をすべて満たす場合は、創作活動を行った個人ではなくその人物が属する会社等が著作者となる。
(a)その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること
(b)法人等の業務に従事する者の創作であること(部外者に委嘱して作成された場合など、会社との間に支配・従属関係にない場合は除外)
(c)職務上作成されること(作成を具体的に命じられた場合に限られ、大学教授の講義案のようにその職務に関連して作成された場合は除外)
(d)公表するときに法人等の名義で公表されること(通常、コンピュータ・プログラムの場合には公表せずに利用するものが多いためこの条件を満たさなくてもよい)
(e)契約や就業規則で創作活動を行った個人を著作者とする定めがないこと

すべての「著作物」に著作権が発生する
著作権は、その権利を得るための申請などは不要で、前述の条件に該当する著作物を創作した時点から自然発生します。「誰が作ったか」や「品質の高低」は関係なく、子どもが描いた絵や個人間でやりとりする手紙、アマチュアが制作した映像や音楽など、この世に存在する著作物のすべてに著作権があるのです。
著作権法の中では、さらに具体的に著作物に該当するものが例示されています。身の回りのものや広報PR活動に関係あるものがどの種類に該当するのかを想像しながら、目を通してみてください。
【著作物の種類】
- 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物(論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など)
- 音楽の著作物(楽曲および楽曲を伴う歌詞)
- 舞踊又は無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け)
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など<美術工芸品も含む>)
- 建築の著作物(芸術的な建造物 ※設計図は6.図形の著作物)
- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物(地図と学術的な図面、図表、模型など)
- 映画の著作物(劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど)
- 写真の著作物(写真、グラビアなど)
- プログラムの著作物(コンピュータ・プログラム)
- 二次的著作物(1〜9の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案<映画化など>し創作したもの)
- 編集著作物(百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など)
- データベースの著作物(11.編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの)
企業が著作権を侵害したときのリスク
著作権法は罰則が規定されている法律のため、権利を侵害した者や企業に対しては刑事罰が科せられます。しかし、想定しておくべきリスクは刑事罰だけではありません。企業が著作権を侵害した場合、社会的な信用を失ってしまう可能性もあるのです。そうしたリスクの詳細をご説明します。
社会的信用が損なわれる
近年、各企業が以前にも増して強化しているコンプライアンス。日本語にすると「法令遵守」を意味する言葉で、法令に限らず社会のルールや倫理を守った経営が重要視されています。そんな中で著作権を侵害する、つまり著作権法を守らない行動が発見されれば、社会的な信用は大きく損なわれますし、広報PR活動の肝である「ステークホルダーとの関係構築」にも大きな悪影響を与えることを念頭に置いておきましょう。
民事上及び刑事上の責任が問われる可能性がある
前述の通り、企業が著作権を侵害した場合、次のような責任が問われます。「1.民事上の請求」と「2.刑事罰」いずれの場合も、侵害状況によって損害賠償や罰金の具体的な金額は異なり、法人が著作権を侵害すると「最大3億円」の罰金が科せられます。
1.民事上の請求
(a)侵害行為の差止め・侵害物の廃棄
(b)損害賠償
(c)不当利得の返還請求
(d)名誉回復等の措置
2.刑事罰
(a)著作権・出版権・著作隣接権の侵害:10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金
(b)著作者人格権・実演家人格権などの侵害:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
※法人の代表者や従業員などが著作権(著作者人格権、実演家人格権を除く)等を侵害した場合:侵害行為者への罰則のほか、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられる。
参考:14 著作権が「侵害」された場合の対抗措置

広報PR担当者として知っておきたい著作権に関する9つのこと
ここまで、著作権法と著作権の基本情報について整理してきました。ここからは、前述の情報に加えて知っておきたい補足情報や著作物の使用時に守るべきルールなど、9つの情報を解説します。

1.著作物が保護されている国・地域
著作物が著作権法によって保護されるためには、著作物が次のa〜cの条件に当てはまっている必要があります。つまり、基本的には「日本人が日本で発行した著作物」「条約により保護の必要がある著作物」が保護の対象になります。
(a)国籍の条件:日本国民(法人を含む)が創作した著作物であること
(b)発行地の条件:最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)であること
(c)条約の条件:条約により我が国が保護の義務を負う著作物であること
参考:著作権法
2.著作権の保護期間
著作権は永遠に有効なものではありません。原則として「著作者の死後70年まで」が保護期間で、その期間を過ぎた著作物はパブリックドメインとして共有財産になり、誰でも自由に使えるようになります。ただし、著作物の種類によって保護期間は若干異なるので、以下を確認してください。
【著作物の種類と保護期間】
- 実名(周知の変名を含む)の著作物:死後70年
- 無名・変名の著作物:公表後70年(死後70年経過が明らかであればその時点まで)
- 団体名義の著作物:公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)
- 映画の著作物:公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)
3.著作権の制限(著作物を自由に使えるシーン)
著作権は全ての著作物に対して発生する権利ではあるものの、次の1〜11に該当する一定の例外的な場合に著作権等を制限し、著作権者等からの許諾なしで自由に利用できることが著作権法に定められています。ただし、この定めに基づいて複製されたものを本来の目的とは異なる目的で使うことは禁止されていますし、利用の際には原則として出所を明示する必要があるので十分に注意してください。
【著作物を自由に使えるシーン】
- 「私的使用」関係
- 「教育」関係
- 「図書館」関係
- 「福祉」関係
- 「報道」関係
- 「立法」「司法」「行政」関係
- 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係
- 「引用」「転載」関係
- 「美術品」「写真」「建築」関係
- 「コンピュータ」関係
- 「放送局」「有線放送局」関係
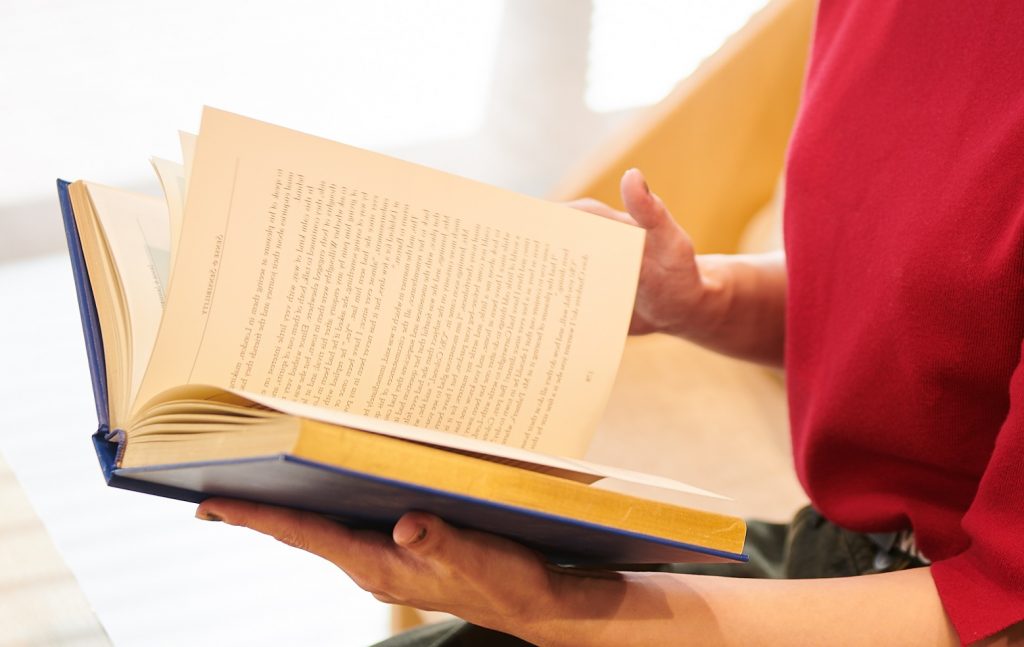
4.著作隣接権
著作隣接権とは、「著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者)」に与えられる権利のことです。なお、実演家は「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」、レコード製作者は「音の原盤を最初に作った者」を意味します。
また、著作権者が「差止請求権(他人による無断での著作物の利用を止められる権利)」を有する一方で、著作隣接権者は差止請求権に加えて「報酬請求権(他人による著作物の利用に際して使用料などの条件付きで利用させられる権利)」を有することが特徴です。その他の権利の詳細は、文化庁のホームページで確認できます。
参考:文化庁|著作隣接権
5.著作権者による許諾
著作権の保護対象である著作物の利用に際しては、「著作権者の許諾を得る」必要があります。ただ、著作者が著作権を譲渡している場合など、まれに「著作権者と著作者が異なる」ケースがあるので、確実に「著作権者」との契約となるよう注意してください。
著作権者を捜す際、著作物が本やCDの場合は出版社や発行元への問い合わせが有効です。それでも著作権者を見つけるのが難しいときは、著作物が分類される分野の著作権を集中管理する団体へ問い合わせてみてください。
6.文章の引用ルール
3.著作権の制限(著作物を自由に使えるシーン)でも解説した通り、他人の著作物である文書を自社の著作物に引用することは、問題ない行為です。広報PR活動、特にプレスリリースの作成などでは引用を行う場面も多いですが、引用方法には厳格なルールが設けられています。引用を行う際は、必ずルールを守ってください。もっとも、国や地方自治体の資料に掲載されている内容は、一般への周知を目的にしていることより通常の引用のルールより緩やかなルール(※1)によって引用することができます。
【引用のルール】
- 引用する著作物がすでに公表されているものであること
- 公正な慣行に合致すること
- 報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内であること
- 出所を明示すること(複製以外の場合はその慣行があるとき)
- 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
- 引用される分量が必要最小限の範囲内であること
- 引用部分が明確であること(カギ括弧などで明確にする)
※1 国・地方公共団体の機関・独立行政法人等が作成する「広報資料」「調査統計資料」「報告書」等の著作物からの引用の場合、以下の条件によって引用することができる。
- 引用を掲載する資料が一般への周知を目的とすること
- 引用する資料が行政機関等の著作名義で公表したものであること
- 刊行物(DVDなど電子媒体も含む)へ転載すること(ウェブサイトへの転載は含まれません)
- 「転載禁止」などの表示がないこと
- 出所を明示すること
7.写真・画像の使用範囲
写真や画像にも、もちろん著作権があります。プレスリリース・メディア向け資料の作成や自社Webサイト・SNSでのメディア露出の報告など、広報PR活動の中では写真や画像を使用する場面が多いですが、ルール違反がないかどうか細心の注意を払う必要があります。
ここで理解しておきたいのが、「著作権」と「肖像権」の違いです。「肖像権」は顔写真を無断で撮影されない権利及び撮影された写真を無断で公開されない権利を言います。したがって、例えば自社の従業員が他社媒体のインタビューを受ける場合、従業員の顔写真を撮影するか及び撮影された写真を公開するかを決める権利は自社の従業員にあり、無断で顔写真を撮影されたり撮影された写真が公開されたりした場合、当該従業員は撮影した方やインタビューを実施した企業に対し撮影や顔写真の公開を中止し請求することができます。
他方、写真自体の著作権は写真を撮影した方、またはインタビューを実施した企業が保持します(※2)。したがって、自社の従業員が顔写真の撮影及び公開をインタビュー実施企業に許諾した場合、当該従業員及び従業員を雇用している企業は自身の写真を無断で使用することはできません。
「著作権」と「肖像権」の違いの詳細につきましては以下の記事も参考にしてください。
また、自社の情報が掲載されているとしても、その記事や写真の著作権はそれを作成した方や企業にありますので、新聞記事やテレビ番組のキャプチャーを無断で自社のWebサイトやSNSに掲載することも厳禁です。どうしても必要な場合は、必ず著作権者である新聞社やテレビ局からの許諾を得てください。
【広報PR活動で注意したい使用例】
- OKパターン:Webサイトなどで使用するため自社が撮影した写真(著作権者=自社)を自社のSNS投稿でも使用する
- NGパターン:自社の従業員が受けた他社媒体のインタビュー中の写真(著作権者=他社)を自社のWebサイトで無断使用する
※2 企業が従業員ではないカメラマンと業務委託契約を締結し、著作権の譲渡および著作者人格権の不行使を明確に取り決めた場合。
8.音楽の使用範囲
近年、広報PR活動で音楽を使う場面が増えてきています。例えば、自社のWebサイトやSNS、YouTubeなどのプラットフォームで配信する動画や、自社でイベントを実施する際にBGMとして音楽を使用するケースがあるでしょう。音楽は特に複雑に権利・権利者が入り交じる著作物。使用方法によっては重大な著作権侵害になる可能性もあるので、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
【広報PR活動で注意したい使用例】
- 市販のCDなどをBGMとして社内で流す場合:作曲・編曲・作詞者の許諾が必要。市販のCDなどをコピーした場合は「複製行為」となるため、著作権に加えて原盤権者(レコード会社)やアーティストの許諾も必要。
- 複数の市販のCDをCD-Rなどに再編集してBGMとして社内で流す場合:作曲・編曲・作詞者の許諾/レコード会社(原盤権者)の原盤権の許諾/実演家等の許諾(著作隣接権)が必要。
- 自身が演奏・歌唱する他人の曲を使用する場合:作曲・編曲・作詞者の許諾が必要。
- 市販の音源を動画のBGMとして使用する場合:作曲・編曲・作詞者の許諾/レコード会社(原盤権者)の原盤権の許諾/実演家等の許諾(著作隣接権)が必要。
*JASRACやNextTone等が管理している楽曲であれば、これらの著作権管理事業者から許諾を得て使用することも可能です。ただし、著作隣接権については管理していないので、著作隣接権に関する利用をする場合には別途許諾が必要となります。
9.違法ダウンロード
近年よく耳にする「違法ダウンロード」も、著作権侵害の一部。「販売または有料配信されている著作物」を無断でコピーすること、インターネット上に公開してダウンロードできる状態にすること、違法にアップロードされたものであることを認識しながらダウンロードすること(私的に利用する場合も含まれます)はすべて民事的責任及び刑事的責任が問われる行為です。
違法ダウンロードが著作権を侵害する重大な違反行為であることを認識しなければなりませんし、もしダウンロードが必要な場合には、サイトやファイルに違法な点がないかどうかしっかりと確認しましょう。
著作権法を守って、トラブルなく広報PR業務を遂行しよう
条件が多く、一見すると理解が難しく感じる著作権法。しかし、ポイントさえ押さえておけば、決して難しいものではありませんし、あらゆる著作物をまったく利用できないという法律でもありません。著作権法を理解し、違反のない状態で著作物を利用できれば、むしろ広報PR活動の可能性は大きく広がります。
ステークホルダーとの信頼関係の構築を担う広報PR担当者として、当記事を参考に著作権法の知識を得て、トラブルなく広報業務を遂行してください。

広報PR担当者が知っておきたい「著作権」に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事プレスリリースの基本構成は?構成の作り方・入れるべき要素・注意するポイントを紹介
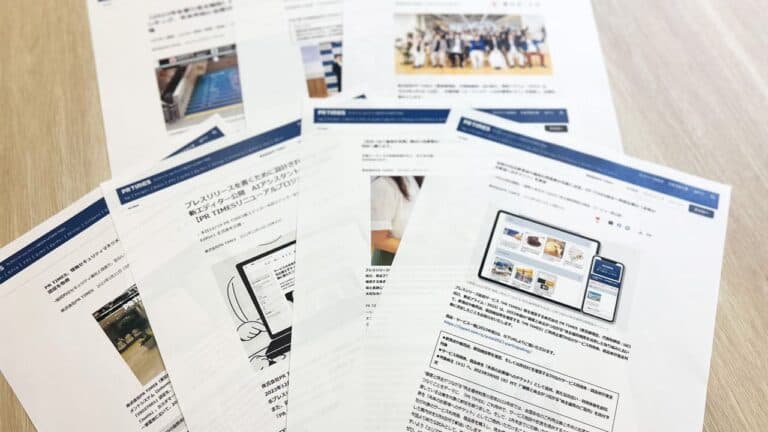
- 次に読みたい記事オウンドメディアのKPI・KGI・目標設定はどうする?設定のポイントとKPI例

- まだ読んでいない方は、こちらから新型コロナウイルス影響下、メディア側の動向は? #メディア関係者アンケート<前編>
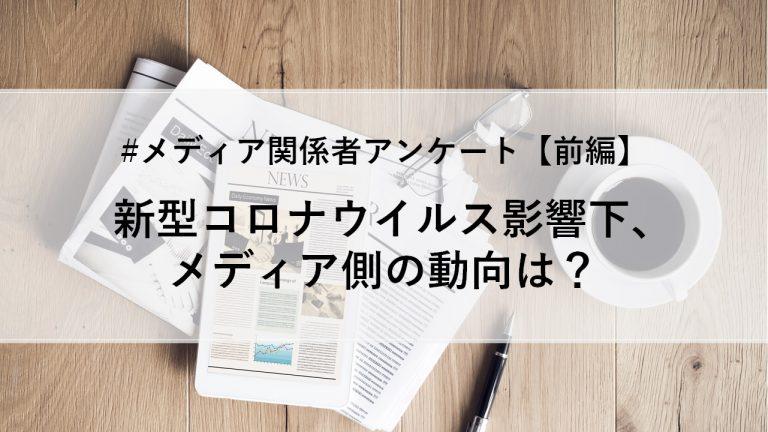
- このシリーズの記事一覧へ

