広報・PR担当者にとって、メディアからの取材対応は重要な業務のひとつです。適切な対応ができれば、自社のメッセージを効果的に発信でき、ブランド価値の向上にもつながります。一方で、取材を受けるときの準備不足や対応のミスがあると、意図しない形で情報が広まり、企業イメージに影響を与える可能性もあります。
本記事では、取材対応をスムーズに進めるために、広報担当者が取材前・当日・後日に押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。しっかり準備を整え、メディアとの良好な関係を築きましょう。
取材対応とは?取材を受けるときの全体像を把握しておこう
テレビ・新聞・雑誌・ラジオ・Webメディアなどマスコミからの取材を受ける際は、準備から取材中、後日のフォローを含めた対応が必要です。
取材を受けるかどうかは、さまざまな要素から判断します。取材依頼の内容が自社にとってプラスになるか否か、いまその情報を公にする適切なタイミングなのか否かなどが考慮すべきポイントです。
取材を受けることが決まったら、インタビューを受ける社内の担当者と日程調整をして、複数の候補日をメディア側に提示できるとスムーズです。取材場所は、メディア側から撮りたい人、場所、モノの要望があれば、撮影ができるように準備します。工場などの製造現場であれば「見学したい」という相談を受けることもありますので、現場とやりとりして調整しましょう。
オフィスを取材する場合は、だらしない印象を与えないよう、事前に社員に取材日程をアナウンスし、デスクなどを片付けておくようお願いしておくとよいですね。また、映ると情報流出につながる書類などに関しては、あらかじめ見えない場所にしまっておきます。
当日は会議室など取材場所の準備、取材対応者(インタビュイー)の服装チェックをして、取材にも同席します。取材中・後日のフォローまで含めて一連の流れが取材対応です。
取材対応を成功させる基本の心構えとマインドセット
取材の成功は、事前の準備や当日の心構えにかかっています。広報・PR担当者として、取材に臨む際に意識すべき基本的なマインドセットを持つことで、メディアとの円滑なコミュニケーションを築き、自社のメッセージをより効果的に伝えることができるでしょう。
ここから解説する3つのポイントを深く理解し、実践に活かしてください。
1.取材内容の編集権限はメディア側にある
取材内容の編集権限はメディア側にあります。メディアにとって「取材」はその字の通り、ニュースの「材料を取る」ことを意味します。つまり取材で得た情報をニュースとして使うかどうか、切り取り方のニュアンスなども、メディア側が決めるということです。
広報担当者として、取材内容をコントロールしたい気持ちは理解できますが、掲載前の記事や放送予定の番組の原稿を事前にチェックしようとする行為は、敬遠されたり、信頼関係を損なう可能性があります。唯一、明確な事実誤認がある場合のみ、誠実な姿勢で訂正を依頼するのがプロの対応です。この原則を理解することで、メディアとの建設的な関係を築き、次回の取材機会にもつながります。
2.オフレコは通用しないと心得る
取材の場における「オフレコ」は、広報担当者にとって非常に危険な概念です。記者や編集者にとって、取材で得たすべての情報は記事の素材であり、たとえ口頭で「これはオフレコで」と伝えたとしても、その発言が意図せず使用されてしまうリスクは常に存在します。
そのため、絶対に公にしたくない情報は、いかなる場合でも発言しないという強い心構えが必要です。
事前に社内で発言してはいけないNGワードを共有し、取材中にうっかり口にしないよう、徹底したトレーニングを重ねておきましょう。
3.業界用語を多用しないよう気を付ける
広報の役割は、自社の専門的な情報を、社会の誰もが理解できるように「翻訳」することにあります。専門紙の記者でない限り、記者は業界の専門用語に精通しているわけではありません。業界用語を多用すると、正確な情報が伝わらないばかりか、不要な確認作業が増え、取材時間が超過する原因にもなります。読者や視聴者の視点に立ち、平易な言葉で丁寧に説明する姿勢が重要です。
社内で使われる専門用語の定義を統一し、誰にでもわかる言葉に置き換える練習を日頃から行っておくことが、取材の質を高めることに直結します。
4.取材相手は「味方」と考える
取材相手であるメディアや記者は、敵でもなければ、自社の広報ツールでもありません。彼らは自社の情報を世の中に伝える「協力者」です。このマインドセットを持つことで、取材の場の雰囲気は一変します。
敵対心を持つのではなく、互いに良い記事・番組を作り上げるパートナーとして接することで、より深い話を引き出してもらえたり、意図を汲み取った記事を作成してもらえたりする可能性が高まります。誠実な態度と協力的な姿勢で臨むことが、メディアとの長期的な信頼関係を築くための最も重要なポイントです。
【取材前】準備の質が成功を左右する!徹底した事前準備
取材対応の成否は、事前の準備によって決まると言っても過言ではありません。メディアとの限られた時間を最大限に有意義なものにし、お互い有益な時間にするためには、当日に臨むまでにできることをすべてやり尽くしておきましょう。
1.メディアと記者の事前リサーチ
取材依頼を受けたら、まず最初に行うべきは、メディアと記者の徹底的な事前リサーチです。メディアの媒体特性(新聞、テレビ、Webなど)や読者層を理解することで、記事のトーンや伝えたいメッセージの方向性を調整できます。さらに、担当記者の過去の記事を読み込むことは、その記者がどのようなテーマに関心があるのか、どのような切り口で記事を書く傾向があるのかを把握する上で非常に有効です。
リサーチをすることで、記者の質問を予測するだけでなく、広報担当者が「私たちはあなたの媒体や記事を理解しています」という誠意を示すことにも繋がり、取材の場での信頼関係構築に役立ちます。
2.想定質問を作成しインタビュー練習を実施する
メディア側から取材依頼書をもらった場合、それを基に想定質問を作成しましょう。記者によっては大まかな質問事項を教えてくれる場合もあります。想定質問を作成したら、取材対象者とインタビューの打ち合わせをします。広報担当者が記者役になって、想定質問に対する回答を掘り下げながら追加で質問してみましょう。
練習で良いフレーズやメッセージが引き出せたら、その回答をメモしておけば当日に再確認しやすいです。予行演習をするとインタビュイーが話す内容を整理でき、落ち着いて取材に対応できます。
3.最新の自社データを揃えておく
自社の基本データの中でも、公開していないもので用意できる数字の「最新版」を用意しましょう。メディアの記者は、ニュースの新しさと希少性を重視する傾向があります。
従業員数・売上高・販売数は会社概要やIR資料で見ることができますが、業界シェア・生産数・サービスのダウンロード数などは、公開していない企業も多いです。未公開のデータは希少性があり、準備すると記者がニュースで取り上げやすくなります。また取材中に記者から質問があったとき、新しい情報を回答できるよう、エクセルやスプレッドシートにまとめておきましょう。
4.もっとも伝えたいメッセージをひとつに絞ってキーワードを決める
メディアの発信に触れた視聴者や読者に自社をどう思ってもらいたいか意識し、伝えたいメッセージを明確にします。そのメッセージにぴったりのキーワードを決め、取材で5回以上発言することを、インタビュイーの目標にしてみましょう。インタビュー練習でキラリと光るワードが飛び出すこともあります。取材中に繰り返し伝えることでメディア関係者の印象に残り、見出しに使ってもらえることもあります。
例えば、「営業改革で売上高130%増、販売先拡大に成功」という見出しと「カスタマーサポートが売上高130%増に貢献、リピーターが利益底上げ」という見出しでは、読者に与える印象は大きく異なります。
記者から今年度の売上高が伸びた要因を聞かれたとします。営業、カスタマーサポートなどさまざまな要因が絡んでいたとしても、記事やテロップの見出しに2つの要素は入りません。今回の取材では、「営業力の高い会社」というイメージを与えたいのか、「顧客対応が丁寧な会社」というイメージを与えたいのか、どちらに重点を置くかは、事前に社内で調整しておきましょう。
インタビュイーには、今回の取材でもっとも伝えたいことを伝え、どのように発言してもらうか決めておくとよいでしょう。取材内容の編集権限は記者にありますが、広報担当者は、記者に与える情報の数と深度、印象をコントロールできます。準備したメッセージを発信し、メディアがどう取り上げるかをチェックしながら、試行錯誤を重ねましょう。
5.当日持参する資料の準備
取材当日、記者がスムーズに取材を進められるよう、事前に準備しておくべき資料があります。紙媒体の記者であれば、印刷された企業概要やサービス資料、製品カタログ、さらにはキーマンの顔写真やロゴデータなどを用意しておきましょう。Webメディアやテレビの場合、高解像度の画像データや動画素材を、USBメモリやクラウドサービスを通じてすぐに共有できるようにしておくことが重要です。
これらの資料は、記者が記事を執筆する際に不可欠な情報であり、彼らの手間を省くことで「この企業の広報は気が利く」という良い印象を与えることができます。また、取材対象となる製品やサービスの実物、デモンストレーション用のツールなども、記者の理解を深める上で有効です。

【取材当日】スムーズな進行と円滑なコミュニケーションのポイント
取材対応当日、広報担当者はメディア関係者と自社のインタビュイーとの間で架け橋としての役割を果たしましょう。この日、両者は初対面であることがほとんどです。緊張した雰囲気を和らげ、双方が気持ちよくコミュニケーションできるよう、細やかな気配りやサポートを徹底することが、取材を成功へと導く鍵となります。
本項では、取材対応当日に行いたいポイントを紹介します。
1.取材に同席しインタビュイーをサポートする
広報担当者は必ず取材に同席しましょう。広報担当者が取材中に発言することはほとんどなく、サポートに徹します。
- インタビュイーが誤った情報を発言したときにさりげなく訂正する
- 数字やデータがすぐ出てこなかったときに代わりに回答する
- 取材中に伝えると決めていた事項を話し忘れていたら「そういえば、〇〇の件もありますよね」と適切なタイミングで話題を振る
などが事例です。取材当日がメディア関係者とインタビュイーの初対面というケースがほとんどです。日頃からメディアリレーションズをおこなっている広報担当者は、お互いが質問・回答しやすい和やかな雰囲気作りを心掛けるのも重要なサポートですね。
2.取材の目的を再確認する
取材当日の冒頭、取材に同席する広報担当者が、取材の目的を記者に再確認することは、円滑なコミュニケーションを築く上で非常に有効です。
「本日は〇〇に関するお話を中心に、〇〇といった切り口でお話しさせていただければと思いますが、認識は合っていますでしょうか?」といった形で、取材のゴールを双方が共有することで、話の方向性がぶれることを防げます。これは、記者にとっても取材の軸が明確になり、効率的に質問を進められるメリットがあります。
また、事前にリサーチした記者の過去の執筆内容に触れ、「以前の〇〇に関する記事を拝見し、〜〜という点に大変感銘を受けました」と伝えることで、記者の関心事を理解しているという誠意を示し、取材の場の雰囲気を和やかにすることができます。
3.追加情報を迅速にメールで送る
取材後に、記者から素材の提供をお願いされることがあります。代表の宣材写真、ロゴマークなどのデータ、商材の写真、社員や従業員の業務の様子がわかる写真などがよくあるパターンです。
こうした依頼があった際、いかに迅速に対応できるかが、プロとしての評価を左右します。できれば事前に用意しておき、打診されたらその日のうちに共有できるようにしましょう。迅速かつ丁寧な対応は、記者の制作スケジュールを助けるだけでなく、広報担当者に対する信頼感を高め、長期的なメディアリレーションシップの基盤となります。
4.取材の記録を残しておく
取材中の受け答えを、録音やメモで正確に記録することは、広報担当者にとって非常に重要な業務です。この記録は、取材内容を正確に把握するためだけでなく、今後の広報戦略を練る上で貴重な資産となります。
インタビューの場は、メディア関係者だけでなく広報担当者にとっても社長の想いや考えを聞ける貴重な機会です。取材での回答内容は、次回の取材、会社説明資料、コーポレートサイト、採用活動、社内研修などさまざまな活かし方ができる素材になるかもしれません。
また、取材中にすべての質問に対して完璧に回答することは難しいものです。その場で回答できなかったものについても記録し、早めに調べてメールで情報を送りましょう。

【取材後】成果を最大化する事後対応と関係構築
ここまで取材対応で準備しておくべきこと、取材を受ける当日に行いたいことを紹介しました。無事に取材が終わってホッと一息……といきたいところですが、実はメディア取材後日の対応も重要な業務です。本項では取材対応後日に行いたいポイントを解説します。
1.お礼のメールを送る
取材が終了したら、できるだけ早く、できれば取材当日のうちに、記者へお礼のメールを送りましょう。これは単なる社交辞令ではなく、メディアリレーションシップを構築する上で非常に重要なアクションです。
メールでは、取材の機会をいただいたことへの感謝を伝えるとともに、取材で話した内容への補足や、提供し忘れた情報があれば、このタイミングで送付します。この迅速かつ丁寧な対応は、記者の「またこの企業の広報に取材したい」という好印象につながり、今後の関係性構築に大きく貢献します。
2.社内外への告知
メディア掲載が決定したら、その情報を社内外のステークホルダーに積極的に告知することは、広報の成果を最大化する上で不可欠な業務です。「〇月〇日の〇時から〇〇という番組で弊社が紹介されます」「〇月〇日付の〇〇新聞にて弊社の〇〇について掲載予定です」などと、わかりやすく紹介するとよいです。記事や番組が多くの人の目に触れるのはメディア側にとっても良いことなので、積極的にステークホルダーに知らせていきましょう。
社内に対しては、従業員のモチベーション向上やエンゲージメント強化に繋がります。「自分の会社が社会に認められた」という誇りや帰属意識を育む良い機会です。
また、社外のステークホルダー、特に既存の取引先や顧客に対しては、「勢いのある会社」というポジティブなイメージを与え、信頼度や期待値の向上に貢献します。広報活動の目的は、メディアに掲載されること自体ではなく、その後のステークホルダーからの評価を高めることにあります。この視点を持って積極的に情報を発信しましょう。
3.モニタリングして誤情報がないかチェック
自社に関するメディア掲載やSNSの投稿などを確認することを「モニタリング」と言います。取材終了後は、モニタリングで掲載や放送の内容をチェックしましょう。
誤情報には、企業側の伝達ミスとメディア側の誤認によるもの、2つのパターンが考えられます。いずれの場合も、事実に反する情報が世に出た場合は、迅速な対応が求められます。
メディアの過失が大きく、企業イメージに甚大な影響を及ぼす場合は、訂正を依頼する勇気が必要です。ただし、訂正記事の掲載はハードルが高い場合も多いため、まずはウェブ版の記事だけでも正しい内容に修正してもらうよう、誠実な姿勢で依頼することが賢明です。
4.自社サイトやSNSでシェア
獲得したパブリシティは、二次利用することでその価値をさらに高めることができます。自社ウェブサイトやSNS、営業資料、採用資料に掲載することは非常に有効な手段です。しかし、この際に広報担当者が絶対に忘れてはならないのが、著作権の扱いです。
メディアが制作した記事や映像、画像などの著作権は、すべてメディア側にあります。そのため、無断で切り抜いたり、画像や映像を使用したりすることは著作権侵害にあたります。
ウェブ記事のリンクをSNSでシェアする程度であれば問題ないケースが多いですが、記事そのものを転載したり、画像を二次利用したりする際は、必ず事前にメディアに申請し、許可を得るべきです。このルールを守ることで、メディアとの信頼関係を維持し、今後の取材機会を失うリスクを回避できます。
5.取材対応の振り返り
すべての取材対応が終了した後、広報担当者として行うべき最後の重要なステップは「振り返り」です。今回の取材で良かった点や、次回への改善点を社内で共有しましょう。
例えば、「インタビュイーがこの質問にうまく答えられた」「このデータが非常に喜ばれた」といった成功体験や、「もっとこの情報を準備しておけばよかった」「想定外の質問に答えられなかった」といった反省点を具体的に洗い出します。
この振り返りのプロセスは、今後の広報活動をより洗練させ、メディアリレーションシップをより強固なものにするための貴重な財産となります。このPDCAサイクルを回すことで、広報担当者としてのスキルアップにも繋がります。
お互いが良い取材になったと思えるように準備・対応しよう
本記事では取材対応について広報担当者が知っておきたい取材対応について紹介しました。
「取材対応」と聞くとインタビューの様子を連想しがちですが、実際は事前準備、当日のフォロー、記事掲載後のモニタリングなど裏方の仕事が多いです。広報担当者は、インタビュアー(メディア側)とインタビュイー(取材を受ける社内の人間)がお互いに満足のいく取材にするため、本記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
取材対応に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事【フォーマットあり】取材依頼書の書き方とは?基本構成と承諾率を高める5つのポイントを紹介
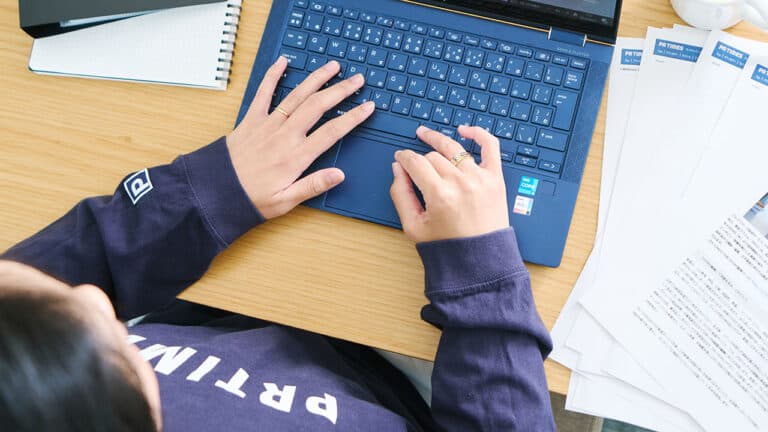
- 次に読みたい記事広報PR担当者が知っておきたいインタビューのコツ12個

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

