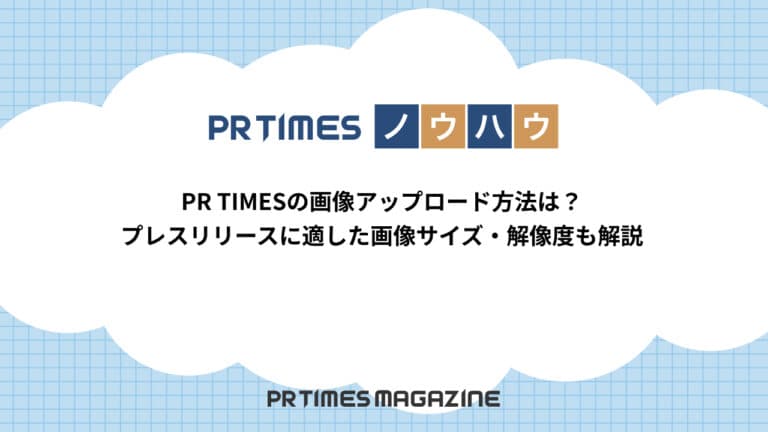プレスリリースや社内報、SNS、メディア向け資料など、広報業務では写真を使った情報発信の機会が増えています。担当者自身が撮影やディレクションを担うことも多く、その方法次第で写真のクオリティが情報の伝わり方に大きく影響します。
写真は、文章だけでは伝えきれない雰囲気や信頼感を補完する、広報における重要な要素です。効果的な撮り方やディレクションの基本を押さえることで、情報発信の幅も広がります。
本記事では、広報担当者が知っておきたい写真撮影の基本やコツを、6つのポイントとシーン別にご紹介します。これから写真撮影を検討している広報の方は、ぜひ参考にしてみてください。
広報に写真が重要な理由
広報活動において、写真は単なる「添え物」ではありません。文章だけでは伝えきれない企業の雰囲気や信頼感、リアリティを補完し、ステークホルダーとの距離を縮める強力な手段です。特にSNSやオウンドメディア、プレスリリースでは、情報の第一印象を決定づける要素として機能します。
また、視覚的な情報は記憶に残りやすく、情報の理解度や共有率も高めます。同じ内容でも写真があるプレスリリースの方が、メディアに取り上げられる確率が上がるのは想像しやすいのではないでしょうか。
広報の目的が「伝える」だけでなく「伝わる」ことである以上、写真の役割は非常に大きいと言えるでしょう。
さらに、撮影された写真は一度きりの用途にとどまらず、コーポレートサイト、採用パンフレット、SNS、営業資料など幅広いコンテンツで再利用が可能です。良質な写真を資産として蓄積することは、広報の効率と質の向上に直結します。
広報担当が知っておきたい、写真撮影で気をつけたい7つのポイント
広報写真は「当日うまく撮る」よりも、「当日までに迷いを消す」ことで品質が決まります。なぜなら、写真は媒体ごとに必要な比率や雰囲気が異なり、現場では時間も人も限られるからです。事前に目的と掲載先を定義し、必要カットと段取りを言語化しておけば、撮影中の判断が減り、被写体の負担も軽くなります。
結果として、プレスリリースならニュース性が伝わる画がそろい、採用なら職場の空気感が残り、SNSなら指が止まる一枚が生まれやすくなります。ここでは「決める→設計する→1セットで回す」という最短の型に落として、初めてでも再現できる流れに整理します。
撮影場所の決定やスケジュールの策定など、7つのポイントを紹介します。
1.用途や掲載媒体に合ったカットや撮影場所を決める
撮影をスタートする前に、その用途と必要なカット、撮影場所をあらかじめ検討しておきましょう。写真は読み手やメディア関係者にわかりやすく情報を伝えてくれます。一方で、用途に合った撮り方をしたり写り込みなどに配慮したりして、違和感を抱かせないようにすることも大切です。
例えば、テーマがオフィス紹介ならオフィスで被写体を撮影する必要がありますし、自社製品の紹介なら、なるべく背後に写り込みがないほうが製品が映えるでしょう。インタビューなどで人物を撮影するなら、夜より昼の明るい部屋で撮ったほうがきれいに写ることもあります。
また、あとになって「あの写真も必要だった」と慌てないよう、「どんな写真が何枚必要なのか(カット数)」を想定しておくことも重要です。伝えたい内容によって「寄り or 引き」と撮り方を変えたり、掲載媒体によって「縦 or 横」の形態を選んだりして、わかりやすい写真になるよう、工夫しましょう。
2.必要なシーンとカットを踏まえた撮影スケジュールを組む
必要なシーンとカットを洗い出したら、続いて撮影スケジュールを組み立てます。
人物を含む撮影の場合は、写る人のスケジュールを押さえる必要がありますし、オフィスの撮影の場合にも、そのことをメンバーに周知しておく必要があるでしょう。また、時間帯によって窓から差し込む太陽光は変化します。光の様子によって写真の印象は変わるので、自然光で撮る場合は時間帯にも気を配りましょう。
必要なシーンとカット数によって、所要時間も異なります。「いつ・何を・どれくらい撮るのか」をしっかりとスケジュールに落とし込んでおきましょう。
3.串刺し、目刺し、首切りなどのNG構図を把握する
人物を被写体とする写真撮影で、NGとされる構図があるのをご存じでしょうか。「串刺し」「目刺し」「首切り」……やや物騒なネーミングですが、撮影の品質アップのために頭に入れておきましょう。
すぐ後ろにあるものだけでなく、遠くにあるホワイトボードや窓枠、建物などにも気を配らないとこれらのNG構図になってしまうことも。注意してくださいね。
【NG構図の例】
- 串刺し:被写体の頭に対して垂直の線(たて線)が背景に写り込む
- 目刺し:被写体の目に対して刺さるような線が背景に写り込む
- 首切り:被写体の首を横切る線が背景に写り込む

4.髪型や服装の要件があれば事前に共有しておく
インタビューなどで人物を被写体にする際、髪型や服装に指定があれば、前もって共有しましょう。
例えば、コーポレートカラーやサービスカラーを身に着けてもらったり、自社のロゴ入りの服を着てもらったりするほか、スーツなどのドレスコードを設けることもあるかもしれません。写真の使いみちや掲載媒体に合わせて、要件を指定しましょう。
また、撮影中に髪型や服装が乱れていることに気づいたら、その場で直しながら撮影します。
5.余計なものが写らないようにアナウンスする
写真撮影においては、「必要なものを撮る」だけでなく「必要ないものを写さない」ことも重要です。
自社と関係のない企業・団体のロゴやペットボトル、パソコンのステッカーなどが写りこんでしまうことも。また、本筋とは関係のない商品名・サービス名の写り込みは避けましょう。個人情報が漏れる可能性がある社員証や書類も、よけておくのがベストです。

こちらは、余計なものが写ったインタビューカットの例です。ホワイトボードのイレーザー、となりの椅子、紙コップ、パソコン、ボールペンなどが写り込んでおり、被写体の表情や身振りが目立ちません。必要のないアイテムは、画面から除くようにしましょう。首から社員証を下げているときは、氏名や社員番号が見えてしまう可能性があるため、外してもらったほうが無難です。
一方、被写体が仕事で打ち合わせをしている姿を撮影する目的で、パソコンなどの道具とともに写す必要があれば置くなど、アイテムの配置はケースバイケースで対応しましょう。
また、最近は新型コロナウイルス感染症拡大の影響でマスクをする機会も増えていますが、撮影時にはマスクを外してもらうと、被写体の表情が見えてよいでしょう。
6.撮影許可と肖像権への配慮を忘れずに行う
イベントや社内風景、社員の写真などを外部発信する際には、必ず事前に撮影許可を取り、被写体が誰か特定できる写真の場合は肖像権に配慮しましょう。社内では撮影方針を明文化したうえで同意を得ておくこと、イベントでは受付で掲示や同意書を設けるなどの工夫が必要です。
<イベントでのご案内文例>
会場内にて、広報用の写真・映像を撮影しております。
基本的にはお顔が映らないよう配慮し、また公開時には写り込んだ方が特定されないよう編集を行います。
気になる方は、お近くのスタッフまでお気軽にお申し出ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
7. 撮影→確認→整理→共有までを1セットで考える
撮影は「撮った瞬間」ではなく「使える状態になった瞬間」に完了します。まず撮影中は、数カットごとに拡大チェックを挟み、ピント(目・ロゴ・商品名)、ブレ、写り込み、目つぶりをその場で潰します。次に撮影後、データをその日のうちに一次選定し、「掲載候補」「保管」「破棄」に分類して、迷いを翌日に持ち越さないことが重要です。
さらに、社内共有用とメディア提供用で必要な情報が異なるため、共有の形も分けて設計します。社内は「探しやすさ」が価値で、メディア提供は「使いやすさ」が価値になります。これを前提に、ファイル名やフォルダ、キャプション、クレジット、使用条件までまとめて渡せる状態にすると、写真が広報資産として回り始めます。撮りっぱなしにしない運用こそが、次回以降の撮影コストを下げ、発信スピードを上げる近道です。
【シーン別】広報担当者が知っておきたい写真を撮るポイント
広報担当者が写真撮影を担当するシーンは様々ですが、中でも機会が多いと思われる5つのシーン別に撮影のポイントをご紹介します。被写体の自然な表情を引き出したり、イベントの様子をリアルに伝えたりなど、写真の役割を果たせるように、ポイントをしっかり確認して臨みましょう。
1.インタビュー
主役となる人物がいるインタビュー記事には、魅力的なポートレートが欠かせません。ポイントときれいに撮るコツがありますので、それぞれ確認してみましょう。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 柔らかな光が差し込む部屋(窓辺)で電気を消して撮る |
| 暗めの部屋や夜間の撮影では、ストロボを活用する | |
| 被写体の目に光(キャッチライト)を入れるようにする | |
| 表情・ポーズ | 口が左右対称に開いている姿をおさめる |
| 話すときに手元が動いているカットも撮る | |
| 声をかけて、笑顔やいきいきとした表情を引き出す | |
| 基本的にあごを引いて話してもらう | |
| 角度 | 被写体の鼻やあごが目立たないよう、やや上から撮る |
| 眼鏡をかけている人は、フレームと目が重ならない角度から撮る | |
| なるべく被写体に対して平行、垂直にカメラを構える | |
| 構図 | 被写体のアップと離れたカットを両方おさえる |
| 右向き、左向き、正面の3パターンをそろえる | |
| 背景に社名ロゴやその人らしい小道具を置いて撮る | |
| 対談の場合、相手の肩や頭越しに被写体を撮る |


こちらは、明るい窓辺でストロボを使わずに撮影したインタビュー写真の例です。外の光がさし込むところで電気を消すと、自然光が壁に反射して、明るく柔らかな雰囲気の写真が撮れやすいです。被写体に声をかけて、いきいきとした表情を引き出しましょう。
自然光を利用した上記のような撮影でも、窓からの光を反射する位置にレフ板を置き、被写体に当たる光のムラを少なくするのも一計です。
2.イベントレポート
イベントレポートの場合、イベントの「全体感」と「ディテール」の両方を撮影する必要があります。キャプションがなくても何の写真なのかがわかるように撮影できるとよいですね。
また、社外からゲストを招くイベントの場合には、ゲストから撮影許可を取っておく必要があります。イベント冒頭などで、後日レポートとして写真が掲載される可能性があること、撮影を許可できない場合は申告してほしいことなどをアナウンスしましょう。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 暗い部屋では、できる限りストロボを使う |
| 照明がオレンジ色の会場では、ホワイトバランスを調節して電球モードなどにする | |
| 表情・ポーズ | 登壇者の口が左右対称に開いている姿をおさめる |
| 話すときに手元が動いているカットも撮る | |
| 複数の登壇者を写す場合は、全員の目が開いているときを狙う | |
| 角度・構図 | 来場者の撮影許可が取れない場合は、会場全体と後ろ姿を絡めて撮影しておく |
| 引きでイベントの全体感がわかるカットも撮る | |
| たくさんの人が写っているカットでイベントの盛況を伝える | |
| ディテールを伝えるため、登壇者の単独カットも撮影する |


3.宣材写真
自社の製品などを写す宣材写真の場合、手に持てる大きさのものは、柔らかい光が差し込む窓辺に置くときれいに撮れます。直射日光などの強い光については、製品の色が白く飛びやすいので、初心者には難度が高いです。
例えば商品の色や形を伝えたいのなら背景に気を配る、使い方を伝えたいのなら手に取って使用している様子を撮るなど、メッセージを明確にすると、情報の受け手にとってわかりやすい写真にできます。社内の第三者に写真だけ見せて、どのようなイメージを持つかや主題が伝わるかをヒアリングしつつ、アングルや配置を変えていくのもよいでしょう。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 柔らかな光が差し込む部屋(窓辺)で撮る |
| 角度・構図 | 手で使う製品は手に取った様子を一緒に撮るなどして、用途が想像できるようにする |
| 関係がないものの写り込みを避ける | |
| 被写体の輪郭がわかる角度・背景で撮る | |
| 必要に応じてロゴや商品名がわかるように撮る | |
| 粒や粉末の質感を伝えたいときは、中身を出してみる |

こちらは、例として「三角錐のティーバッグ」をテーマに撮影された写真です。ポイントとして以下があげられます。
- 柔らかな自然光が入る部屋で撮影
- 「三角錐」が重要なので、形がわかる角度で置く
- ティーバッグの頂点部分など、テーマの輪郭が目立つところには黒っぽい背景
- 茶葉を散らした部分にはライトグレーの背景を持ってくることでコントラストを見せる
- 用途を想像しやすいよう、実際にいれた紅茶を後ろに配置
- 茶葉の粒感・素材感がわかるように手前に散らしてみる
4.社員総会・決算説明会
社員や投資家への情報発信が目的の「社員総会」「決算説明会」。MVPが表彰されたり、経営に関する重要な情報が発表されたりと、大いに盛り上がる場ですね。こうした自社主催のイベントは「準備が8割」。リハーサルで流れや照明の位置を確認して、事前にカメラの位置やホワイトバランスを決めておくことが重要です。
ステージ付きの会場で行われることも多く、その場合はイベントレポートと似た設営になるため、注意するところも似ています。準備と撮影のとき、次の項目をチェックしましょう。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 暗い部屋ではストロボを使う |
| プレゼンテーション資料が投影されたスクリーンが写り込む場合、暗いと思ったらストロボは使わずにカメラのISO感度を上げる | |
| 表情・ポーズ | 話者の口が左右対称に開いている姿をおさめる |
| 話すときに手元が動いているカットも撮る | |
| 複数の登壇者を写す場合は、全員の目が開いているときを狙う | |
| 表彰がある場合、笑顔やいきいきした表情をおさえる | |
| 角度・構図 | 話者の単独バストアップを撮影する |
| 引きでイベントの全体感がわかるカットも撮る |
5.集合写真の場合
被写体の数が多い集合写真では、いかにすき間なく全員の顔を入れるかを考えましょう。現場で声掛けや位置の調整を行い、全員が目を開けているカットをおさえる必要があり、撮影の難度が高いものです。そのときになって慌てることがないよう、次のポイントを参考に確認しておきましょう。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 明るい部屋で撮影する |
| 暗い部屋ではストロボを使う | |
| 表情・ポーズ | 笑顔やいきいきした表情をおさえる |
| 好きなポーズを取ってもらう | |
| 撮ったらその場ですぐ確認。目を閉じている人がいたら撮りなおす | |
| 髪型や服装が乱れている人がいたら直してもらう | |
| あごを引いてもらう | |
| 角度・構図 | 角度は正面から |
| 台や脚立があれば乗り、やや上から撮る | |
| 主役がいる場合は、中心や前列に入ってもらう | |
| 人と人の距離を詰めてもらう | |
| 人数によって並び方を変える | |
| ・4人まで→横1列 ・5~8人→2列以上 など |
|
| 小柄な人は前列、大柄な人は後列に立ってもらう |

こちらは集合写真です。以下のポイントがあげられます。
- 全員の目が開いている
- 声をかけて笑顔を引き出している
- 1列目は椅子に座ってもらって低くしつつ、2列目はその間から顔を出し、3列目は台に乗ってもらって高低差を出すことで、全員の顔を写している
- 社名(ロゴ)を中心でかかげ、企業・団体の集合写真と一目でわかるようにしている
- ストロボを活用している
社内風景・日常シーン
企業の雰囲気や働く人の人柄を伝えるうえで、オフィスの様子や日常の風景を捉えた写真は有効です。ミーティング風景、執務中の様子、ランチタイムやリフレッシュスペースの活用など、自然な表情や動きのあるシーンを意識的に撮影しましょう。
重要なのは「演出しすぎない」こと。カメラ目線ではなく、あくまで普段の業務の中でのリアルな瞬間を切り取ることで、見る人に親しみやすさや信頼感を与えることができます。撮影前に片付けや整理整頓をしておくと、雑多な印象を避けられ、見せたい雰囲気をより明確に伝えることができます。
また、机の上の資料やホワイトボードなど、映り込んではいけないものがないか事前の確認を忘れないようにしてください。
| 確認する要素 | ポイント |
| 光 | 窓際など自然光のある場所を選ぶと、やわらかい雰囲気が出やすい |
| 暗い部屋ではストロボを使う | |
| 表情・ポーズ | カメラ目線ではなく、業務中の様子を自然に切り取ることで、親しみやすさや信頼感を伝える |
| 過剰なポーズは避ける | |
| 角度・構図 | 正面・斜め・俯瞰など、複数の角度から撮影し、シーンに合った構図を選ぶ |
| 人物だけでなく、空間も含めて切り取り臨場感を出す | |
| その他 | 社外秘の資料やホワイトボードの内容など、写ってはいけない情報が映り込んでいないか確認 |
| デスク周りや背景が雑然としていないか確認し、整った印象を意識する | |
| 写る人の同意も事前に取っておく・ミーティングや作業、休憩など、複数のシーンを撮っておく |
広報撮影ディレクションのコツとプロへの依頼ポイント
広報担当者が理想の写真を手に入れるためには、撮影現場でのディレクション力が問われます。ただ「撮ってもらう」のではなく、「どんな目的で、何を伝えたいのか」を明確にしたうえで、撮影の方向性をカメラマンと共有することが大切です。
最後に、撮影時に意識すべきディレクションのポイントや、社内で協力を得るための段取り、プロのカメラマンに依頼する際に押さえておきたい準備事項について解説します。
広報担当者が撮影現場で意識したいディレクションのポイント
撮影現場では、広報担当者が「どんな目的で」「どこで使用するのか」を明確に伝えることが重要です。被写体の表情や立ち位置、背景の情報量、写真に込めたい雰囲気など、具体的に伝えることでカメラマンの理解度も高まり、狙い通りの写真が撮れます。
事前に、撮影する写真の参考イメージを共有しておくのも有効です。
社内撮影時の協力依頼・段取りのコツ
社内で社員を撮影する際は、撮られる側の心理的ハードルを下げる工夫が求められます。「何に使うのか」「どこに掲載されるのか」を明確に伝え、可能であれば当日の服装や撮影時間も事前に共有しましょう。
撮影当日は時間通りに終えるよう段取りを組むことも、社内の協力を得やすくするポイントです。
カメラマンに依頼する際のチェックリスト
プロのカメラマンに依頼する際は、以下の点を事前に整理しておくとスムーズです。
- 撮影の目的
- 掲載予定の媒体
- 必要なカットのイメージと枚数
- 撮影場所と想定している所要時間
- 被写体に関する情報(人数、服装、役職など)
- 納品形式(データ形式、納期など)
- その他お願いしたい事項や注意点など
広報担当者が主体的に撮影をディレクションすることで、より目的に沿った伝わる写真に仕上げることができます。撮影当日はヌケモレが発生していないか、撮影スケジュールに遅れが発生していないかわかるような香盤表を作成するのもおすすめです。
素材を「使える状態」に整える撮影後の運用方法
良い写真が撮れていても、運用が弱いと「必要なときに見つからない」「権利が分からず使えない」「媒体に合わせたサイズがなくて急ごしらえになる」といった形で価値が落ちます。広報における写真は、掲載の一回で終わる消耗品ではなく、複数チャネルに展開して成果を増幅させる資産です。だからこそ、撮影後に「使える状態」へ整える工程を標準化しておくと、属人化が減り、担当交代や外注時にも事故が起きにくくなります。
最後に、撮影後の運用として、選定・整形・管理・提供の4点を押さえ、メディア対応まで含めて再現できる運用に落とし込みます。
写真選定:掲載目的ごとに「使う基準」を決める
選定はセンスではなく基準で行うとブレません。プレスリリース用なら「何が新しいかが一枚で分かる」「主語が明確(商品・人物・場所が迷子にならない)」「縦横の余白がありトリミング耐性がある」を優先し、SNS用なら「表情や手元など“止まる要素”がある」「スマホ画面で主役が小さくならない」を重視します。採用・社内向けは「演出過多に見えない」「人や空間の温度感がある」「写り込みリスクがない」が基準になります。
選定の実務では、同じカットの連写から微差の中のベストを選ぶ必要があるため、まずは候補を10〜20枚程度に絞り、そこから用途別に最終採用を決める二段階方式が効率的です。迷ったら「第三者がキャプションなしで理解できるか」を基準にすると、広報写真としての強度が上がります。
レタッチ:やりすぎず、明るさ・色味・トリミングで整える
広報写真のレタッチは「盛る」ためではなく「正しく伝える」ために行います。基本は、明るさ(露出)を整えて顔や商品が暗く沈まないようにし、色味は会場照明で黄ばんだり青く転んだりした分を中立に戻します。トリミングは、媒体に合わせて主役のサイズを確保しつつ、ロゴや背景がうるさくならない位置で切るのがコツです。
肌の質感を過度に加工したり、背景を不自然に消したりすると、信頼性を損ねたり「作った感」が強くなったりするため注意が必要です。また、加工の可否は媒体や文脈で判断が変わるので、社内で「許容する範囲(例:明るさ調整、色補正、トリミングまで)」を簡単にルール化しておくと、担当者ごとの差が減ります。最後に、縦横それぞれの最終形(例:横長WEB、正方形SNS、縦長ストーリー)を用意しておくと、運用が一気に楽になります。
ファイル管理:命名・フォルダ・権利情報をセットで残す
管理は「探せる」「迷わない」「使える」を満たすと機能します。
フォルダは日付×案件名(例:2025-XX-XX_新商品発表会)を基本にし、01_選定前、02_採用、03_加工済、04_提供用のように工程で分けると混乱が起きにくいです。
ファイル名は、日付_案件_内容_連番(例:2025XXXX_event_stage_001)のように、検索で引っかかる単語を入れると便利です。
さらに重要なのが権利情報で、撮影者、使用範囲(期間・媒体・二次利用)、クレジット表記、人物の同意状況を一緒に残すことです。これがないと「使っていいか分からない」状態になり、結局使われなくなります。簡単なテキストやスプレッドシートでよいので、写真と同じフォルダに「権利メモ」を置く運用を定着させると、メディア対応や再利用のスピードが上がります。
配布用パッケージ:メディア提供に必要な情報(キャプション/クレジット/使用条件)
メディア提供では、写真そのものだけでなく「使うための情報」がセットになっていることが重要です。具体的には、①写真データ(高解像度のJPEG等)、②キャプション(いつ・どこで・何を写したか、固有名詞の表記揺れなし)、③クレジット表記(必要な場合の文言)、④使用条件(転載可否、加工可否、使用期限、問い合わせ先)を一つのパッケージにします。
加えて、画像素材リンクをまとめたURLや、企業ロゴ、製品画像、代表者写真など「関連素材」も同梱できると、記事化の速度が上がります。提供時に「この写真を使うと何が伝わるか」を一文で添えると、編集側の判断が早くなり、掲載確度にも好影響が出るでしょう。
地味な作業ではありますが、このパッケージ化ができている企業ほど、露出が安定しやすくなるため、撮影後の運用として実施したい内容です。
広報真の撮り方に関するよくある質問(Q&A)
最後に、広報現場で実際に起きやすい”詰まりどころ”をFAQとして整理します。撮影の技術論だけでなく、社内調整、権利、メディア提供といった運用上の論点を一緒に押さえることで、事故を防ぎつつスピード感のある発信が可能になります。以下は、最小限のルールと現実的な対応策に絞って回答するので、参考にしてみてください。

スマホでも広報用の写真は撮れますか?最低限の条件は?
スマホでも十分に広報用の写真は撮れますが、最低条件はあります。第一に、明るい環境で撮ることが重要で、暗所で無理に撮るとノイズやブレが出て「素人感」が強くなります。
第二に、レンズを拭き、手ブレを抑え、主役にピントを合わせるという基本を徹底するだけで見栄えが大きく変わります。第三に、媒体を想定して縦横比率と余白を確保し、後からトリミングできる撮り方にすることが運用面で効きます。
イベントや人物撮影では、スマホのズームを多用すると画質が落ちやすいので、可能なら被写体に近づいて撮り、引きは別カットで押さえるのが安全です。どうしても暗い会場の場合は、照明の当たる位置に被写体を誘導し、連写でブレのない一枚を確保するなど現場設計で補うと成功率が上がります。
撮影許可や肖像権の同意は、社内でどう取ればよいですか?
社内での同意取得は、個別に毎回お願いするよりも、原則ルールを作って運用する方が安全です。
具体的には、以下の3点を明文化し、入社時または年次で同意を取る方法が現実的です。
①何の目的で(広報・採用・社内向け等)
②どこに掲載される可能性があるか(サイト、SNS、プレスリリース、資料など)
③同意の撤回や掲載停止の相談窓口はどこか
加えて、撮影当日は「今日は撮影が入る」「公開の可能性がある」ことを事前周知し、写りたくない人が申告できる導線を用意するとトラブルを減らせます。
個別案件で重要人物を撮る場合は、用途と期間、加工の有無を簡単に説明し、同意の範囲を揃えておくと後から使い回しやすくなります。運用上は「同意の有無が分かる管理」が肝なので、写真フォルダに同意状況のメモを残すだけでも実務はかなり安定します。
イベントで「写り込みたくない人」がいる場合はどう対応しますか?
基本は「写り込まない導線を用意する」「写り込んでも特定されない撮り方にする」「申し出の場を作る」の三段構えです。受付や会場入り口で撮影の告知を掲示し、スタッフが口頭で補足できると丁寧です。写り込みNGの参加者がいる場合は、撮影エリアを区切ったり、席を配慮したり、撮影時に後ろ姿中心の構図に切り替えたりして対応します。
写真の使い方としても、顔が判別できない距離感で会場の熱量を撮る、手元や展示物など人物以外のカットを厚くするなど、レポートの成立を別軸で担保できます。公開前に確認依頼が必要な運用を組むとスピードが落ちるため、可能な限り現場で「写さない設計」に寄せるのが現実的です。
どうしても写り込みが避けられない場合は、公開時にぼかし等の編集を行う選択肢もありますが、編集の可否や手間を踏まえ、事前に方針を決めておくと事故が減ります。
レタッチや加工はどこまで許容されますか?
広報では、加工は「事実を歪めない範囲」に留めるのが原則です。一般的に許容されやすいのは、明るさ調整、色味補正、トリミング、軽微な傾き補正、ノイズ低減など、見え方を整えるための処理です。一方で、製品の形状や色を実物と異なる印象に変える、人物の体型や表情を大きく変える、背景情報を恣意的に消すといった加工は、信頼性を損なうリスクが高くなります。
特にプレスリリースやメディア提供素材は、第三者が扱う前提のため、加工が強いと媒体側で使いにくくなることもあります。社内での運用としては「補正は可、改変は不可」という線引きを共有し、必要なら補正前の元データも保存するルールにすると安心です。表現上どうしても強い編集が必要な場合は、用途を限定し、広告素材などコントロール可能な領域で使い分けるのが実務的です。
伝わる写真で、広報の発信力を高めよう
ここまで、広報担当者向けのシーンを想定した写真撮影のコツをご紹介しました。写真は、「誰に、何を、どんな風に伝えるか」を手助けしてくれる、頼りになるツールです。一方で、準備が十分にできず、撮り方に気を配らないと、その効果が薄くなってしまうでしょう。
撮影の目的や、写真で伝えたい情報などをふまえ、広報担当者が主体的に準備し、関係者を巻き込んでディレクションすることが重要です。正確なディレクションで、効果のある写真を撮影してくださいね。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする