「パブリシティとは何?」「PRや広報とは意味が違うの?」「パブリシティをうまくやるにはどうしたら良いの?」広報PR担当者の中には、このような疑問を持っている人もいるかもしれません。パブリシティは、PR活動を行ううえで重要な手法のうちのひとつです。
本記事では、知っておきたい広報用語「パブリシティ」の基本的な意味から、「PR」や「広報」との違い、メリットや注意点、具体的な手法まで詳しく解説します。パブリシティを戦略的に活用し、自社の広報活動を効果的に進めていきましょう。
パブリシティとは?
パブリシティとは、自社の製品やサービス、取り組みに関する情報をメディアに発信し、報道というかたちで取り上げてもらう広報PR手法のひとつです。記者会見やプレスリリースの配信、取材対応などを通じて、新聞・テレビ・Webメディアなどに掲載されることを目指します。
英語の「publicity」は「宣伝」や「世間に対して広く知ってもらうこと」の意味で用いられますが、日本 国内の広報業界では、宣伝よりも「報道を通じた露出」というニュアンスが強く、「報道露出=パブリシティ」として使われるのが一般的です。
たとえば、プレスリリースやイベントなど、報道関係者に向けて発信した結果、ニュース掲載や報道につながった場合、「パブリシティ(報道)につながった」などのように表現します。
パブリシティには、「ノンペイドパブリシティ」と「ペイドパブリシティ」があります。
意味を簡単にまとめると以下です。
- パブリシティ:企業がメディアに情報提供し、報道として取り上げられることで得る露出全般を指す広報PR手法
- ノンペイドパブリシティ:広告費を支払わず、記者・編集者の判断で報道されるメディア露出
- ペイドパブリシティ:広告費を支払い、記事広告やタイアップとして企業主導で情報発信する露出手法
それぞれの違いについて詳しく説明します。

ノンペイドパブリシティとは
ノンペイドパブリシティとは、広告費を支払わずに報道として取り上げられるメディア露出のことです。いわゆる「無料の報道露出」であり、企業視点ではコストをかけずに認知拡大を狙える手法です。
広報PR活動においては、「パブリシティ」とは「ノンペイドパブリシティ」を指すことが多く、フリーパブリシティといわれることもあります。
ノンペイドパブリシティは、情報が記者や編集者の判断によって扱われるため、消費者にとって宣伝色が薄く、「第三者の視点」から報じられることで信頼度が高まるという特長があります。そのため、上手に活用すれば、企業のブランド力向上やマーケティングにも大きく貢献します。
ただし、掲載はあくまでメディア側の判断次第で、必ず報道につながるわけではありません。また、記事内容を企業がコントロールすることはできず、意図しない編集になる可能性もある点には注意が必要です。
ペイドパブリシティとは
ペイドパブリシティとは、メディアに対して広告費を支払い、記事や番組内で情報発信をしてもらう手法のことです。タイアップ広告、記事広告、インフォマーシャルなどもこれに該当します。
企業側が伝えたい内容を主導的に構成できるため、ブランドイメージやメッセージを的確に伝えやすいことや、掲載が確約されていることがメリットです。
なお、広報・PR業界では、「パブリシティ」と言う場合、基本的にはノンペイドパブリシティを指すため、ペイドパブリシティを「パブリシティ」と呼ぶのは誤解を招く可能性があります。注意して使い分けましょう。
「パブリシティ」と「PR」「広報」「広告」との違い
「パブリシティ」「PR」「広報」は似たような文脈で使われることが多いものの、それぞれ担う役割や意味は異なります。混同されやすいため、あらためてその違いを正しく整理しておきましょう。
PR(パブリック・リレーションズ)との違い
PRとは「Public Relations(パブリック・リレーションズ)」の略で、企業や団体が社会全体や特定のステークホルダー(顧客・株主・地域社会・従業員など)と良好な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動全般を指します。単なる情報発信にとどまらず、信頼構築やイメージ形成も含む広範な概念です。
その中でパブリシティは、PR活動の一部として位置づけられやすく、メディア露出を通じて社会に情報が伝わることで、信頼や認知の獲得に寄与します。
ただしPRは「関係性の設計」そのものが目的であるのに対し、パブリシティは「報道として取り上げられる」という結果に近い概念です。そのため、PRの全体戦略が不在のままパブリシティだけを追うと、短期の露出は得られても、社内外で伝えるべき価値が揺れたり、問い合わせ対応や採用広報など他活動との整合が崩れたりしやすい点に注意が必要です。
広報との違い
広報はPRの一部に位置づけられ、企業や団体がメディアや社会に対して情報を発信する役割を担います。プレスリリースの配信、メディア対応、社内報の制作など、外部・内部への情報伝達を通じて、PR活動の一翼を担う実務的な機能です。
| 用語 | 概要 |
| PR(パブリック・リレーションズ) | 社会やステークホルダーと信頼関係を築くための戦略的活動全般(考え方および行動) |
| 広報 | PRの一環。情報発信を通じてステークホルダーとの望ましい関係をつくり出す活動 |
| (ノンペイド)パブリシティ | 広報PR活動の一環。メディアにお金を払わずに、報道という形で情報を取り上げてもらうこと |
パブリシティは、その広報活動の成果として「記事になった」「番組で紹介された」といった露出が生まれた状態を指し、広報の業務範囲そのものではありません。
たとえば、丁寧な取材対応や素材提供、背景説明を行うのは広報の役割であり、その結果として報道が成立したときに「パブリシティを獲得した」と表現します。実務上は、広報はコントロールできる部分(事実情報、素材、コメント、提供の速さ)を最大化しつつ、コントロールできない部分(掲載有無、切り口、尺、見出し)を前提に設計する仕事だと捉えると、社内説明や期待値調整がしやすくなります。
こちらの記事で、「広報」と「PR」と「広告」の違いを詳しく説明しているので、気になった人は確認してみてください。
広告との違い:コントロール可否と信頼性の差
広告は、掲載枠や配信面を購入し、伝えたいメッセージを自社主導で設計して届ける手段です。ターゲティング、表示回数、期間、クリエイティブなどを比較的コントロールできるため、再現性とスピードに強みがあります。
一方、パブリシティは報道として扱われるため、掲載可否や扱いの大きさ、表現、文脈は原則としてメディア側の判断に委ねられます。その代わり、第三者がニュース価値を認めて取り上げたという構造が生まれやすく、受け手に「宣伝ではなく情報」として受け取られることで信頼を獲得しやすい側面があります。
実務では、広告で認知の土台を作り、パブリシティで信頼と話題化を積み上げ、PR全体として関係性を深める、といった組み合わせが有効です。重要なのは、目的と制約に応じて手段を選び、社内外に同じ言葉で説明できる状態を作ることです。
パブリシティ活動に取り組む3つのメリット
広報PR担当者がパブリシティを獲得するため、メディアにアプローチすることを「パブリシティ活動」といいます。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。こちらでは、パブリシティ活動を行う利点について、ご紹介します。
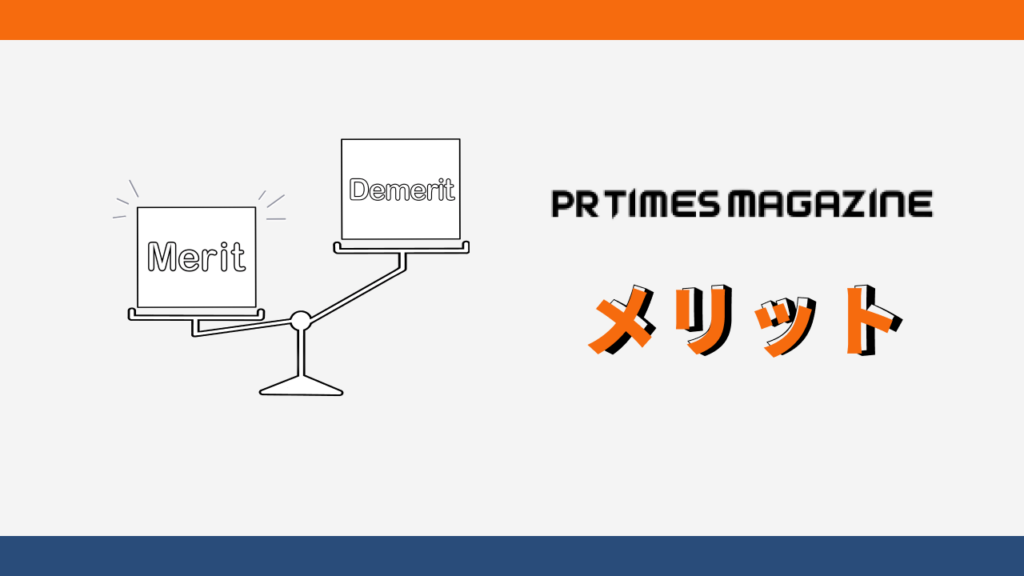
メリット1.メディアを通じて、多くの人に情報を伝えられる
生活者がプレスリリースを直接読むこともありますが、メディアにニュース記事などとして掲載されると、より多くの人に自社の情報を届けられます。
また、特定の分野に特化したメディアに掲載された場合、その分野に興味がある人にも広く情報を届けることができます。認知度を上げ、情報を届けたい相手にリーチしやすくなる点から、メディア掲載は重要な広報PR活動のひとつです。
メリット2.予算がなくても実施しやすい
パブリシティ活動は、多額の予算を組む広告とは異なります。予算の有無に関わらず、メディアと適切なコミュニケーションを取りつつ行う手法であるためです。
注意すべき点は、パブリシティ=「無料の広告」ではないことです。報道は広告ではなく、読者に価値ある情報・ニュースを届ける役割があります。そのため、取材でやりとりした情報の中から、メディア側の編集部が取捨選択し、企業にとって都合の良い内容を省くこともあります。
広告と違って、パブリシティは企業が掲載の有無や内容をコントロールできないのが通例です。広報PR担当者は、メディアが提供するニュースバリューを理解したうえで記者と関係を構築し、広報PRのネタを提供しましょう。
メリット3.第三者視点による企業の信頼性が高まる
メディアに取り上げられるということは、第三者から認められているということ。まったく聞いたことのない企業よりも、取材を受けていたり、日ごろ目にしたりする企業のほうが、信頼できます。
全国紙やキー局の番組など、有名なメディアに露出があれば、全国区で企業の信頼度が高まります。特定の分野に強い専門メディアに掲載されれば、その分野で知名度を獲得できます。
社会から信頼されることは、長期的には広報PRの目的でもある「ステークホルダーとの望ましい関係構築」に役立つといえるでしょう。
広報PR担当がパブリシティを行う5つのアプローチ方法
では、広報PR担当がパブリシティを行うにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、すぐに実践できる5つのアプローチ方法をご紹介します。
1.プレスリリース配信による取材機会の創出
プレスリリースには企業の新しい情報が詰まっているため、メディアの記者は届いたプレスリリースを見て取材を申し込むことも多いです。自社を取り上げてほしいという希望があれば、個別にプレスリリースを送ってみましょう。
自社のプレスリリースを送付する先をまとめた「メディアリスト」を作成することも有効です。
メディアの記者は日々、数十~数百枚のプレスリリースの中からニュースとなるトピックを探しています。プレスリリース配信は、パブリシティを獲得する手段のひとつとしてもっとも代表的といってもよいでしょう。
2.記者会見・説明会での直接的な情報提供
記者会見や説明会を開催することも大切です。プレスリリースの文章だけでは伝わりにくい製品・サービスの魅力、企業の雰囲気を直接伝えることができます。
会場で自社の開発担当者と記者が交流したり、実際の商品を展示したりすることも可能です。こうした場合は、記者会見がそのまま取材の場となることもあり、パブリシティを獲得するチャンスとなります。
3.記者に実物・現場を体験してもらう
記者が商品を手に取る機会を設けることも重要です。食品やコスメなど、実物を見たり使用したりすることで良さが伝わる商品のアピールに適しています。
新商品のテスターやサンプルをメディアに送付するか、直接会うタイミングで実際に渡すなどすることで、色、食感、機能などを直感的に理解してもらいやすくなります。
加えて、先方が商品やサンプルを撮影できるため、写真や映像と一緒に紹介してもらえる可能性も高まります。
4.メディアの文脈に合わせた企画提案
広報担当者がメディアに企画を提案するのも一計です。
たとえば情報を発信する際に「ひとつの新商品・取り組みではエピソードが弱い」「かなり前から売っている商品だが、最近流行のジャンルかも」などと思ったことはありませんか。
ニューストピックは切り口次第で露出が増えます。上記の例では、市場規模などのファクトとなるデータとともに新製品の強みを紹介したり、流行に沿った文脈で既存の商品を紹介したりしても良いかもしれません。
ある程度、メディアの記事やコーナーの趣旨なども理解したうえで「何がニュースとして取り上げてもらえるか」を考えることが理想です。
パブリシティを増やせそうな企画を自ら作り、メールや対面で記者に提案してみましょう。
【参考記事】
新聞掲載につなげる広報活動とは?取り上げやすいネタや6つのテクニックを解説
テレビ露出・取材につなげる広報活動とは?元番組制作スタッフが教える7つのテクニック
雑誌に掲載してもらう4つの広報テクニックとは?
5.ランキングや公募、企画に応募する
メディアが主催するコンペや賞に応募する方法もあります。
メディアでは優れた発信やサービスなどを紹介するため、独自の広告賞や製品賞を設けていることがあります。新規の発信を行うプレスリリースとは異なり、過去数ヵ月~数年の実績で応募できることもあり、入賞すると露出が増える可能性があります。
広報PR担当者は気になるメディアのコンペや賞を常にチェックして、応募できそうなコンテンツがあれば積極的に応募してみてください。

広報PR担当がパブリシティを行うときに知っておきたい3つの注意点
次に、広報PR担当者がパブリシティを行うときに知っておきたい注意点を説明します。パブリシティは広報PR担当者とメディア側の思いが一致して初めて成り立つもの。注意点をきちんと押さえてから取り組みましょう。
注意点1.広告ではなく報道であることを理解する
パブリシティは、お金を払ってつくる「広告」とは異なり、メディアを通じた「報道」の一部です。報道においては、自社のアピールよりも客観性とニュースバリューが重視されることを忘れないようにしましょう。
必要な情報はすべてプレスリリースや、それに付帯する情報として過不足なく伝える姿勢が重要です。電話・メールを通じた記者からの事実確認にも、できるだけ丁寧に対応しましょう。
内容に誤りがあった際に、メディア側に事実関係の誤認とミスがあれば、文言調整・画像差し替えなどの対応をしてもらえることもあります。ただ、企業が追加で要求する調整は、かなり通りにくいです。
広告と異なり、パブリシティの主体はメディアであることを忘れないようにしましょう。
注意点2.意図と異なる切り口で報じられる可能性もある
自社のさまざまな情報をメディアに提供してパブリシティの機会を増やすこと、社外に出る情報をコントロールすることが広報PR担当者の仕事です。
パブリシティの主体はメディア側にあり、基本的に未公開情報は「ニュース」として取り上げられやすいです。取材で話したことは、こちらの一存で「オフレコ」にはできないことを強く意識し、情報管理を徹底しましょう。
また、良くも悪くもニュースとなるトピックを主軸に取り上げられることを覚悟しましょう。たとえば新製品なら「今までになかった製品か」「このタイミングで取り上げる意味があるか」といった視点で切り取られて、ほかの部分をうまくアピールできないこともあります。
注意点3.メディアと企業の双方の思いの重なりで成立する
メディアは企業の広報PRのためではなく、原則として読者や生活者、社会のために報道を行います。
時にはメディアに意図していない部分を紹介されたり、互いの利益が反目しあったりすることもあるでしょう。重要なのは、そのような前提を理解し、日ごろからメディアとの信頼関係を構築することです。
報道は、うれしいニュースばかりではありません。たとえば景気の冷え込みや災害などといった切り口で申し込まれる取材もあります。新製品の紹介だけでなく、こうした社会的なテーマでも情報を提供することも、メディアからの信頼を積み上げることにつながります。
信頼感を高めつつ、メディアが必要とするニュースと自社の広報PRが重なり合う部分を探しましょう。そのコミュニケーションの中で、自社の思想や製品のコンセプトなども理解してもらえるよう、根気強く伝えていくことが大切です。
パブリシティに関するよくある質問(Q&A)
最後にパブリシティに関して、混同が起きやすい用語の違いを整理しながら、実務の判断に直結するポイントに絞って解説します。

中小企業やスタートアップでも実践できますか?
もちろん実践可能です。規模が小さい企業は、全国的な知名度や広告予算で勝負しにくい一方、尖った課題設定やユニークな技術、地域性、創業者のストーリーなど、編集部が好む「語りやすい要素」を持っていることが多いからです。
実践のコツは、プロダクトの機能説明よりも、社会にとっての意味や変化を先に語ることにあります。たとえば「誰のどんな不便が、どう改善されるのか」「なぜ今それが必要なのか」を明確にし、数字や利用者の声で裏付けを取ると、扱われる可能性が高まります。また、最初から全国媒体だけを狙わず、業界専門媒体、地域メディア、テーマ特化のWebメディアなど相性が良い媒体から実績を積み上げることで、次の露出を呼びやすくなります。
パブリシティの成果はどう測ればよいですか?
成果測定は「露出の量」と「事業インパクト」の二層で設計すると、社内合意が得やすくなります。まず露出の量としては、掲載件数、媒体の質、掲載面(トップ、特集、コラム)、到達推定、SNS拡散などを整理します。
ただし、件数だけを追うと薄い露出の量産に偏りやすいため、次に事業インパクトとも接続します。具体的には、指名検索数の増減、公式サイトの流入、問い合わせ件数、資料請求、採用応募、取引先からの反応、SNSフォロワー増など、目的に合わせた指標を設定することが一般的です。BtoBであれば、記事露出後の商談化率や名刺獲得、ウェビナー参加なども有効です。
最終的には、パブリシティ単体で完結させず、露出後の導線(LP、ホワイトペーパー、問い合わせ窓口、採用ページ)を整備し、測れる形にしておくことが、評価の精度と次回改善のスピードを上げます。
メディア関係者と良い関係で共に情報発信を
今回の記事では、パブリシティに関するメリットや注意点について説明しました。広報PRの目的でもある「ステークホルダーと望ましい関係を築く」ためにも、パブリシティが果たす役割は大きく、日ごろからメディアリレーションを丁寧に行う必要があります。
企業にとってパブリシティは、メディアを通じてたくさんの人に情報を届けられるメリットがあります。メディア側にとっても、読者のためになる記事を作るために企業から発信される情報は大切です。
パブリシティの意味や役割をしっかりと理解して、メディアと企業の双方にとってプラスとなる広報PR活動を行うよう意識しましょう。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする


