2019年に順次施行をスタートし、さまざまな業種・業態で取り組みが進められている「働き方改革」。働き方の柔軟な選択のために多様な制度を取り入れる企業も多く、今後も継続的に重要視される活動といえるでしょう。
今回は、働き方改革の具体例を32件ピックアップします。エンゲージメントを向上する施策から、働き手の心身を守る制度利用まで、さまざまな取り組みの中から自社に有用な活動を検討してみましょう。後半では、企業の実際の取り組みと広報PR戦略についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
働き方改革とは?背景と実施する重要性
厚生労働省は「働き方改革関連法」を施行し、多くの企業がこれに基づき取り組みを進めています。テレワークや休業・休暇制度などさまざまな取り組みが挙げられますが、共通する目的は「働き方の多様化」です。具体的な取り組みをご紹介する前に、まずは働き方改革の概要と、その必要性・目的について解説します。

働き方改革とは
「働き方改革」とは、働く人々が柔軟な働き方を自由に選択できるようにするための改革です。2018年7月6日に「働き方改革関連法(改正労働基準法)」が公布され、翌年4月1日に施行。働き方改革関連法により、厚生労働省は以下の3点を義務化しました。
- 時間外労働の上限規制
- 年次有給休暇の確実な取得
- 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引き上げ
労働時間法制や雇用形態などを見直し、働き手の多様なワークライフバランスに対応することが主な目的です。義務化された制度のほかに、「フレックスタイム制」をはじめとする企業が選択可能な施策も複数あります。
企業が働き方改革に取り組む重要性
働き方改革が重要視されるようになった背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少や育児・介護と仕事の両立といった社会的な問題があります。過剰労働の防止を含め、働き手の生活を守るためには以下のような課題にも目を向けなければなりません。
- 長時間労働の是正
- 正規と非正規の格差解消
- 高齢者の就労促進
さまざまな取り組みが促進されている一方で、時間外労働・人材不足といった課題を抱える企業も多く見られるのが現状です。さらなる周知・達成率の向上を目指すためには、環境改善など企業による積極的な取り組みが必要不可欠といえるでしょう。
働き方改革の32の取り組み具体例
働き方改革に関連する取り組みは非常に多様であり、複数を組み合わせることで相乗効果が得られるものもあります。すでに導入している制度を再考することで、より良い社内環境作りにつながる場合もあるでしょう。ここからは、働き方改革の具体的な取り組みを4つのカテゴリに分けて、計32の施策の特徴やメリットをご紹介します。
働く時間の最適化・柔軟化に関する取り組み例12選
個人のライフスタイルに合わせた労働時間を適用できるよう、フレックスタイムや時差出勤をはじめとするさまざまな制度が取り入れられています。出勤・退勤時間を調整する制度のほか、育児休暇や介護休暇といった中長期休暇も働き方改革における重要な取り組みです。働く時間に関する12の制度や取り組みをご紹介します。
※「▶」を押すと内容が表示されます
1.フレックスタイム制度:労働時間・休憩時間を規定内で選べる
1ヵ月以内の一定期間に総労働時間を定め、コアタイム・フレキシブルタイムの条件に応じて労働スケジュールを選べるのが「フレックスタイム制度」です。コアタイムの時間帯であれば、家事育児などのライフスタイルに合わせて労働時間・休憩時間を自由に調整できます。
企業によってはコアタイムを定めないケースもあり、この場合は労働時間の自由度を高められるのがメリット。またフレックスタイム制度の条件は、企業単位ではなくグループ・課・個人ごとに異なる場合もあります。
2.時差出勤制度:複数の選択肢から出勤時間を選べる
時差出勤制度は、原則的な出勤時間以外のスケジュールを設けて選択肢を広げる取り組みです。交通網が混雑しやすいラッシュの時間帯を避けることで、車・電車・バスといったあらゆる利用者を分散させる目的があります。
1日あたりの勤務時間を調整できるフレックスタイム制度に対し、労働時間が固定化されている点が時差出勤制度の特徴。働き手自身の都合に合わせるだけでなく、取引相手とのスケジュールに応じて出勤時間を調整できるのも魅力です。
3.短時間勤務制度(時短勤務):1日最長6時間の勤務
「短時間勤務制度(時短勤務)」は、名前の通り本来よりも短い労働時間内で勤務する制度。子育てや介護と仕事を両立できるよう、「育児・介護休業法」によって策定されました。
1日あたり5時間45分~6時間の所定労働時間を設けており、フルタイムよりも数時間遅く出勤、または早く退勤できるメリットがあります。時短勤務を希望する場合は事前申請が必要ですが、複数の条件を満たしている状態でなければなりません。
4.選択的週休3日制:1週間に3日の休日を設ける
原則週休2日である勤務スケジュールを変更し、1週間に3日休めるよう対応するのが「選択的週休3日制」です。法的に義務化されている制度ではありませんが、働き手のワークライフバランスを充実させる施策として政府が推進しています。
給与が減少するケースや労働時間の増加など、休日の取り方は企業によってさまざまです。
5.残業の原則禁止・事前申請制:企業と働き手双方の負担を軽減
労働基準法の改正により、残業時間に月45時間、年360時間の上限が設けられました。しかし「想定よりも多く残業してしまった」「上限内で業務を完了できない」といった問題もあり、残業そのものを原則禁止とする企業も見られます。
定時退社を原則とし、やむを得ない場合は事前申請により残業を許可するケースも。このような取り組みは働き手の負担を軽減するだけでなく、予算管理をはじめとする経営面で企業側にもメリットがあります。
6.ノー残業デーの設定:残業しない日を設ける
「ノー残業デー」は、普段残業を許可している企業が定時退社を促す日のこと。部署単位で行われることもあり、頻度や曜日は業務量によって異なります。
内閣府は週の中日である水曜日の実施を推奨しており、実際に定期的なノー残業デーを取り入れている企業も少なくありません。残業時間減少による負担軽減のほか、「残業しないと間に合わない」といった課題があったときに体制を再考するきっかけにもなる取り組みです。
7.有給休暇の計画的取得促進:働き手の有給休暇を事前に割り振る
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇を計画的に割り振り、有給休暇取得率を高める取り組みです。働き手はあらかじめ決められた休暇の過ごし方を検討しやすくなり、企業側は計画的な業務運営に取り組めるというメリットがあります。
対象となる有給休暇は、全体のうち5日を超える部分です。病気など個人的な理由が発生する可能性を考慮し、最低5日間は自由な有給休暇として残さなければなりません。
8.産前産後休業・育児休業:事前申請で出産・子育てに専念できる
労働基準法では、母体保護を主な目的に「産前産後休業(産休)」と「育児休業(育休)」が定められています。基本的な規定は以下の通りです。
また「パパ・ママ育休プラス制度」と呼ばれる取り組みもあり、父母が両方取得する場合は1歳2ヵ月まで取得できます。
9.出生時育児休業(産後パパ育休):男性の育休取得推進
育児休業と別に取得できる休暇制度として、2022年10月に「出生時育児休業(産後パパ育休)」が施行されました。子どもの出生日を基準に、最大28日間取得できる休暇制度です。
休暇中は産休の出産手当金や育休の育児休業給付金と同じく、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が受け取れます。共働き世帯が増える現代において、父親にフォーカスした休暇制度は働き方改革の重要な取り組みのひとつといえるでしょう。
10.子の看護等休暇:育児と仕事を両立するための休暇制度
育児・介護休業法で定められている「子の看護等休暇」は、子どものケガや病気といった理由がある場合に取得できる休暇制度です。育児と仕事を両立できるよう、2025年4月1日から段階的な法改正が施行されました。
11.介護休業・介護休暇:介護離職の課題解決に向けた取り組み
育児・介護休業法のうち、介護が必要な家族がいる場合に中長期的な休みを取得できるのが「介護休業」です。対象家族1人につき3回まで、計93日の休業日を申請できます。介護休業給付が支給されるため働き手の生活が保障でき、介護による離職率減少にもつながるでしょう。
一方「介護休暇」は、年間最大5日の休暇が取れる制度。要介護の家族がいる場合は最大10日間申請できます。短期間ではあるものの、通院の付き添いや介護関係の手続きなど、休まざるを得ない場合に有効活用できる制度です。
12.特別休暇:企業独自の休暇制度でワークライフバランスを整える
出産・育児や介護を事由とする休業・休暇制度のほか、「特別休暇制度」として企業独自の取り組みを進めるケースも多く見られます。「誕生日休暇」や、特定の理由を問わない「リフレッシュ休暇」が一例です。業種や運営方針などに応じて休暇制度を導入することで、ワークライフバランスを充実させられるでしょう。 例えばPR TIMESでは、2025年3月1日に「サバティカル休暇制度」を新設しました。対象の正社員・契約社員が23日間の連続休暇を取得し、業務代替者には1人5万円の賞与を支給する特別休暇です。業務から完全に離れる期間を設けることでリフレッシュし、自分や家族と向き合うきっかけ作りにもなっています。
働く場所の多様化に関する取り組み例5選
新型コロナウイルスによる自粛生活を受けて、自宅での労働を許可したり、コワーキングスペースの利用を支援したりといった取り組みを強化した企業も多いのではないでしょうか。働く場所を多様化することで、働き手のストレス軽減や人材確保といったメリットを享受できるでしょう。働き方改革における就業場所の取り組み例をご紹介します。
13.テレワーク(在宅勤務):通勤が不要な働き方
働き方改革に加え、コロナ禍で注目度を高めたのが「テレワーク」です。働き方改革の代表的な取り組みでもあり、テレワークを積極的に導入する企業も見られるようになりました。自宅で就業できるため通勤が不要になるのがメリット。働き手のストレス軽減に有用な取り組みのひとつといえるでしょう。
自宅で作業できる範囲には限りがあるためすべての業種で導入するのは困難ですが、環境を整えられる業種であれば、地域を問わない人材確保にも効果が期待できます。
14.サテライトオフィス:本拠から離れた場所にオフィスを設置
企業・団体の本社や通常のオフィス以外の場所でも働けるよう、本拠から離れた場所に設置されるのが「サテライトオフィス」です。サテライトオフィスを設置するエリアは都市部・地方・郊外と企業により異なりますが、いずれも働く場所の多様化を目的としています。
例えば地方在住の働き手が都市部の企業に就職した場合、地方にサテライトオフィスがあれば自宅から近い場所で勤務が可能です。育児・介護と仕事の両立といったワークライフバランスにもつながるため、働き方改革の重要な取り組みとして注目されています。
15.ワーケーション/プレジャー:仕事と休暇・余暇の両立
「ワーケーション」とは、「Work(仕事)」「Vacation(休暇)」を組み合わせた造語で、言葉の通り仕事と休暇の両立を目的とした取り組みです。一定期間地方で勤務して現地の人々と交流を深めたり、便宜的なテレワークで長期休暇を取得したりといった例があげられます。
また、類似の取り組みとして知られる「プレジャー」は、「Business(ビジネス)」「Leisure(レジャー)」を組み合わせた造語。出張先での滞在期間を延長し、余暇を楽しむことで仕事との両立につなげる取り組みです。
16.移住支援金制度:地方移住を伴うリモートワークをサポート
一時的な出張や地方でのテレワークではなく、移住を検討する働き手も増えています。全国各地の市町村が地方創生移住支援事業を展開しており、地方への移住により交付金を受け取れる「移住支援金制度」の適用が可能です。
働き手の移住を企業側がサポートすることで、離職率低下や人材確保といったメリットにつながるでしょう。企業と地域が連携し、地方にサテライトオフィスを展開したりフルリモートを導入したりといった事例も見られます。
17.コワーキングスペース:支援補助金の活用で働く場所を多様化
特定の企業関係者にかかわらず、さまざまな人が利用できるよう運営されているのが「コワーキングスペース」です。起業後間もない経営者やフリーランサーが主な利用者ですが、近年では企業の従業員が利用する機会も増えています。
全国各地で「コワーキングスペース支援補助金制度」を設けており、施設の新設や利用など条件に応じて補助金の受け取りが可能。企業がコストを押さえながらコワーキングスペースを活用することで、地方でオフライン会議を実施したり働き手の就業場所を多様化したりといった働き方改革に取り組みやすくなるでしょう。
労働環境・業務効率化に関する取り組み例5選
ITツールの導入やチャットツールの活用といった取り組みは、働き方改革における重要な施策です。働き手個人のリソースが増えるだけでなく、企業全体の業務効率化も期待できるでしょう。労働環境の見直しや業務効率化に関する取り組みの例を5つご紹介します。
18.ITツールの導入:顧客管理や経理などの業務を効率化
既存業務の効率化を図る手段として有効なのが「IT化」です。ITツールを導入することで、顧客管理・経理・営業管理などあらゆる管理業務を効率化できるのがメリット。特に昨今では「インボイス制度」「電子帳簿保存法改正」といった政策も進んでおり、IT化は企業にとって欠かせない取り組みともいえます。
厚生労働省が「業務改善助成金」を実施しているため、助成金制度を活用できればコストを抑えた働き方改革の一助となるでしょう。
19.組織内DX課:RPAなどで企業・組織体制を変革
働き方改革で企業が取り組める施策として「DX化」があげられます。デジタル技術による業務効率化を目的としたIT化とは異なり、企業文化や組織体制そのものの変革を目指すのがDXです。
本来人間が行うパソコン作業をロボットに任せる「RPA」をはじめ、複数の方法を組み合わせてDX化を進めていきます。組織内改革により業務効率・生産性が向上することで、事業改善だけでなく新たな事業開発を進めるきっかけにもなるでしょう。
20.タスク管理やチャットツールの活用:(Slack、Notionなど)
個人・団体を問わずさまざまな場面でチャットツールが利用されていますが、企業に導入する事例も見られます。「Slack」「Notion」「チャットワーク」といったサービスはビジネス向けプランも展開しており、働き方改革を進めるうえで重要なツールです。
上記のような施策はメールに比べて取り組みやすく、処理プロセスが少ないため時間コストの削減につながります。
21.会議場所・時間の見直し:時間短縮や事前共有で負担軽減
部署内での会議やチームミーティングは重要な業務のひとつですが、「どこで実施するか」「どのくらい実施するか」を見直すことで業務効率につながる可能性があります。働き手はもちろん、経営層の負担を減らして個人業務の時間を増やすためにも必要な取り組みといえるでしょう。
たとえば小さなオフィスで会議場所の確保に手間取っている場合は、コワーキングスペースの活用で解決が見込めます。テレワークを導入している企業であれば、ZOOMなどのデジタルツールを用いてオンライン会議を実施するのも一案です。
22.オフィス内フリーアドレス:インナーコミュニケーション強化やコスト削減
多用な働き方に対応するために有用な方法のひとつが「オフィス内フリーアドレス」。オフィス内の作業デスクを固定せず、働き手が好きな席を選べるような環境を整える取り組みです。物理的な作業を伴わない、または少ない業務において有用な施策といえます。
オフィス内のインナーコミュニケーションを強化しやすい点が主なメリットですが、スペースの有効活用やコスト削減といった利点も魅力です。従業員数や業務内容により課題が生じる可能性はあるものの、IT化・DX化の恩恵を有効活用した働き方改革といえるでしょう。
人材活用に関する取り組み例3選
労働の中心となる生産年齢人口が減少傾向にある昨今においては、人材活用の取り組みを強化することも重要です。育児・介護で退職した人を再雇用したり、シニア人材を採用したりといった施策は企業側にもメリットの大きい取り組みといえるでしょう。再雇用をはじめ、人材活用に関する取り組みの例を3つご紹介します。
23.出戻り支援:退職した元従業員の再雇用
何らかの理由で退職した元従業員をあらためて雇用する支援制度も、働き方改革に必要な取り組みです。「出戻り支援」「再就職支援」などの名称で知られており、一定の要件を設けて雇用を進める企業も見られます。
子育てや介護など、家庭の事情でやむを得ず退職した働き手にとって非常にメリットの大きい取り組みです。また、企業に理解のある元従業員を再雇用することで、優秀な人材とともに事業を続けられるという企業側のベネフィットも見込めます。
24.定年後人材の積極採用:定年後の採用で人材確保
人材確保を主な目的として、定年後の人材を採用する企業も見られます。専門知識や長年培った技術を持つシニア人材の雇用は、企業側にとってもメリットの大きい施策です。
シニア人材の再雇用のほか、業務委託制度を適用するケースもあります。生産年齢人口の減少が危惧される昨今において、年齢上限を引き上げて採用を検討する雇用制度も必要性を高めているといえるでしょう。
25.副業・兼業:将来を見据えて選択肢を増やす取り組み
厚生労働省は、複数の仕事を掛け持つ「副業・兼業」を促進しています。副業で起業の手段を見つけたり、人生100年時代における第2の人生の準備をしたりといった活動につなげることが目的です。
また、企業によっては「社内副業」を導入し、担当以外の部署や業務を担う取り組みを進めているケースもあります。働き口の選択肢を増やす制度は、将来的な人材育成や自由度の向上にも効果が期待できるでしょう。
意識改革・組織風土の醸成に関する取り組み例7選
企業理念を根底から考え直したり問題点を明らかにしたりするためには、従業員だけでなく管理職にも目を向けなければなりません。エンゲージメント調査やメンタルヘルスケア支援制度などを導入できれば、従業員が抱える悩みをもとに改善策を検討できるでしょう。意識改革・組織風土の醸成に関する取り組み例を7つご紹介します。
26.管理職向け研修:効率化やマネジメントを学ぶ
研修制度は多くの企業が取り入れていますが、管理職にフォーカスした取り組みを検討するのも働き方改革の一案です。管理職を対象とした研修プログラムを組むことで、業務効率化に有効な手段を提案したり、従業員のマネジメントを学ぶ機会になったりといったメリットを発揮します。
社内研修として展開するほか、外部に委託して研修に参加するケースも。管理職の人々が時代に応じてアップデートする機会を設けることで、意識改革・組織風土の醸成につなげられるでしょう。
27.ハラスメント対策の強化:働き手を守るための取り組み
近年特に話題に挙がることが多い「ハラスメント」は、企業にとって大きな課題のひとつともいえます。企業全体で対策を強化できれば、社内環境を改善するきっかけとなり全体的な意識改革へとつながっていくでしょう。
モラルハラスメント、パワーハラスメントなどいくつかのハラスメントがありますが、いずれも問題を明らかにして解決を目指すプロセスが重要です。特にカスタマーハラスメントにおいては、行動指針を見直すことで働き手の尊厳を守る結果につながります。
28.エンゲージメントの調査・改善:働きがいを調査し改善を検討
定期的な社内調査を実施する企業は多く見られますが、働き方改革にも役立つ場合があります。社内の関係者に向けて「働きがい」を中心に調査することで、全体のエンゲージメントを可視化できるためです。
改善の余地がある不満・不足が見られれば、業務改善・制度刷新などあらゆる施策を検討できます。組織風土を改めることで、人材を失うリスクを低減する結果にもつながるでしょう。
29.ダイバーシティ&インクルージョン:働き手の多様性を受容する取り組み
人種・ジェンダー・伝統といった多様性を意味するのが「ダイバーシティ」、それを否定せず、特性を活かせるよう受容するのが「インクルージョン」です。LGBTQをはじめ、あらゆる人が自由な選択肢を持つための考え方で、働き方改革においても重要視されています。
表面的な否定要素がなくなるため、優秀な人材を確保しやすくなるのがメリット。多様性を認めることで働き手の負担が軽減できるだけでなく、新たな人材をきっかけとする新商品の開発や、離職率低下・定着率向上などの効果も期待できます。
30.キャリア相談窓口の設置:専門家に相談してキャリアを守る
働き手個人のキャリアを守るための取り組みとして、キャリア相談窓口を設置するケースがあります。自身のキャリアを専門家の視点から客観的に考える機会になるため、キャリアアップに有効な支援制度です。
「社内の相談窓口は心理的に不安だ」という意見がある場合は、社外に委託して機会を設けることもあります。働き手の現状を肯定し、さらに将来的なキャリアアップ・人材育成につなげることでモチベーションも高まり、働き手・企業双方が恩恵を受けられるでしょう。
31.メンタルヘルスケアの支援体制:EAPなどで不調にアプローチする
健全で効率的な業務体制を維持するためには、働き手のメンタルヘルスケアも重要です。労働安全衛生法の改正により、50人以上の事業場には年1回のストレスチェックが義務付けられました。心身の健康を維持するだけでなく、ハラスメントを予防したりリスクマネジメントを強化できたりといった効果が期待できます。
メンタルヘルスケアに関する取り組みはさまざまですが、例えば「EAP(従業員支援プログラム)」は身体・精神両方の健康を支援するプログラムです。定期的な支援により不調への早期アプローチが可能となるため、ストレスによる休業・退職者を減らす結果にもつながるでしょう。
32.社内コミュニケーション施策:社内SNSなどで交流を深める
働き方の多様化を進めるうえで、社内コミュニケーションを充実させる取り組みは必要不可欠といえます。「テレワークの同僚に情報共有できていない」「育休取得者から引き継ぎが終わっていない」といった問題を未然に防ぎやすくなるためです。
普段の業務で共有を徹底するだけでなく、社内SNSを活用したり交流会を開催したりといった施策も検討できます。社員同士で雑談を交わす機会が増えれば、気軽に意見を出しやすい環境が整うかもしれません。
働き方改革に取り組む企業の具体例・事例5選
ここからは、実際に働き方改革に取り組む企業の具体例をご紹介。自由な働き方を実現するさまざまな取り組みをピックアップしています。働き方改革に関する制度導入を検討中の方はもちろん、今後さらなる取り組みの展開を想定している企業の方もぜひ参考にしてみてください。
事例1.職人が主役でいられる環境整備を強化
立ち食いスタイルの江戸前寿司店「魚がし日本一」を運営する株式会社にっぱんは、2025年6月13日の新店舗オープンにあたって待遇強化策を導入しました。これまで自社で実施していた制度をさらに拡充し、技術習得の環境整備や週休3日制といった取り組みを展開しています。
「職人が主役でいられる環境」の実現に注力することで、長時間労働・低賃金の業界イメージを払拭する働き方改革でもあります。従業員にとってメリット・ベネフィットの多い制度を強化することで、店舗拡大や離職率低下にアプローチした事例です。
参考:魚がし日本一>寿司職人の働き方を見直す人事方針を新たに策定|週休3日制・高水準給与で制度改革を推進
事例2.副業可・独立可や再雇用制度など自由な働き方を提案
従業員の多様性に応える人事制度を策定しているサイボウズ株式会社。2012年には副業・独立を認め、現在までさまざまな働き方改革に取り組んでいます。
「100人100通りの働き方」という考え方を重要視し、時間や場所を選ばない自由な働き方を実現した企業です。自社独自の制度「育自分休暇」を制定し、一度離職しても6年間は受け入れが可能で、再雇用後にさらなる活躍の場を設けています。
参考:同じ価値観を持っている人はいない。「100人100通りの働き方」が必要な理由とその実現方法 | PR TIMES MAGAZINE
事例3.初任給引き上げ・熱中症対策・DX化などで働き方を多様化
働き方改革による働き手の多様化を推進し、建設業では珍しい女性3割の従業員数を誇る三和建設株式会社。高校生新卒採用の初任給を引き上げたり、熱中症対策を強化したりといったさまざまな取り組みを展開しています。
特に魅力的なのは、作業のDX化です。建設業界全体の人材不足を解消するため、一部作業の自動化や業務改善を目的とした開発を手掛けました。DXの導入が難しいと思われがちな建設業界ですが、積極的な取り組みにより負担軽減・人材不足解消などの効果が期待できるでしょう。
参考:業界のイメージを変えたい。ひとり広報が立ち上げからメディア掲載を5倍へ伸ばした施策|三和建設株式会社 | PR TIMES MAGAZINE
事例4.65歳以上の人材を募集する「老卒採用」がスタート
住宅・不動産ポータルサイトの運営などを手掛ける株式会社LIFULLは2024年、65歳以上のシニアを募集する「老卒採用」を実施しました。シニア採用を積極的に行う企業少ないことを受けて、「歳をとったら引退しなきゃ、なんてない。」をコンセプトにスタートした取り組みです。
営業・クリエイティブ・法務の3種類を募集ポジションに掲げており、複数の業種で活躍できる機会を設けているのが特徴。高齢者の就業者割合が多い現代において、採用の間口を広げる取り組みは働き方改革の重要な施策のひとつといえるでしょう。
参考:LIFULL、経験豊富なシニアを募集する「老卒採用」を開始
事例5.オフィスでの自由な働き方を推進するレイアウトにリニューアル
YKK AP株式会社は、東京都千代田区にある本社ビルのオフィスフロアを全面リニューアルし、「会えるオフィス」として使用を開始しました。部門別に区分けされていたオフィスの固定堰を撤廃し、フリーアドレスのレイアウトを採用。さらにデジタル対応を強化し、コミュニケーションやパフォーマンスの向上といった効果を目指しています。
好きなときに好きな場所を選べる点を強みとしており、フリーアドレスのメリットを最大限に活かした好事例ともいえるでしょう。一ヵ所にとらわれないデスクレイアウトのほか、備品の共有や書庫の共通化なども従業員同士のつながりを深め、エンゲージメントの向上が期待できる施策です。
参考:会話がはずむ「会える」オフィスにリニューアル!YKK APのパーパス実現のための働き方改革とは
働き方改革の取り組みを広報PR・発信する重要性
働き方改革に取り組む企業は、広報PR活動を展開することも重要な業務です。メディア関係者への認知拡大はもちろん、就職・転職を控えている人やその家族、株主、現在の従業員など幅広いステークホルダーにアプローチするきっかけとなります。
例えばロート製薬株式会社は、毎年6月10日を「ロートの日」に定め、健康宣伝日としてプレスリリースを配信。心身の健康維持・増進や業務効率化、多様な働き方といった取り組みを具体的に提示することで、働き方改革に対する自社の活動・制度を広く伝えました。時流に応じた活動内容がわかるプレスリリース配信は、働き手を守る安心性・安全性を知ってもらう広報PR業務のひとつともいえるでしょう。
参考:6月10日は健康宣言日「ロートの日」社員の自律と社会への参画を促す「ROHTO Well-being LIFE宣言」~リスキリング休職制度も新設
働き方改革の取り組みを広報PRしていく際の3つのポイント
働き方改革に関する取り組みの認知を広めるためには、制度導入の背景や企業としての目的・目標などを明らかにしなければなりません。導入後に変化が見られたのであれば前後の違いを可視化し、取り組みの意義を示すことも大切です。働き方改革についてプレスリリースを配信する際、特に重視したいポイントを3つご紹介します。

ポイント1.自社の課題や制度導入の背景を明らかにする
プレスリリース制作の前に実施しておきたいのが、働き方改革に対する自社の課題や制度導入の背景を明らかにするプロセスです。「なぜ当該の制度が必要なのか」「企業としてどのような効果が見込めるのか」を明確にし、実施に至った理由を伝えましょう。
導入の背景が明らかになれば、今後企業としてどのような成長が見られるのか、ステークホルダーからの期待値も高まります。関連の取り組みだけでなく、事業や企業そのものに関心を持ってもらうきっかけにもなるでしょう。
また、新しい取り組みを従業員に周知するためには、社内広報が有効です。社外に発信するプレスリリースとは別に社内広報の制作も進行し、スムーズにスタートできる体制を整えておきましょう。
ポイント2.導入前後の変化を数値などで透明化する
働き方改革に関する取り組みを続けているなかでプレスリリースを配信する場合は、導入前後の変化を示すことで効果を可視化できます。より多くのステークホルダーに認知してもらうためには、導入後の継続的な情報発信が重要です。
例えば、離職率の低下を目的とした働き方改革であれば、導入後どの程度低下が見られたか数字を示せると変化が伝わりやすくなります。客観的なデータの収集が難しい場合は、制度を利用した従業員のコメントを紹介したり、取り組みによる社内満足度調査をレポートしたりしてもよいでしょう。
ポイント3.調査結果や評価実績は社内広報で共有する
働き方改革の取り組みによって社内に変化が見られた場合は、実績として従業員に共有することも大切です。社外へのプレスリリース配信と併せて、社内広報を制作して調査結果・評価実績などを積極的に配信しましょう。
具体的な取り組みや制度の体験談・実績・利用状況がわかれば、新しい社内制度も浸透しやすくなります。社内広報については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧になってください。
働き方改革の取り組みを社内外に発信していこう
働き方改革は、すべての働き手のあらゆる場面において多様性を認める施策。働く場所・時間の自由化はもちろん、子育て・介護による休暇に対応したり、自社独自の制度を取り入れたりすることでワークライフバランスを充実させられます。
自社で取り入れている施策を広く発信するためには、プレスリリース配信をはじめとする広報PR活動が重要です。社内外への積極的な発信により、自社の課題・活動内容・実績を明確に示せるようになります。今回ご紹介したポイントを参考に、課題や背景を明らかにしながら継続的な情報発信を実施していきましょう。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事病院広報誌とは?基礎からわかる作り方・活用法と成功のポイントを解説【事例あり】
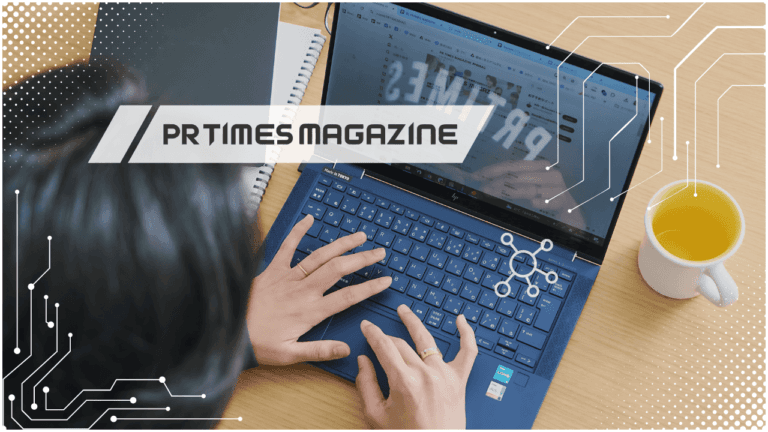
- 次に読みたい記事病院ブランディングとは?信頼と認知を高める広報戦略と具体的な施策・実践ポイントを解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

