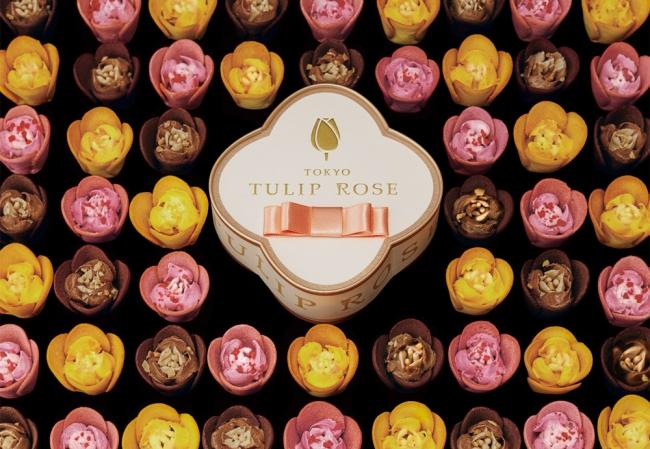新しいアプリを公開する際は、ただ機能を発表するだけではなく、「どのように世の中へ知らせるか」が、サービスの信頼性や認知拡大に直結します。特にアプリのようなプロダクトは、実際に使ってもらう前に信用を得る必要があるため、第三者を通じた情報発信が効果的です。
そこでポイントとなるのが、プレスリリースの活用です。メディアを通じて情報を届けることで、信用の獲得や対象とする層への効率的なアプローチが可能となり、SNSなどへの二次的波及も期待できます。
本記事では、アプリ公開時にプレスリリースを活用する3つのメリットを紹介し、効果的な情報発信について解説します。
アプリの公開に関するプレスリリースを配信する3つのメリット
新しいアプリを世の中に届けるうえでカギとなるのが、信用の獲得と関心層への効率的なアプローチです。ここでは、プレスリリースの発信によって得られる具体的なメリットを3つご紹介します。
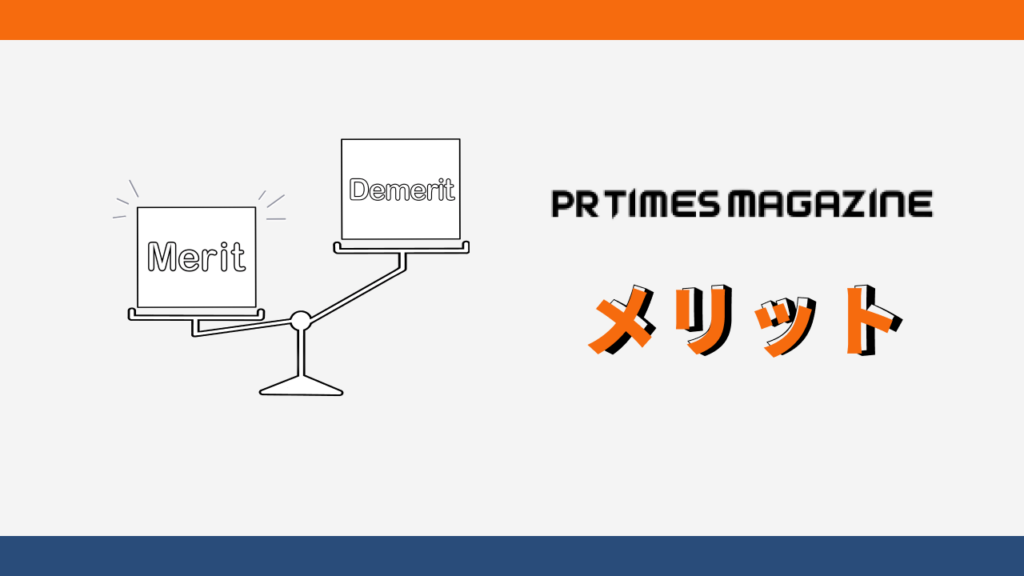
メリット1.信用を獲得できる
アプリのローンチ時にまず重要なのは、ユーザーからの信頼を得ることです。プレスリリースを活用することで、アプリに関する正確な情報をメディアや業界媒体へ届けることができるでしょう。
特に新規アプリの場合、提供元や機能、セキュリティ対策など、利用前に知っておいてほしい情報を事前に発信しておくことで、初動でのユーザー獲得を後押しできる可能性が高まります。
メリット2.幅広い層にアプローチできる
アプリは特定の業界や業種に特化しているケースが多く、情報が届きづらいこともあります。PR TIMESのメディアリスト機能を活用すれば、自前のメディアリストがなくても、テレビ・新聞・雑誌・Web・フリーペーパー・ラジオ・通信社など、1万件超えのメディアから最大300件へメールでプレスリリースを配信することが可能です。
専門メディアや業界紙などの読者層にも直接アプローチできるため、関係者やキーパーソンに情報を届けるきっかけになります。結果として、潜在的な利用者や提携先からの問い合わせにつながり、認知拡大にも大きく貢献できるでしょう。
メリット3.二次的な広がりが期待できる
プレスリリースがメディアに取り上げられると、SNSやブログ、まとめサイトなどへの二次的な波及が期待できます。新聞やWebメディア、テレビなどで紹介されることで、企業の信頼性や認知度が一気に高まることもあります。
アプリの場合、第三者であるメディアからの紹介は、潜在的ユーザーやパートナーへの強い説得材料となります。メディア掲載をきっかけにSNSや口コミで情報が拡散され、短期間で多くの注目を集めることが可能です。
費用対効果の高い広報PR施策として、プレスリリースはアプリ公開時のスタートダッシュに欠かせない手段といえるでしょう。
アプリの公開に関するプレスリリース作成の3つのポイントと注意点
アプリの公開に関するプレスリリースの効果を最大限に引き出すには、作成時の工夫が欠かせません。ここでは特に意識しておきたい3つのポイントと注意点を紹介します。
1.技術説明に偏りすぎない
アプリ開発に力を入れてきた企業ほど、つい技術的な特徴を強調しがちです。しかし、生活者やメディアが知りたいのは、「使って何ができるのか」「どんな価値があるのか」といった点です。
プレスリリースでは、ユーザー課題をどう解決できるのか、導入によってどのようなメリットが得られるのかを中心に構成しましょう。興味を持ってもらうための「入口」であることを意識し、専門用語や開発背景ばかりに偏らず、具体的な使い方や効果を伝えることが大切です。
2.競合との差別化を明確に打ち出す
アプリ市場は競争が激しく、プレスリリースの内容が「よくあるサービス」に見えてしまうと、埋もれてしまうリスクがあります。自社アプリならではの優位性を、明確に伝えることが重要です。
機能や価格といった表面的な比較だけでなく、独自の特徴、対象ユーザーの明確さ、導入のしやすさ、セキュリティ配慮、サポート体制なども盛り込みましょう。競合との差別化を打ち出す際は、他社製品を否定するような表現は避けるのが基本です。
あわせて、「なぜこのタイミングで発表するのか」といった背景も記載すると、内容に納得感が加わります。
3.セキュリティ情報を明示する
アプリにおいては、ユーザーが安心して利用できる環境が整っていることを明確に伝える必要があります。特に、個人情報や位置情報、決済機能などを扱うアプリの場合、セキュリティ対策やプライバシー保護への取り組みを具体的に説明しましょう。
たとえば、「通信はすべて暗号化」「個人情報は第三者に提供しない」といった一文があるだけでも、利用への心理的ハードルが下がります。運営体制やサポート内容、第三者認証の取得状況なども、信頼性を高める要素となります。
機能や利便性に加え、「安心して使える理由」をセットで伝えることが、信頼の獲得と利用促進につながります。
アプリの公開に関するプレスリリース作成前に準備すること・タスク
効果的なプレスリリースを配信するうえで重要なのは、作成前の入念な準備です。実際にどのような素材を集めれば、公開予定のアプリの魅力を押し出すことができるのか具体的に紹介します。

1.ユーザーと利用シーンの具体化
アプリの公開にあたっては、想定するユーザー像と利用シーンを具体的に描くことが重要です。
ユーザーの業種や立場、抱える課題、どんな状況でアプリを使うのかを整理すると、プレスリリースで伝えるべき訴求ポイントが明確になります。こうすることで「このアプリは自分に関係がある」と読み手が感じられるようにし、共感や興味を引き出しやすくなります。
2.強みと独自性の言語化
自社製品ならではの強みや差別化ポイントは、社内では当たり前になっていることも多く、外部には伝わっていないことがあります。
「他のアプリと何が違うのか」「なぜ今このアプリが必要なのか」といった問いをもとに、第三者目線で言語化しておくと、プレスリリースの説得力が高まります。
技術的な特長に加え、ユーザー体験や導入メリットにも注目しながら整理しておきましょう。
3.UIのスクリーンショットとテストユーザーの準備
アプリの魅力や使いやすさを言葉だけで伝えるのは限界があります。そのため、UIのスクリーンショットや利用シーンを示す画像、テストユーザーの声などをあらかじめ用意しておくと効果的です。視覚的にアプリの価値が伝わることで、メディアの理解も深まり、記事化される可能性が高まります。
まだ実績が少ない場合でも、テストユーザーのフィードバックや今後の導入予定事例などを紹介することで、信頼性を補完できます。
アプリの公開におけるプレスリリース事例10選
ここまで紹介してきた、アプリ公開時におけるプレスリリース活用のメリットや作成のポイントを踏まえ、実際に配信された事例をご紹介します。
具体的な構成や見せ方を知ることで、自社のリリース作成の参考にしていただけます。
事例1.アセットテクノロジー株式会社
- アプリの機能ごとにUIスクリーンショットを活用し、視覚的にわかりやすく説明
- 日本語アドバイザーの経歴を紹介し、製品の信頼性を向上
- SNSキャンペーンの併記による製品の認知拡大
参考:アセットテクノロジー、不動産オーナー様と管理会社とのコミュニケーションを円滑に行えるアプリ「AT Owner’s」をローンチ
事例2.verbal and dialogue株式会社
- アプリの利用方法を画像付きで紹介し、操作のしやすさを訴求
- 採択や受賞実績を記載し、製品の信頼性を強化
- 建設業界の課題を明示し、それに対する解決策としてのアプリ価値を提示
- 今後の展望を踏まえ、導入による持続可能性を示唆
参考:AI工事写真アプリ「Cheez」を5月19日に正式ローンチ
事例3.ビズメイツ株式会社
- 法人向けに行ったテスト提供の結果を紹介し、実績と信頼性を強調
- 新機能追加の背景を、ユーザーの声とともに紹介
- UIのスクリーンショットで機能を視覚的に解説
参考:ビズメイツ、AI×人のハイブリッド英語学習アプリを本格提供開始
事例4.株式会社menopeer
- アプリと関連性の高い記念日に合わせてリリースを配信し、話題性を創出
- テストユーザーアンケートを活用し、ニーズに応えた開発であることを訴求
- UIのスクリーンショットを掲載し、アプリの特徴をわかりやすく説明
参考:国際女性デーにあわせ、プレ更年期〜更年期世代の女性を支えるヘルスケアアプリ「Lumino(ルミノ)」を正式ローンチ 〜女性の声を反映した調査結果も発表
事例5.株式会社KortValuta
- 双子や三つ子に関するデータや悩みを提示し、アプリの必要性を明示
- 想定ユーザーの声を写真とともに紹介し、感情に訴求
- 冒頭で用途や利用シーンを簡潔に提示し、ひと目でアプリの目的が伝わる構成
参考:双子・三つ子のママたちがつくった世界初の多胎育児特化型アプリ「moms」、3月5日プレリリース
事例6.SpiralAI株式会社
- アプリの提供開始に加え、ニュース性のある情報を別軸で追加し話題性を強化
- 通常のAIとの会話比較を通じ、アプリの独自性を訴求
- コラボ声優のコメントを紹介し、安全性・倫理性への配慮もアピール
参考(ローンチ):自社開発の感情特化型LLM「Geppetto」を搭載 感情豊かな動物キャラたちと話して、友だちになれるAIアプリ「HAPPY RAT」を本日より提供開始
参考(企画):声優 梶裕貴さんが命を吹き込んだ心を持つAIキャラクター「SOYOGI」が登場 会話型友だちAIアプリ「HAPPY RAT」との夢のコラボが実現
事例7.株式会社みずほポシェット
- 想定するユーザーと、その課題・解決策を具体的に提示
- 調査レポートを活用し、製品の社会的意義と需要を裏付け
- アプリを通して学べることを、事例形式で丁寧に紹介
参考:「令和っ子のお金トラブルと金融経済教育に関する意識調査」 親子で楽しくお金のおけいこができるアプリ『PochettePlus』2025年4月24日(木)より提供開始
事例8.株式会社ベガコーポレーション
- メディア限定の体験会を紹介し、報道や購入を後押し
- 想定ユーザーの状態や使用シーンを具体的に説明
- 過去の製品に関するプレスリリースへのリンクも用意し、経緯の把握を容易化
参考:【スマホでお部屋づくり】自社開発アプリ「おくROOM®」のリリースが決定!スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスが開始
事例9.コングラント株式会社
- 社会課題を明示し、その課題解決としてのアプリの価値を訴求
- 製品のコンセプトをビジュアルでわかりやすく表現し、今後の展望提示による将来性と社会的意義の伝達
参考:寄付体験を革新するスマート寄付アプリ「GOJO」。5月22日(木)サービス開始
事例10.株式会社Sound One
- UI動画を活用し、アプリの使用シーンを直感的に伝達
- 「活用シーンとターゲット」の明確な記載による読み手の想像促進
- URLに加え、QRコードも併記することでインストールの導線を強化
参考:走行中の“音・映像・軌跡”をまるごと記録できるアプリ「Sound One Recorder Ver.4」を公開
アプリの公開時に行いたい3つの広報PR施策
ここからは、プレスリリースの配信とあわせて実施したい効果的な広報PR施策をご紹介。ご状況に合わせて取り組みやすいものからスタートしてみてください。

1.テストユーザーによる事前体験と感想の収集
アプリのローンチ前にテストユーザーを募り、実際に利用してもらうことで、ユーザー視点からの率直なフィードバックが得られます。これはサービスの改善や完成度の向上に役立つだけでなく、得られた感想をプレスリリースやWebサイト、SNSなどに掲載すれば、信頼性の高いプロモーション素材として活用できます。
さらに、テストユーザー自身がSNSなどで体験を発信することも期待でき、自然な口コミによる情報拡散が生まれる可能性も。特に新しいアプリでは、「実際に使ってみた」声が、潜在ユーザーの不安を払拭し、導入を後押しする重要な材料になります。
2.ティザーサイトや事前登録キャンペーンの実施
プレスリリースの配信前に、アプリのコンセプトや一部機能を紹介するティザーサイトを公開したり、事前登録キャンペーンを実施したりすることで、潜在ユーザーの関心を高められます。
メールアドレスやアンケートを通じてリード情報を収集すれば、ローンチ時に一斉に通知・告知でき、効率的に初期流入の確保が可能に。登録者限定の特典や先行案内を用意することで、参加意欲の向上も期待できるでしょう。
また、キャンペーンをSNSと連動させれば拡散力が高まり、注目度を段階的に高めながらローンチへの期待感を醸成できます。
3.業界メディアや関係者への事前案内と個別打診
アプリの広報においては、業界メディアやキーパーソンとなる関係者への事前案内・個別打診が非常に効果的です。プレスリリース配信に先立ち、関心を持ちそうなメディア、インフルエンサー、業界団体などに対して、アプリの概要や特徴、想定される効果を丁寧に説明し、取材や掲載の可能性を探っておきましょう。
特にアプリのようなサービスは、第三者からの紹介が利用者に与える安心感や信頼性に直結します。専門メディアでの紹介や業界内での評価は、導入検討の後押しになります。
こうした関係性を事前に築いておくことで、プレスリリース後にインタビューや独自記事として取り上げられるなど、より深い露出にもつながる可能性があります。
まとめ:信頼性を高め、話題を呼ぶ配信を
アプリの認知拡大を図るには、信頼と注目を同時に獲得できる広報PR戦略が不可欠です。なかでもプレスリリースは、正確な情報を第三者視点で伝えることで、初動のユーザー獲得や認知向上に大きく貢献します。
プレスリリースには、信頼性の醸成、対象ユーザーへの効率的なアプローチ、SNSやブログなどへの二次的波及といった3つの効果も期待できます。技術に偏らずユーザー視点で価値を伝えること、競合との差別化、セキュリティ情報の明示など、アプリならではの要素を適切に押さえることが成功のカギとなります。
本記事で紹介したテストユーザーの声や利用シーンの可視化、メディアへの個別打診といった施策も組み合わせながら、ローンチ初期の広がりを最大化してみてください。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする