「リード獲得につながる効果的な広報PR活動について知りたい」「どのような手法を選べばよいのか迷っている」と感じている広報PR担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、広報PRの視点からリードジェネレーションに取り組む際に知っておきたい基本的な考え方と実践しやすい手法、成果につなげるためのポイントをわかりやすくご紹介します。
リードジェネレーションとは
リードジェネレーション(Lead Generation)とは、自社の商品やサービスに関心を持つ見込み顧客(リード)を獲得するための一連のマーケティング活動を指します。
マーケティングが担うことが多い領域ですが、広報PR活動がリード獲得の起点となるケースも少なくありません。Webサイトの運営やセミナーの開催、広告だけでなく、プレスリリースの配信やSNSでの情報発信によって認知度が高まり、結果として新たなリードとの接点が生まれることがあるからです。
BtoB領域では、資料請求や問い合わせといった行動を通じて営業につなげる、重要なファーストステップとなるでしょう。
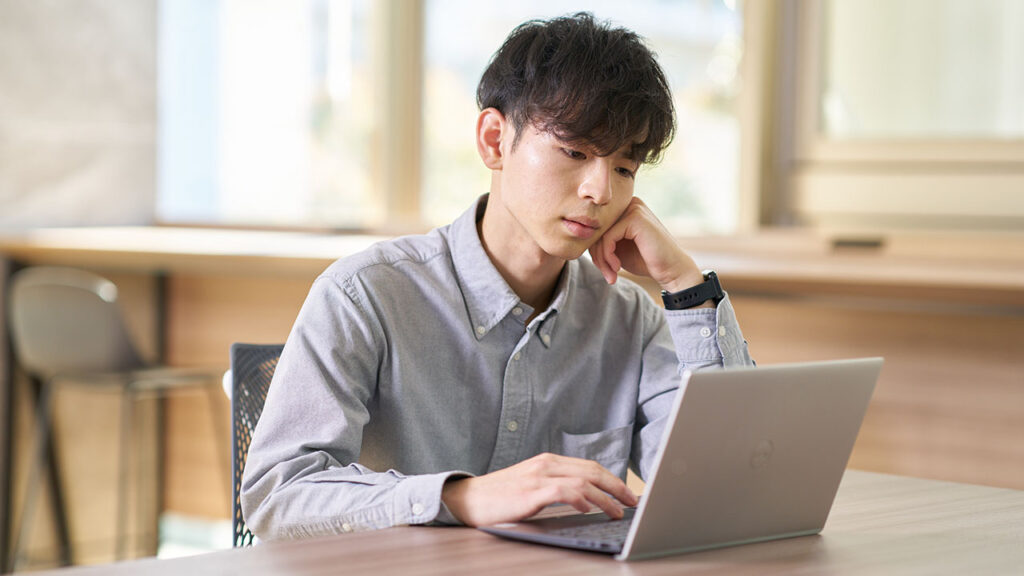
リードナーチャリングとの違い
リードジェネレーションが「見込み顧客(リード)を新たに獲得すること」を目的としているのに対し、リードナーチャリング(Lead Nurturing)は「すでに獲得した見込み顧客(リード)を育成する」プロセスです。見込み顧客の関心を維持・向上させ、購買やサービス利用につなげることを目的とします。
たとえば、セミナー後のフォローアップメールや、定期的な有益コンテンツの提供などがナーチャリング施策に該当します。広報PR活動においても、こうした関係性の構築を意識することが重要です。
リードクオリフィケーションとの違い
リードクオリフィケーション(Lead Qualification)は、獲得した見込み顧客の情報をもとに、購買や利用につながる可能性が高いかどうかを見極めるプロセスです。リードの「質」を評価し、有望なリードを選別する役割を担います。
一方、リードジェネレーションはリードを「増やすこと」が主な目的であり、目的や実施のタイミングが異なります。広報PR活動を通じて得られたリードも、営業やマーケティングと連携し、丁寧に評価・育成していく視点が求められるでしょう。
リードジェネレーションの5つの手法
リードジェネレーションを実現するには、目的や顧客層に応じて、適切な手法を選定することが重要です。また、複数の手法を組み合わせることで、リードとの接点を生むチャンスを広げ、効果をより高めることも可能です。ここでは、広報PRで実践できるリードジェネレーションの手法を5つご紹介します。
1.見込み顧客との接点を増やすオウンドメディアの運営
見込み顧客との継続的な接点をつくるうえで、オウンドメディアの運営は欠かせない手法のひとつです。生活者が商品やサービスを比較検討する際には、まず検索エンジンで情報収集を行うことが多いため、SEOを意識したコンテンツを発信し、自社への流入経路を増やすことが求められます。
また、広報PR活動との連動によっても、リード獲得への効果を高めることが可能です。たとえば、プレスリリースで発表した情報を公式Webサイトで記事化して詳しく解説することで、内容の理解を促進でき、関心度の高い層からの流入が期待できます。
オウンドメディアの作り方は、以下の記事をご参照ください。
さらに、オウンドメディアとクロスチャネルを組み合わせることで、より効果を発揮します。公式SNSと連携させたクロスチャネルでの発信により、多様なタッチポイントを確保しやすくなるのもメリットです。
2.プレスリリースを活用した新規リードの獲得
プレスリリースの配信は、企業やブランドの情報を広く届けるとともに、新たなリード獲得の起点にもなり得る施策です。たとえば、新商品・サービスの発表、イベントの告知などを発信することで、関心を持った生活者やビジネス関係者との接点を創出できます。
さらに、メディアに取り上げられれば、より高い拡散効果が得られ、自社Webサイトや資料請求ページなどへの流入増加にもつながるでしょう。
プレスリリースでは「誰に、何を、なぜ届けるのか」を明確にし、ニュース性や話題性を意識した設計が重要です。
3.公式SNSの運用によるファン層の興味喚起
XやInstagram、FacebookなどのSNSを活用した情報発信も、リードジェネレーションにおける有効な手法のひとつです。公式SNSの運用は認知拡大にとどまらず、投稿へのコメントやシェアなどを通じて、見込み顧客と双方向のコミュニケーションを図れることが特徴です。
たとえば、投稿に対するリアクションから興味・関心の高いユーザーを把握し、特設ページへ誘導する導線設計をすることで、リードの情報獲得につなげられます。さらに、SNSは低コストで広範囲にリーチでき、運用データを分析しながら適宜改善できる点も大きなメリットといえるでしょう。
4.セミナー・ウェビナーによる深い情報提供
セミナーやウェビナーの開催は、見込み顧客と直接接点を持ち、信頼関係を構築するための有効な方法です。参加者にとって価値ある情報を提供することで、企業への信頼感が高まり、リードの購買意欲向上にもつながります。
たとえば、業界の最新動向や課題解決策をテーマにしたセミナーを行うと、情報収集意欲の高い層との接点が生まれやすくなります。さらに、申し込み時に取得できる基本情報(氏名・企業名・メールアドレスなど)は、リードナーチャリング施策においても有効に活用できます。イベント後のアンケートやフォローアップメールなどで、継続的な接点を設計することもポイントです。
以下は、セミナーの集客方法について詳しく書かれた記事になります。セミナー・ウェビナーの開催を検討する場合は、ぜひ参考にしてみてください。
5.展示会やイベントなどのリアル開催で信頼を構築
展示会やリアルイベントは、製品やサービスを直接体験してもらえる貴重な機会であり、リードジェネレーションにおいても高い効果を発揮します。実際に担当者と対話することで、信頼感の醸成や課題の共有がしやすくなる点もメリットです。
たとえば、BtoB企業が展示会に出展し、来場者と名刺交換を行ったり、アンケートで課題をヒアリングしたりすることで、リード情報の質も高まります。
また、イベント後に送るサンクスメールや来場特典の提供などを通じて、リードと継続的な接点を持つ機会にもつなげられるでしょう。
リードジェネレーションを成功させる4つのポイント
リードジェネレーションを成功させるには、施策の実行に加えて、その前提となる考え方や運用設計も大切なポイントです。ここでは、成果につながるリードを獲得するために意識したい4つのポイントをご紹介します。

ポイント1.獲得したい見込み顧客(リード)を明確にする
リードの数を増やすことも重要ですが、自社の事業成長や目標に直結する「適切なリード」を見極めることが成果を左右します。
たとえば、BtoB企業であれば「特定業種の中小企業のマーケティング担当者」、BtoC企業なら「20〜30代の美容意識が高い生活者」など、目的に合ったリード像を具体的に設定しておくことがポイントです。
届けたい相手が明確であれば、施策内容の選定やメッセージ設計にも一貫性が生まれ、無駄のない効果的なアプローチが可能になります。
ポイント2.質の高いリードを獲得する
リードジェネレーションでは、数に加えて「質」にも注目することが不可欠です。購買やサービス利用につながる可能性が高いリードに対して、効率よくアプローチすることで成果につながりやすくなります。
たとえば、BtoBであれば業界特化型のセミナーや資料提供、BtoCであれば購入意欲の高い層に向けたキャンペーン施策などが効果的でしょう。オウンドメディアで深い情報を発信することやプレスリリースを活用し、メディアを通して情報を広げられることも有効です。
過去の商談化率や顧客属性データなども活用しながら、自社にとって有望なリードを見極めたうえで戦略を設計することが大切です。
ポイント3.取得したリード情報を有効に活用する
リード情報は、展示会・セミナー・SNS・オウンドメディアなど、取得経路ごとに整理しておくことで分析しやすくなります。接点によって関心の深さや属性に傾向があるため、それを把握することでアプローチの精度を高められるでしょう。
たとえば、展示会経由のリードは具体的な課題を持つケースも多く、SNS経由のリードはまだ情報収集中の段階であることも少なくありません。こうした違いを踏まえて情報を分類・可視化し、必要に応じてマーケティングツールなども活用することで、次の施策にスムーズにつなげることができます。獲得後の活用体制を整えることは、リードジェネレーション全体の費用対効果を大きく左右するためとても重要です。
ポイント4.マーケティング・広報PR・営業など関連部署との連携を強化する
リード獲得は広報PRやマーケティング、営業など複数の部署が関与するため、部門間の連携が不可欠です。たとえば、広報PR活動によって得られたリードが、営業での商談や成約にどのようにつながったかを部署間で共有することで、次の施策改善に役立てることができます。
また、定期的にリードの質や獲得経路を振り返ることで、どのチャネルが効果的かを可視化しやすくなります。情報を共有しながら部門を越えて連携することで、リードジェネレーション全体の成果をより高めやすくなるでしょう。
リードジェネレーションの事例
実際にリードジェネレーションに取り組んでいる企業は、どのような工夫をしているのでしょうか。ここでは、体験イベントやセミナーなどを活用して、質の高いリードを獲得している3つの事例をご紹介します。
事例1.ON&BOARD株式会社
ON&BOARD株式会社は、投資家や起業家、スタートアップ支援者など、将来的な関係構築が必要となるビジネス層を対象にリードジェネレーションを展開しています。
創業支援プログラムを軸に、関心度の高い層との接点を獲得しており、イベント終了後もメディアコンテンツを継続的に発信。
一度きりで終わらない接点設計により、長期的な関係構築を実現しています。BtoBにおける「質の高いリード獲得」と「接点の継続」が両立された事例といえるでしょう。
参考:ベンチャーキャピタルON&BOARD 創業支援プログラム第2期「Out of BOUNDS for Biz」DEMO DAYをGlobal Business Hub Tokyoにて4月18日開催決定
事例2.鳥羽珈琲株式会社
鳥羽珈琲株式会社は、生活者から寄せられた「コーヒーをもっと深く知りたい」といった声に応えるかたちで珈琲教室を開催。
体験型イベントを通じて、コーヒーに関心の高い見込み顧客との接点を創出しています。さらに、お土産として自宅で楽しめるコーヒー豆を配布するなど、イベント終了後のブランド接触機会が設計されているのもポイントです。
参加者の属性や反応を分析し、次の施策にもつなげている点からも、顧客起点のリード獲得施策として参考になります。
参考:コーヒー好きのための大人の夏期講習!自由が丘の優雅なカフェで学ぶ「珈琲教室」
事例3.株式会社Japanticket
株式会社Japanticketは、中国インバウンド集客に関心のある企業担当者を対象に、無料セミナーを開催しています。参加対象を「飲食・商業施設・小売業界の担当者」と明確に定めることで、「ニーズの高い層=質の高いリード」の獲得を意図的に実現。
さらに、セミナー内容も実践的なノウハウや事例を中心に構成されており、参加者の関心を高めながら接点を強化しています。リードの選定と、施策の内容設計のバランスがとれている点が参考になる事例です。
参考:【3/26(水)無料セミナー】 2025年、中国市場のインバウンド集客成功法!中国人観光客が行きたい店から学ぶ「大衆点評」を活用した実践的インバウンド施策
まとめ:リードジェネレーションは質の高いリードの獲得がポイント
リードジェネレーションを成功させるには、単にリードの数を集めるのではなく、自社の目的に合った「質の高いリード」をいかに見極め、獲得していくかが重要な課題です。
広報PR活動を通じて認知を広げ、関心度の高い層と接点を創出することで、成果につながる関係構築のきっかけになります。そのためには、マーケティングや営業といった他部署との連携も不可欠です。
まずは「どのようなリードを獲得したいのか」を明確にし、それを軸に施策を設計していくことが、リードジェネレーション成功への第一歩となるでしょう。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事新製品のマーケティング手法5選|成功ポイント、BtoCとBtoBの違い

- 次に読みたい記事ブランド評価とは?評価の指標や測定方法、ブランド価値を高める5つの方法を解説

- まだ読んでいない方は、こちらから広報の手段・方法とは?具体的な12の広報活動例と成功に導くコツ・TIPSを解説

- このシリーズの記事一覧へ

