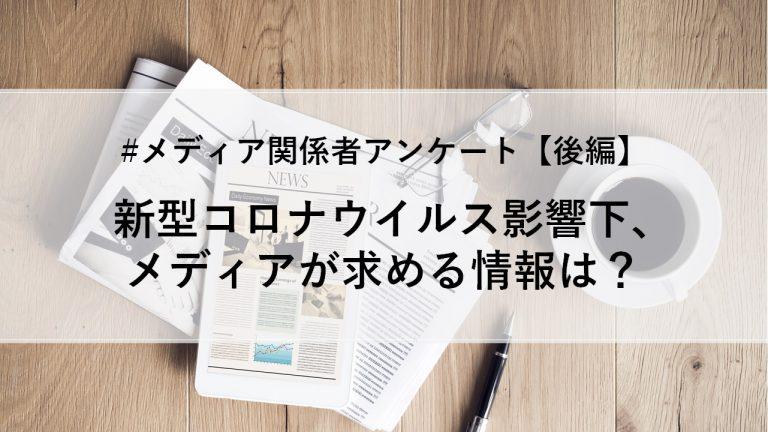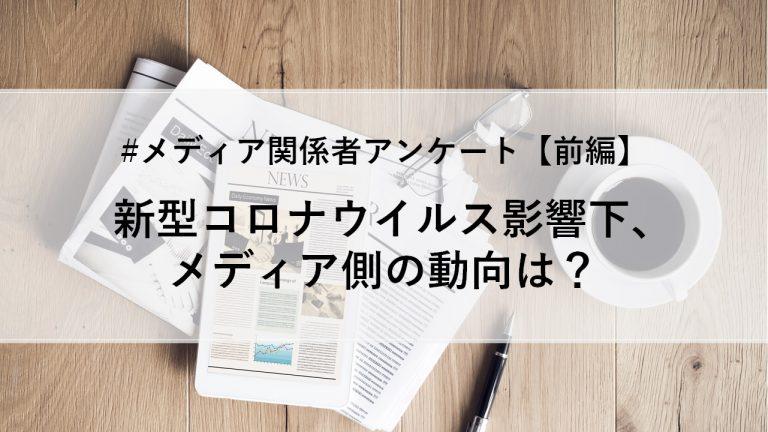新型コロナウイルスの影響でテレワークを実施する企業が増える中、「オンライン取材」を取り入れるメディアも増えています。この記事では、いつでもオンライン取材に対応できるよう5つのおすすめツールや押さえておくべきコツをご紹介します。
オンライン取材のメリットとは?
新型コロナウイルスの拡大に伴い、実施の機会が増えているオンライン取材。これまでの取材の常識からすると、どんなメリットがあるか一見わかりにくいかもしれません。しかし、実は取材する側にも取材される側にもメリットがある方法です。メリットを理解して、しっかりと取材対応できるよう準備しましょう。
メリットの一例
- 通信環境さえ整っていれば場所を選ばない
- 移動の必要がなく費用・時間の節約になる
- ビデオ会議ツールの画面共有機能を使ってスムーズに資料共有できる
- ビデオ会議ツールの録画・録音機能を使って取材の様子をログに残しやすい
オンライン取材に使える5つのおすすめツール
オンライン取材で使えるビデオ会議用ツールには、多くの種類があります。メディアや企業のインターネット環境や求める費用対効果と照らし合わせながら、どのツールを使うか選べると良いでしょう。ここでは、おすすめの5つのツールとそれぞれの特徴をご紹介します。
1.Zoom
最近のテレワークの流れの中で最も注目を集めているビデオ会議ツールが「Zoom」です。バーチャル背景を活用してユニークな使い方をするユーザーも多く、最大100人まで接続可能で、ホストが参加メンバーを少人数グループに分けられる機能もあります。ただし、無料版の場合は3人以上での接続が40分間までになる制限があるので注意しましょう。

- プランと月額料金:基本(無料)、プロ(2,125円/ホスト)、ビジネス(2,700円/ホスト)、企業(要問合/ホスト)
- 最大接続人数:1,000人
- アカウントなしの会議参加:可能
- 画面共有:可能、ホワイトボード機能あり
- 録画 / 録音:無料で可能
- その他:無料版の場合は3人以上での接続は40分間まで、バーチャル背景機能あり
2.GoogleMeet
2020年5月に一般ユーザーでも利用できるようになったのが「Google Meet」です。基本的には有料で利用しますが、14日間は無料でお試し利用できます。
- プランと月額料金:無料版、Basic(680円/ユーザー)、Business(1,360円/ユーザー)、Enterprise(3,000円/ユーザー)
- 最大接続人数:100人
- アカウントなしの会議参加:無料版では不可
- 画面共有:可能
- 録画 / 録音:無料版では不可
- その他:英語字幕機能あり
3.Microsoft Teams
「Microsoft Teams」は、250人が同時接続できます。利用にはMicrosoftアカウントが必要ですが、同じ画面上でWordやExcel、Power PointなどのOfficeアプリを用いた共同作業をすることも可能です。
- プランと月額料金:無料版、Essentials(500円/ユーザー)、Basic(750円/ユーザー)、Standard(1,560円/ユーザー)、Premium(2,750円/ユーザー)
- 最大接続人数:300人
- アカウントなしの会議参加:不可
- 画面共有:可能
- 録画 / 録音:無料版では不可
- その他:共有ストレージ機能あり、Microsoft Officeの共有機能あり
4.Skype
「Skype」の特徴は、アカウントなしで会議に参加できること。ホストが会議のURLを作成し、ゲストを招待するだけなので手間もかかりません。最大接続は100人までで、画面共有や録画・録音などの基本機能もすべて備わっています。
- プランと月額料金:無料版、月額プラン(290円〜 ※発信先によって異なる)
- 最大接続人数:100人
- アカウントなしの会議参加:可能
- 画面共有:可能
- 録画 / 録音:可能
- その他:固定電話や携帯電話への通話も可能(有料)
5.Whereby
「Whereby」もSkypeと同じくアカウントなしでの会議参加が可能です。チャット機能や画面共有などの基本機能は備わっており、無料版でも最大45分間接続できます。無料版に期間制限がなく、100人まで同時接続可能な点も魅力的です。
- 料金:無料版、Pro($6.99/ユーザー)、Business($9.99/ユーザー)
- 最大接続人数:200人
- アカウントなしの会議参加:可能
- 画面共有:可能
- 録画 / 録音:無料版では不可
- その他:チャット機能あり
オンライン取材の準備から本番までの流れ5ステップ
オンライン取材で何よりも大切なのは、メディア側も企業側も互いに十分な事前準備をしておくことです。使いなれないツールを使ったり、同じ空間にいない状態で会話を進めたりするとトラブルも起きやすくなります。スムーズに取材を進行できるよう、準備から本番までの流れを5つのステップで解説します。
STEP1.取材内容をすり合わせる
まずは、事前に取材内容をすり合わせましょう。互いに取材の主旨を理解しておかないと、メディア側は得たい情報を得られませんし、企業側は狙った形での露出ではなくなる可能性があります。
ビデオ会議ツールで対面の状態を作れるとはいえ、通常時にオフラインで行われる取材では伝わる情報がうまく伝わらない可能性もあります。どんな目的で取材をする / されるのか、必ず共通認識を作っておき、認識に齟齬が生じないようにしましょう。
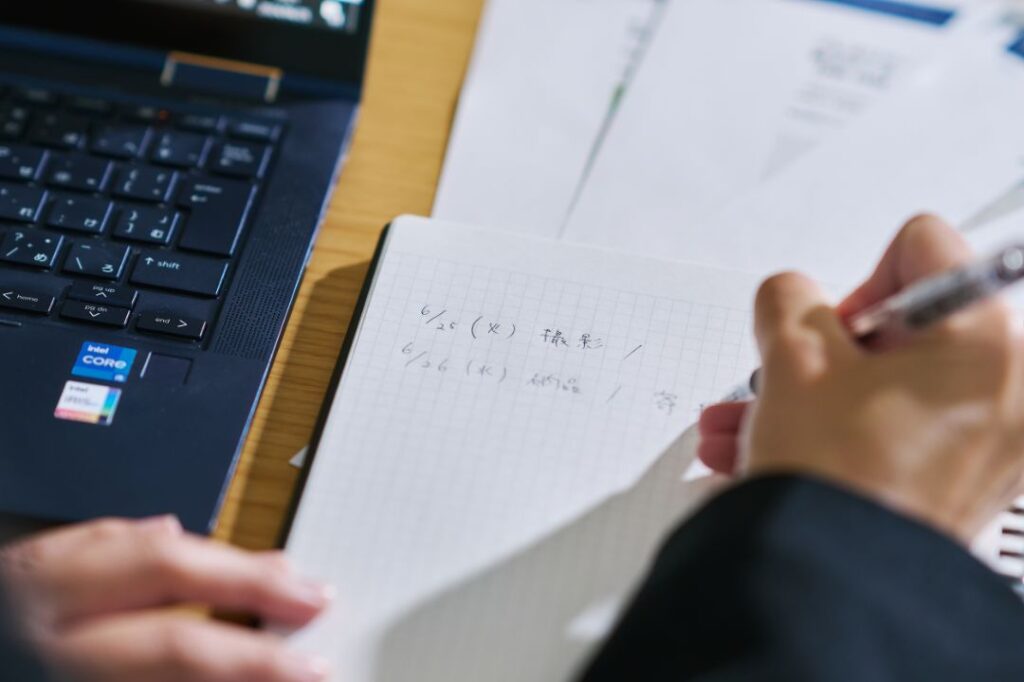
STEP2.取材出席者を確定させる
メディアが企業のオフィスや店舗などへ訪問する通常の取材であれば、会話の流れで「あの人にも話をしてもらおう」と急遽取材に呼ぶことが可能です。しかし、オンライン取材ではそうはいきません。STEP1で確認した取材目的に合わせて、適任と思われるスタッフを必ず事前に確定させておきましょう。
STEP3.取材日時を決める
前述の通りオンライン取材は場所や時間にとらわれない取材方法なので、取材日時は柔軟に調整できます。ただ、メディア / 取材を受けるスタッフ / 広報担当者など、異なる場所にいるすべての関係者が取材開始時刻までにスタンバイ完了している必要があるので、その点を考慮して取材日時を調整するよう注意してください。
STEP4.ツールのURLやアクセス方法を共有する
メディアや企業によって使用しているビデオ会議ツールは異なります。また、最適なツールが取材内容によって異なる場合もあるでしょう。メディアと企業のインターネット接続環境や取材内容によって最適なツールを選定して、取材当日に使用する会議のURLやアクセス方法を共有しましょう。取材当日になって慌てないためにも、事前に準備しておくことが重要です。
STEP5.時間になったら入室する
あらかじめ決めてある取材開始時刻になったら、STEP4で共有したツールとアクセス方法に則って会議に入室しましょう。入室したら、必ずすべての関係者がアクセス完了していることと、音声や動画の通信状況にトラブルがないかを確認してください。すべて問題なければ、その時点から取材を開始できます。
オンライン取材をするときの5つのコツと注意点
いよいよオンライン取材本番。オンライン取材には、通常時の取材とは異なる「オンライン取材ならでは」のポイントがあります。誤った情報や印象を与えずに正確な取材対応ができるよう、オンライン取材の5つのコツと注意点を確認して取材に臨みましょう。
1.聞き取れなかったら必ず聞き返す
接続状況や通信環境によっては、音声が聞き取りにくい瞬間があるかもしれません。聞き取れなかった場合は遠慮なく聞き返して、勝手な推察で会話を進めることのないようにしましょう。
数字や固有名詞など、相手にとって聞き取りにくいと思われる情報について話す際には、しっかりと聞き取れているかどうか逐一確認しながら会話を進めるのもよいかもしれませんね。
2.延長時に対応できるようツールの使用時間は30分長めに設定する
取材内容によっては取材の所要時間が延びる可能性もあります。ビデオ会議ツールの使用時間は、余裕を持って予定の時間よりも30分間長く設定しておきましょう。先述のとおり、ツールによっては接続時間に上限が設けられている場合もあるのであらかじめ確認しておくことも必要です。
3.議事録を共有し、数字などの聞き間違いを防ぐ
取材が終了した後、会話を書き起こした議事録をメディアに共有するのもひとつの方法です。「聞き取れなかったら必ず聞き返す」を徹底していても、どうしても100%完璧にはならないもの。互いに勘違いを生むことがないよう、数字などのデータや固有名詞など絶対に間違ってはいけない情報については議事録で再確認してもらうようお願いするとよいでしょう。

4. 取材対象者の肩書や漢字表記などを取材前後に共有する
オンライン取材では名刺交換ができないため、互いの肩書や氏名の表記も当然確認できません。どこの部署の誰が取材に対応するのか、メディア側に共有しておきましょう。共有のタイミングは取材の前後どちらでも構いませんが、取材前に共有しておいたほうがスムーズかもしれません。
5.提供できそうな画像や写真を予め用意しておく
取材当日の会場や人の様子を撮影できないのも、オフライン取材の特徴です。取材に関連する画像や写真を持っている場合にはあらかじめ用意しておき、メディアへ共有しましょう。また、もしビデオ会議ツールの画面のスクリーンショットが使用される場合には、写り込んではいけないものがないかなどを一度確認させてもらったほうがよいでしょう。
オンライン取材の進め方が心配な場合はリハーサルをしておこう
取材する側、される側の双方にメリットが多いオンライン取材。しかし、今まで主流ではなかった方法だからこそ、実践には丁寧な準備が必要です。進め方に不安がある時は、この記事を参考にしながらリハーサルをしてみてください。準備さえ整っていれば、きっとオンライン取材のメリットを享受できるはずです。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
オンライン取材の方法に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする