働き方が多様化し働き手にとって選択肢が増え、超少子高齢化が進行している昨今の日本は、条件だけでは人材を採用できない時代に突入しています。働き手の多くが待遇面だけでなく、その企業で働く理由もあわせて入社するか否かを決めているからです。
そんな時代において企業をブランド化しファンを作る「採用ブランディング」は、現状の採用課題解決の糸口となります。自社の魅力や他社との違いを明確に捉えてブランドメッセージとして打ち出すことで、自社にマッチした人材を獲得できます。採用に苦戦している企業こそ、採用ブランディングを実施する効果を実感できるはずです。
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、戦略的に自社のブランド力を高める採用活動のことです。転職顕在層・転職潜在層に向けて他社とは異なる自社の魅力を多面的に発信することで、自社のファンになってもらうことを目的とします。理想とする人材を採用するためのいわば土台作りとなる活動で、採用ブランディングの後に続く採用マーケティングにも影響を与えます。
採用ブランディングによっていかに自社で働きたいと思わせられるかが今後の採用活動を左右します。

採用広報との違い
採用広報は、自社が求める人材からの応募を促進するために行う活動です。求める人材像が明確になっていることが特徴。その人物像に対して自社で働く際の具体的なイメージを持ってもらい、応募や採用につなげることを目的とします。
一方、採用ブランディングは採用市場において自社ブランドの価値や存在感を高めることを目的としています。活動の対象となる人物像は設定されておらず、転職顕在層から転職潜在層まで幅広くアプローチし、経営理念やビジョン・ミッションに共感する人材を集めます。
採用広報と採用ブランディングは目的や対象となる層が異なりますが、いずれも短期的に成し得ない点は共通しています。
採用マーケティングとの違い
採用マーケティングは、採用に至るまでの転職顕在層・転職潜在層の行動のステップを認知・興味関心・応募・内定の4ファネルに分けた際、「応募」の部分にフォーカスしてマーケティング活動を行います。応募数を増やすことを目的としているため、短期間で集中的に行われるのが特徴です。
一方、採用ブランディングは採用における「興味関心」の部分にフォーカスしてブランディング活動を行います。自社のファンになってもらうことを目的としているため、活動は長期間にわたって行われるのが特徴です。
採用ブランディングによって採用の土台を作り、採用マーケティングによって自社の理想とする人材を獲得するという流れで覚えておきましょう。
なぜ今、採用ブランディングが重要なのか?目的と必要性を解説
採用ブランディングの重要性が高まっている背景には、働き方の多様化や価値観の変化、人材獲得競争の激化といった社会的要因があります。従来のように待遇面だけで差別化する採用活動では、企業の本質的な魅力が伝わらず、入社後のミスマッチや早期離職のリスクが高まることから、採用ブランディングに注目が集まっています。
採用ブランディングの最上位の目的は、「自社のファンを増やし、採用市場での存在感を高めること」です。その実現には、次の2つの上位目的に取り組む必要があります。
1つ目は、「入社後のミスマッチを防ぎ、定着率を向上させること」です。求人広告や人材紹介に頼った採用活動では、企業文化や働き方の実態が十分に伝わらず、ミスマッチが生じやすくなります。採用ブランディングに取り組むことで、候補者にリアルな企業像を伝え、入社後のギャップを減らすことができます。
2つ目は、「企業の理念やビジョンに共感する人材を集めること」です。報酬や条件ではなく、企業の存在意義や目標に惹かれて応募してくる人材は、自らの価値観と仕事を結びつけながら主体的に行動する傾向があり、長期的に企業の成長を支える重要な戦力となります。
さらに、現代の求職者は「いますぐ転職したい人」だけでなく、「良い企業があれば将来検討したい」と考える潜在層も多く存在します。採用ブランディングはそうした層にもアプローチできるため、中長期的に優秀な人材との接点を築くうえでも有効です。
このように採用ブランディングは、単なる採用手法ではなく、企業の価値を言語化し、共感によって人材との信頼関係を構築する経営戦略の一環といえます。定着率の向上、人材不足の解消、企業文化の浸透といった多方面において、今後ますます必要性が高まる施策です。
採用ブランディングに力を入れる5つのメリット
転職顕在層から転職潜在層まで、幅広い層の方にアプローチできるのが採用ブランディングですが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。人材不足の解消や人材の定着率向上以外の面で、採用ブランディングによって得られるメリットをご紹介します。採用ブランディングに力を入れることで、採用面での自社の課題解決が期待できるかもしれません。
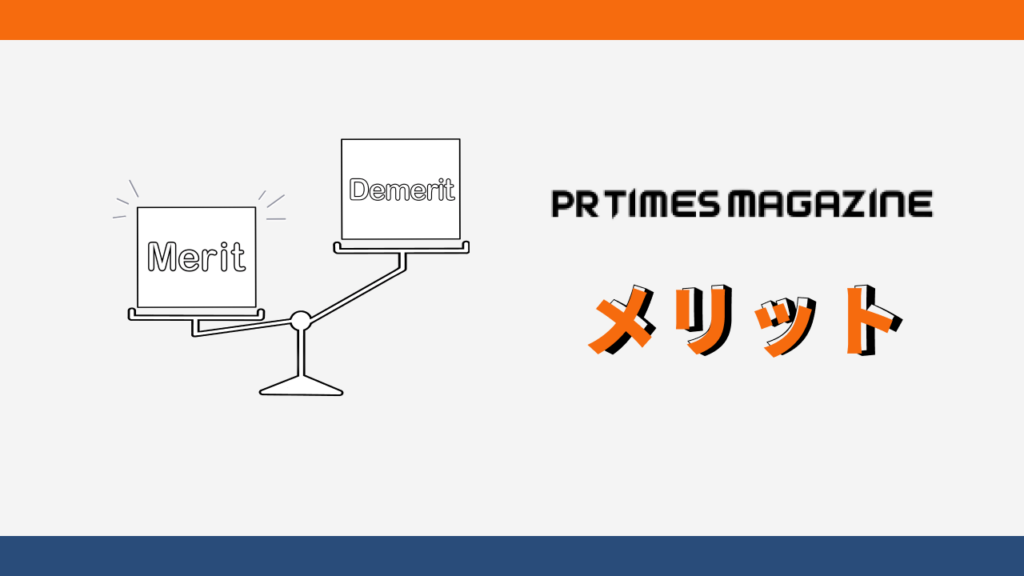
メリット1.自社の認知度向上
採用ブランディングに力を入れることにより、自社の認知度向上が期待できます。
採用ブランディングは、人材紹介サービスや求人広告以外にSNSや自社採用サイトなど、情報の発信方法が多岐にわたります。転職活動中や求職中の方から、まだ転職は考えていない方まで幅広い層に情報を届けられ、自社の認知度が向上しやすいというメリットがあります。自社のブランドイメージを広く浸透させることで、人材も獲得しやすくなります。
メリット2.入社後ミスマッチの防止・ロイヤリティが高い人の獲得
採用ブランディングは、経営理念や価値観、経営戦略などを理解・浸透させて自社のファンを作る活動です。待遇面で納得していることはもちろん、業務内容や全社の取り組みに共感した愛社精神や帰属意識の強い人を獲得しやすくなります。
そうした人材は応募時点でロイヤリティが高いため、既存の従業員とも同じ方向を向いて業務を行ったり議論したりすることも可能です。組織力強化の面でもメリットがあります。
メリット3.採用コスト削減
採用活動は、かけたコストに対して応募者が少なかったり、集まった人材の質が低かったりと難しい点が多く、想像以上に費用がかかります。採用ブランディングは、そうした採用コストの削減にもつながるのがメリットです。
効果が期待できるまで時間はかかるものの、ブランディングが成功すれば、人材紹介サービスや求人広告を利用せずとも応募者が増えるため、まず全体の採用コストを大幅に削減できます。
経営理念やビジョン、ミッションなどに共感した人材が集まりやすくなるので入社後ミスマッチや内定者辞退も減らすことができ、再度採用活動を行う際にかかるコストの削減も可能です。
メリット4.応募者数の増加
採用ブランディングは、応募の母数を増やしたい場合にもメリットがあります。人材紹介サービスや求人広告は、短期的に見れば応募者が増加し効果があるものの、他社の募集や広告に埋もれてしまいやすく、長期的に見ると応募者数の増加が期待できません。
採用ブランディングに力を入れれば、自社の強みや他社との違いを明確にアピールすることができます。待遇以外の面で自社の魅力を増やせるので、結果的に応募者数の増加につながります。
メリット5.応募者の質の向上・多様化
応募者数の増加に加えて、応募者の質が向上するのも採用ブランディングに力を入れるメリットです。求人媒体への掲載は応募者数が増えることにはつながっても、企業側が求めるような人材が集まるとは限りません。
採用ブランディングでは、企業理念や経営の方針、企業としての存在意義などの情報を発信します。そうした自社ならではの魅力に共感した応募者が集まりやすくなるため、応募者の質やマッチ率の向上が期待できます。自身が心から共感し、貢献したいと思えるビジョンや理念のある企業で働きたいと考える、多様な方からのエントリーが得られることもメリットです。
採用ブランディングに取り組む際の3つのポイント
採用ブランディングに取り組む際、あるいは成功させる際は以下の3点を意識しましょう。実際にコンテンツを制作したり、オウンドメディアやSNSアカウントを開設したりする前に準備しておきたい内容でもあります。ブランディングに関わるメンバーでしっかりと議論し、話をまとめてから実際に採用ブランディングに向けた取り組みの動き出しを行いましょう。
ポイント1.全社的に取り組む
採用ブランディングは、採用担当者だけでなく全従業員の協力が必要な全社的な取り組みです。例えば、採用イベントで採用担当者が登壇するより、経営層やその部署の第一線で活躍する従業員が登壇した方が、経営理念や自社で働くことのやりがいを具体的に説明できます。イベント参加者からの質問や相談にも、熱意を持って答えられるでしょう。
全社的に取り組むことで、価値観を統一できるのもポイントです。オウンドメディアやSNSなどで発信している情報と従業員の言動が異なると、採用ブランディングにマイナスの影響を与えてしまいます。一貫したブランディングを行うという意味でも、全社的な協力は必要不可欠です。
ポイント2.中長期的な目標を立てる
短期的な採用において採用ブランディングは不向きであることを留意しておきましょう。通常、ブランドイメージの構築には数ヵ月〜年単位の時間がかかります。短期では効果が出ないため、中長期的な目標を立てて取り組むことが必要です。
中長期的な目標とは、例えば「オウンドメディア開設から1年後にはメディア経由の応募を◯倍にする」という目標などが挙げられます。採用ブランディングの取り組みによりどのような数値的変化が見られたら良いかを目標としましょう。
ポイント3.リソースを確保する
採用ブランディングを成功させるポイントは、一貫性と継続性を維持できるかどうかにあると言われています。
意外と見落とされがちなのが継続性を維持するためのリソースの確保です。特に、社内の人間のみで採用ブランディングを完結させたいと考えるのであれば、リソースを確保するために他業務の調整も必要なので、運用体制を明確にしつつ月間で必要な工数も具体的な数字で把握しておかなければなりません。
中長期的な目標にあわせて、取り組みたい施策を考えておけば必要なリソースの確保がしやすくなります。
Z世代・ミレニアル世代の採用における変化と対応
これから採用ブランディングを実施する際に知っておいてほしいのが、Z世代(1990年代後半~2010年頃生まれ)やミレニアル世代(1980年代~1990年代生まれ)の傾向です。これらの世代はデジタルネイティブであり、働く目的や価値観にも大きな変化が見られます。具体的には以下のような傾向が顕著です。
- 仕事の意義や社会貢献性を重視する
- ワークライフバランスや柔軟な働き方を重視する
- 企業の透明性や誠実さに敏感
- SNSや動画を通じた情報収集が日常的
こうした世代に響く採用ブランディングを実現するには、「理念共感」「社員のリアルな声」「等身大の情報発信」が不可欠です。SNSやショート動画、社員の日常を映すコンテンツなどを通じて、共感や信頼を生むコミュニケーションを設計しましょう。
採用ブランディングの方法
採用ブランディングを行うにはさまざまな方法があります。どれかひとつだけでなく複数の方法を組み合わせて、ブランド価値の最大化を図ることが一般的です。企業によってかけられる費用やリソースは異なるので、自社で実施可能かつ高い効果が期待できそうな方法を選択しましょう。
- 採用サイトを立ち上げ、採用に関するコンテンツを公開する
- 採用イベントの実施
- 企業説明会の実施
- SNSによる情報発信
- 採用パンフレット
- TVCM
採用ブランディングは長期間の取り組みが必要です。継続が可能かという観点からも検討しておくと、他業務の多忙さやコンテンツ不足などを理由に中途半端に終わってしまうということを防げます。
採用ブランディングで活用したい媒体・ツール
採用ブランディングの方法とあわせて知っておきたいのが、活用したい媒体・ツールです。オウンドメディア・各種SNS・プレスリリースの3つが主に活用されています。各媒体・ツールの活用方法を簡単に説明します。注意点や留意したいポイントについても解説しているので、その点も含めて自社で導入できそうかどうか検討する際の参考にしてみてください。
オウンドメディア
オウンドメディアは、採用ブランディングにおいて転職顕在層・転職潜在層に向けて自社が伝えたいメッセージを自由に発信できるツールです。テキストだけでなく写真を入れたりデザインを工夫したりと自由度が高く、他社との差別化もしやすいため、多くの企業が採用ブランディングの方法として活用しています。多くの情報を蓄積できるので、中長期的に効果が出る採用ブランディングには特に向いています。
多くのメリットがある一方で、運用コストがかかりやすいのは留意点。従業員へのインタビューや対談、従業員の寄稿などコンテンツの準備には、ある程度の時間と工数を必要とします。更新頻度や運用体制は無理のない範囲で考えましょう。
各種SNS
X(旧 Twitter)やInstagram、Wantedly、YOUTRUSTなど各種SNSは採用ブランディングでも活用することができます。企業の公式アカウントとは別に採用ブランディングに特化したアカウントを開設して運用します。
情報を素早く発信できたり、転職潜在層にも情報を届けたりできるのがメリット。企業と採用候補者の距離が近いため、親近感を与えることもできます。
一方で、SNS上の企業の発言は炎上につながるリスクをはらんでいます。明確な運用ルールを設けたり、投稿前には社内でダブルチェックを行ったりするなど、リスク管理が必要不可欠です。
プレスリリース
数は多くありませんが、プレスリリースも採用ブランディングで活用したい媒体・ツールのひとつです。プレスリリースは「プレス(press=報道機関)」と「リリース(release=発表、公開)」の単語を組み合わせた造語であり、企業が発表する公式な文章のことを指します。そのため、人事・採用に関する新情報をプレスリリースとして発信することが可能です。
例えば、採用イベントの実施や企業出展などの情報を発信したり、働き方に関する自社の取り組みを発信したりなどの活用方法が挙げられます。採用オウンドメディアのオープンや企業公式SNSアカウントの開設などをプレスリリースとして配信するのも良いでしょう。
採用ブランディングを実践する5ステップ
採用ブランディングは、単なる広報活動ではなく、戦略的に進めることで効果を最大化できます。実践する際の5つのステップについて解説します。

STEP1. 自社のブランドコンセプトを明確にする
まずは、自社がどんな存在で、どんな価値を社会や社員に提供しているのかを言語化します。企業理念、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)、カルチャー、働き方の特徴などを整理し、「自社らしさ」を明文化しましょう。この軸がすべての採用ブランディングの土台となります。
STEP2. ターゲット人材(ペルソナ)を設計する
次に、自社が求める理想の人材像を具体化します。年齢や職歴などの基本情報に加えて、価値観や仕事観、SNSの利用傾向、共感しやすいメッセージなども含めて設計しましょう。ペルソナの解像度が高いほど、響く情報発信が可能になります。
STEP3. 接点設計とチャネル選定を行う
次に、ターゲット人材が普段どこで情報を収集しているかを踏まえ、効果的なチャネルを選定します。先程紹介したような自社サイトや採用特設ページ、SNS、社員インタビュー記事、イベント登壇、プレスリリースなど、複数のタッチポイントを戦略的に設計しましょう。
STEP4. 社内巻き込みと実行体制を整える
採用ブランディングは採用担当だけでは完結できません。経営層や現場社員の協力が不可欠です。社内への理解促進、発信協力の依頼、インナーブランディングとの連携などを通じて、組織全体で取り組める体制を整えましょう。
STEP5. 効果検証と改善サイクルを回す
施策を実行した後は、数値的・定性的な視点で効果を検証します。どのチャネルからの流入が多いか、どんなコンテンツが反応を得ているか、実際に採用に至った人材はどんな共通点があるかなどを分析し、PDCAサイクルを回すことでブランディング精度を高めていきます。
採用ブランディングのKPI・効果測定方法
採用ブランディングは短期的な成果が見えづらい施策のため、定期的なKPI設定と効果測定が不可欠です。主なKPIには以下のようなものがあります。
- 認知・関心フェーズ:採用ページやオウンドメディアのPV数、SNSのフォロワー数、プレスリリースの閲覧数、エンゲージメント率など
- 接触・行動フェーズ:イベント参加者数、資料ダウンロード数、スカウト返信率、エントリー数の推移など
- 成果フェーズ:応募者の質(スキルやカルチャーフィット)、内定承諾率、入社後の定着率など
定性的な指標としては、候補者からの「共感したメッセージ」や「企業イメージに関する声」などをアンケートで収集し、改善に活かすことも重要です。
採用ブランディングの成功事例
ソフトバンクグループ株式会社は、オウンドメディアを用いて採用ブランディングに取り組んでいます。採用専門のサイトを開設し、採用に関する情報を一ヵ所に集約しているのが特徴です。
「トップメッセージ」として、創業者取締役・社長の想いを掲載しています。ソフトバンクグループが目指す将来像が明確になるだけでなく、熱いメッセージへの共感を生む設計になっています。他にも、ブランディングメッセージや会社概要を簡潔にまとめた10分の動画など、共感を生むようなコンテンツが充実しています。
それ以外にも従業員インタビューや従業員の対談などコンテンツが豊富で、実際の働き方や仕事のやりがいなどリアルな情報を届けています。
参照元:ソフトバンク「新卒採用」
採用ブランディングの失敗パターンと注意点
採用ブランディングには効果が見えづらいという特性があり、間違った進め方をすると逆効果になることもあります。以下はよくある失敗パターンです。
【1】目的が曖昧なまま発信を始めてしまう
ブランドの軸が定まっていないと、メッセージが一貫せず、逆に企業イメージがぼやけてしまいます。
【2】求職者目線に立っていない
自社の魅力を一方的に語るだけではなく、「どんな人が、なぜ共感するか」の視点を忘れないことが重要です。
【3】社内との連携が不十分
人事や広報だけで進めると、現場とのギャップが生まれやすく、発信内容が現実と乖離してしまいます。
【4】短期的な成果だけを求める
採用ブランディングは中長期的な投資。短期的な応募数だけにとらわれると、本質的な改善にはつながりません。
成功の鍵は、「自社らしさを言語化し、それを一貫して伝え続けること」。地道な継続がブランディングを育てていきます。
採用ブランディングで採用力を強化するとともに定着率向上も意識しよう
今後も日本の労働人口が減少し続けることを考慮すると、入社が決まった従業員のフォローを手厚くしたり、定期的にヒアリングを行ったりして定着率を上げるための取り組みも同時に行う必要があります。中長期的な計画と目標の指標にあらかじめ定着率も加えておけば、それに合わせたコンテンツの作成が可能です。
応募者数の増加や質の向上も大切ですが、入社した従業員が早期離職しないように、採用力を強化するとともに定着率向上も意識したブランディング活動を行っていきましょう。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事人的資本開示とは?義務化された19項目・例・情報開示ポイントを解説

- 次に読みたい記事企業活動のすべてが採用広報につながる【プレスリリース事例を徹底解説10選】|前田梨沙

- まだ読んでいない方は、こちらから採用ブログとは?10のネタ・始め方から運営方法のポイント・事例まで紹介

- このシリーズの記事一覧へ

